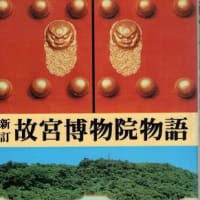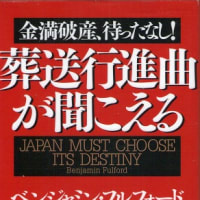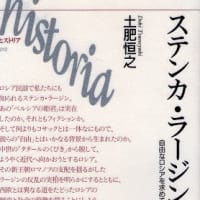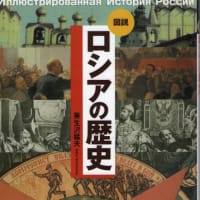例によって図書館から借りてきた本で、「なぜ戦争は終わらないか」という本を読んだ。
不思議な本だ。
ユーゴスラビアの内紛というか、その国の消滅を詳細に述べた本であった。
われわれ日本人にとってユーゴスラビアというのはあまりにも遠くて未知の国であった。
この内紛に関連して明石康氏や緒方貞子さんらが飛び回っていたことは、当時の日本のメデイアを通じて知らないわけではなかったが、そこで何が起きていたのかはさっぱり理解できていなかった。
理解しようとしても、なにせ現地の事情に疎いものだから、さっぱり要領を得なかった。
地球上どこにでも転がっている民族紛争ぐらいの認識しか持っていなかった。
しかし、この本の著者はこのユーゴに10年近くも住んでいたわけで、その紛争を肌を通じて感知してきたことは間違いなかろうと思う。
奥付けによると、この本の著者、千田善氏は1958年生まれ、昭和33年の生まれで、押しも押されもせぬ戦後世代である。
だとすると物の見方そのものが完全に戦後世代の物の見方になっている。
その意味で、我々旧世代のものからすると、いささかの違和感は免れない。
この本の主題は、ユーゴスラビアにはそれぞれたくさんの民族が同居して、それらがそれぞれに自己主張するので、戦乱が収まらないという主旨だ。
ところが、自己主張さえしなければそういう事態にはならない、ということを述べたかったと思う。
これは全くもって真理なわけで、まさしく戦乱の種、戦争の種は、お互いの自己主張に原因があることは当然であるが、ならば人間は自己主張なしで生きられるかという点に尽きる。
本文中に、数ある部族の中で、マケドニアはそのいう手法で以って、戦乱の渦に巻き込まれなかった時期もあったが、大統領が変われば他の部族と同じ道を歩むことになったわけで、そのことによって人々が幸福になったわけではないと、述べている。
不幸の到来がその分先伸ばしされただけで、結果的には、してもしなくても同じ結果を招いたことになる。
基本的に、人間は諍い続けながら生き延びるわけであって、諍いが避けられないものであるとするならば、それを克服する手段を常に考えて生きねばならないということである。
日本人の知識人としてアメリカを糾弾することは意図も安易に行われているが、アメリカが今日の世界で史上最高で最強の軍事国家ということは誰しも認めざるを得ない。
つまり世界のトップなわけで、トップの地位にいるということは、周りからは糾弾の嵐が吹き叫ぶわけで、それを擁護する論調は低調をきたし、それをあえて展開する者はいない。
ユーゴの紛争とは別の場面でも、アメリカのユニラテラリズム・唯我独尊的な行いを非難する論調は数々あれど、それは逆に、アメリカでさえも容易に解決できない難問を、迅速、かつ明快に決着できないことへの焦りのようでもある。
ユーゴの地での民族紛争が、乱れた麻のように輻輳した現状を、誰もが有効に解決できないままでいながら、その問題解決をアメリカにぶつけておいて、アメリカがそれをスムースに処理出来ないからといって非難しているようなものだ。
アメリカの力に頼る前に、自分たちでことを解決すれば、アメリカの出る幕は無いわけで、アメリカの出る幕がなければ、アメリカのユニラテラリズムもあり得ない。
それと、国連に対する期待においても、国連に紛争解決の手段と方法を期待する方が最初から間違っている。
国連というのは、わかりやすい例にたとえるならば、町内会で、町内会に入ったからといって町内のごたごたが一気に解決するというものでもなく、町内会に入ることと問題解決とは別の次元の話である。
町内のごたごたを提訴したから、そこで話し合いがもたれ、話し合ったらそれで一気に問題解決に向かうというものではない。
町内会のメンバーになったならば、メンバー同士のごたごたを、その長老が納得のいくように治めてくれるというようなものではない。
この地球上に生きている人間は、自然の真理に基づいて生きているわけで、理念や、理想や、知性や、理性で生きているわけではない。
人間は本来持っている人間としての欲望に支配されて、自然の欲求に基づいて生きているわけで、ユーゴスラビアの内紛もその顕著な例である。
この本の著者も単純明快に答えているが、その内紛の根源は領土問題である。
それぞれの民族にとって「生きるべき土地を如何に確定するか」という問題である。
旧ユーゴスラビアも第2次世界大戦後は共産主義国の一員として東側陣営の中にいたわけで、その時には共産主義という大きな重しが、そこに住む様々な民族の上に均等に被さっていた。
ところが旧ソビエット連邦が崩壊すると、その重しがなくなってしまったわけで、言葉は悪いが、いわゆる言いたい放題ものが言える時代が来たわけである。
共産主義の抑圧から解かれて見ると、「俺たちの土地は一体どこなんだ!」という疑問がわいてきたわけである。
今までは様々な民族が様々に入り混じって住み分けていたが、自分の隣に気に入らないものがいることに何となく居心地の悪い思いをしていたものが、それを共産主義の手前、我慢していた。
ところが、それぞれに自由にものを言ってもいい状況に置かれると、自由にものを言うことが自己主張につながったわけである。
この自己主張で、意見や思考が合うもの同士が集まると、いわゆる民族意識というものが醸成され、それに様々な利害得失が絡み、紛争に発展したとみなさなければならない。
こういう場面で、あくまでも「血で血を洗う抗争は厭だ」と言って、妥協に妥協を重ねて隠忍自重することも、生き方の選択としてはありうるが、果たしてそれを受け入れるものがいるかどうかはわからない。
ユーゴスラビアの紛争というのは、ある意味で共産主義という抑圧の重しが取れたことによって、人間が原始の心に先祖返りしたことでもある。
昔も今も、学問を積んだ知識人は、頭の中が知識で一杯なものだから、何でもかんでも知識と学問で分析したり解明しようとするが、物事はもっと単純明快で、自然そのものを見つめていれば、事の次第はなるようにしかならないということが分かる。
この本の著者も、アメリカや国連がユーゴスラビアの内紛の解決に冷淡だ、ということを嘆いているが、それは言うまでもなく当然のことだ。
「アメリカは世界一の軍事力を持った国だから、ユーゴの内紛にもっと力を入れよ」と、願う方が最初から間違っている。
アメリカはアメリカの国益を図って行動しているわけで、アメリカの国益にとって利するものがない、という話に積極的になるわけがないではないか。
それに反し、国連というのは、最初から各国間の福祉に貢献すべく設立された組織なのだから、国益とか利害関係で行動を左右することは理念に反している。
アメリカも主権国家の一つとして国策を誤ることはたびたびある。
そのアメリカの国策の誤りを、部外者としての我々がとやかく言ったところで、アメリカは痛くも痒くもないないわけで、そういう批判に応じてアメリカが国策を変えるということもあり得ない。
この本の表題の「なぜ戦争は終わらないのか」という主題は、「ユーゴスラビアの内紛はなぜ終わらないのか」ということであって、我々のイメージしている戦争とはいささか異なっている。
戦争など、内紛であろうが、内戦であろうが、テロであろうが、無いに越したことは無い。
しかし、繰り返し繰り返し起きているわけで、そのことから見れば、これは人間のもって生れた業だと思う。
人間が生きるということは、平和と戦争の二つしかないわけで、平和でないときは戦争中ということである。
ならば、平和な時を長引かせればいいわけで、その為には如何なるノウハウがあるか、と考えればいい。
この本でも述べているように、ユーゴスラビアの内紛も、最初の内は話し合いでことを解決しようとしていたが、その話し合いが暗礁に乗り上げた時、それを武力で解決しようとしたから、それがエスカレートしたわけで、ここが最大のポイントである。
話し合いが暗礁に乗り上げた時、それを如何に切り抜けるかで戦争は回避されるが、ここで双方がそれぞれに少しずつ妥協すれば、最悪の事態は避けられるはずである。
ここで双方が妥協に応じれない、応じようとしないから、話し合いが暗礁に乗り上げ、我慢しきれなくなった方が、最初に拳を振り上げることになる。
妥協に応じれないという部分に、国益があり、それに付随した権益や権能があり、メンツがあり、誇りがあり、名誉が掛かっているわけで、そういうものを一切合催投げ捨てるとなれば、それは自死を意味するわけで、それを容認できるかどうかの問題にいきつく。
共産主義が世間を席巻していた時は、人々は言いたいことも言えず、それこそ耐えるのみであったが、その重しが取れたとたんに、今までの鬱憤が一気に息を吹き返して、収集がつかなくなったという図式であろう。
この地に10年も滞在した日本人から見ると、この紛争は日本でいえば青森の人と、東京の人と、名古屋の人と、大阪の人と、九州の人が、「俺の土地はどこだ」、「ここは俺の土地だから出て行け」、「お前は自分の仲間のところに行け」と言い合っている図のように見えるのではなかろうか。
その言い合いの中で、自己主張を押し通そうとするから、妥協点が見えず、最終的には殺し合いに発展しているわけで、その殺し合いには号令を掛けるリーダーが必要なことは言うまでもない。
今までは、狭い土地にいくつもの民族がひしめき合って生きてきたが、共産主義という共通の重しがなくなったとたんに、自分たちの我の応酬になったわけである。
世界的規模、あるいは地球規模でみれば、あくまでもコップの中の嵐にすぎないわけで、そんな些細な紛争に大国がシャシャリ出る方がおかしいわけで、それを期待するなどもっとおかしい話だと思う。
国連が介入してくることは、ある程度、整合性があるが、アメリカやNATOの出る幕ではないと思う。
国連は確かにこういう小さな紛争に介入しても許されるであろうが、国連は国連で万能ではないわけで、日本でいえば村と村の水争いのような紛争にまで介入するにはいささか小廻りが効かないように見える。
当事者がお互いに殺し合いをやめて、平和裏に生きる道を模索するほか、この地に平安は無いと思う。
領土を巡る争いといったところで、前世紀のような帝国主義的な植民地獲得戦争とは意味が違うわけで、要するに自分たちの住む場所の取り合いなわけで、部外者が介入できる筋合いのものではない。
アメリカが出てくれば、当然、空爆という手法を使うことは必然である。
アメリカだとて自分の国の兵士が殺されるのを黙って見ているわけにもいかないので、当然安全な場所からの攻撃という意味で空爆になるのは当然のことだ。
紛争解決のための話し合いというのも実に虚しいことの積み上げで、明石康さんでも緒方貞子さんでも、そういう虚しい実績の積み上げである程度の功績を挙げているが、当事者にはこういう仲介者の虚しさというのは理解しがたいことに違いない。
何度も何度も同じことの繰り返しの議論を積み上げて、妥協点を探るという行為は、実に敬虔な行為だと思うが、当事者からみれば、自分たちが得する事案は全くないわけで、きっと腹立たしい気持ちでいたに違いない。
彼らにしてみれば、目に見える形で相手からの妥協が欲しいわけで、そういう手土産もないまま、交渉の場に付くということは、相当に危険でもあったであろう。
民族紛争というのは実に無意味な争いである。
どちらが勝ったとしても勝利を祝うような気持ちにもならない虚しい行為だと思う。
民族の間のお互いの嫌悪感というのは、よくよく掘り下げて考えてみれば、長年の間に醸成され、人為的に作られた概念にすぎないわけで、科学的な根拠は全くない筈である。
問題は、この作られた概念にある。
自分たちの民族が統一国家として独立するということも、独立したからと言っていきなり裕福な国になれる訳でもなく、実態は今までの続きでしかないわけで、明らかに独立した、自主独立を獲得した、という概念の産物でしかない。
独立してもしなくても、今までの生活がいっぺんに良くなるものでもない。
しかし、このユーゴスラビアではそういう機運が高まって、それぞれに独立しようとしたが、したらしたで自分たちの領地を拡大しようという欲望が押さえられなくなった。
そこで自己主張の連鎖反応が起きて、際限なく殺し合いが継続するという事態を招いたのである。
何度も言うが、この内紛は、この地に住む人たちの、自分たちの問題なわけで、アメリカも国連もただの部外者にすぎない。
そういうものの介入に期待してはならないと思う。
この本の著者は旧ユーゴスラビアの民族紛争を戦争という言葉で一括りしているが、戦争という言葉をこういう使い方をしてはいけないのではなかろうか。
言葉というのは、人間の意志や、気持ちや、あらゆる事象を人に伝えるツールであるので、厳密な使い方をしないことには、その真意が伝わらないように思う。
広い意味では経済戦争とか、人材獲得戦争などと比喩的に使われることも往々にしてあるが、民族紛争とか、テロとの戦いを、戦争という言葉で言い表すことには妥当性があるだろうか。
人の殺し合いという意味では同じであるが、人が殺し合うということは人間・人類のもっている業のようなもので、太古から連綿と引き継がれてきた行為ではなかろうか。
戦争という状況下では、人が人を殺しても許されるということは、これも人間の都合によって都合よく定められた、人為的な概念であって、今に生きる人間は、それを容認している。
そもそも生きた人間の作る社会において、正しいとか正しくない、正義・不正義、善悪、善し悪しなどこういう思考そのものが、人間の作りだした人為的な概念にすぎないわけで、自然界の生き物の一種という視点からみれば、人類・人間の奢りではないかと思う。
生き物の一種族としての人間の在り方も、基本的には弱肉強食の世界で、優勝劣敗という自然の法則に支配されているわけで、そこでは同情とか、慈愛とか、博愛という感情が入り込むこと自体、人類・人間の奢りではないかと思う。
人間は「考える葦」と言われているが、その「考える」という行為が、人為的な概念を作りだしているのではなかろうか。
太古の人々は、戦争も天変地変と同じ感覚で受け入れていたのではなかろうか。
地震、雷、火事、親父というのが日本人としての怖い物の代表として認知されているが、天災とか自然災害というのは諦めがつく。
しかし、戦争も普通の人々にとっては、災害と同じようなもので、人為的には何らコントロールのきかないものという認識であったのではないかと思う。
戦争も「人々の努力で回避できるものだ!」という認識は、ずいぶん後になってから生まれ出た概念であって、これも人々が頭の中で描いた人為的な概念の一つではなかったかと思う。
人々が殺し合うという現象・事象は、人間の誕生以来、連綿と継続された人々の生き様である。
人々は、この世に誕生して以来、お互いに殺し合って生きてきたように思う。
今日の平和な日本においても、親の子殺し、子の親殺し、怨恨による殺し、金の貸借にかかわる殺し、全く理由のない無差別殺人、こういうものが日常生活の中にごろごろあるのに、戦争による殺し合いだけが罷りならぬ、という論法も全く整合性に欠けるではないか。
日本の平和主義の人たちも、われわれの周りで起きている日常的な殺し合いに対しては、どう考えているのであろう。
テレビドラマは毎日毎日殺しのテクニックを開陳しているわけで、毒殺、扼殺、車を使った轢き殺し、突き落とし、刃ものによる殺傷などなど、殺人のノウハウをこれでもかこれでもかと見せびらかしているではないか。
「はぐれ刑事純情派」、「相棒」、「水戸黄門」などなど、必ず人が殺される場面が登場しているではないか。
これは人間というものが如何に人を殺すことに執着しているかということだと思う。
我々の身の回りの殺し合いは刑法で管理されていると言ってもいい。
しかし、主権国家同士の殺し合いは、これを裁く法律というものが存在していない。
あるにはあるが、それを実効あらしめ、管理し、維持し、権威を持った組織がないので、弱肉強食の自然の原理が作用して、極めて不整合な効果しかえられない。
公平な措置が取られないので、不平不満、不信感の連鎖反応が起きて、再び自然界の原理に帰趨して、強い国の我を飲まざるを得ないということになる。
不思議な本だ。
ユーゴスラビアの内紛というか、その国の消滅を詳細に述べた本であった。
われわれ日本人にとってユーゴスラビアというのはあまりにも遠くて未知の国であった。
この内紛に関連して明石康氏や緒方貞子さんらが飛び回っていたことは、当時の日本のメデイアを通じて知らないわけではなかったが、そこで何が起きていたのかはさっぱり理解できていなかった。
理解しようとしても、なにせ現地の事情に疎いものだから、さっぱり要領を得なかった。
地球上どこにでも転がっている民族紛争ぐらいの認識しか持っていなかった。
しかし、この本の著者はこのユーゴに10年近くも住んでいたわけで、その紛争を肌を通じて感知してきたことは間違いなかろうと思う。
奥付けによると、この本の著者、千田善氏は1958年生まれ、昭和33年の生まれで、押しも押されもせぬ戦後世代である。
だとすると物の見方そのものが完全に戦後世代の物の見方になっている。
その意味で、我々旧世代のものからすると、いささかの違和感は免れない。
この本の主題は、ユーゴスラビアにはそれぞれたくさんの民族が同居して、それらがそれぞれに自己主張するので、戦乱が収まらないという主旨だ。
ところが、自己主張さえしなければそういう事態にはならない、ということを述べたかったと思う。
これは全くもって真理なわけで、まさしく戦乱の種、戦争の種は、お互いの自己主張に原因があることは当然であるが、ならば人間は自己主張なしで生きられるかという点に尽きる。
本文中に、数ある部族の中で、マケドニアはそのいう手法で以って、戦乱の渦に巻き込まれなかった時期もあったが、大統領が変われば他の部族と同じ道を歩むことになったわけで、そのことによって人々が幸福になったわけではないと、述べている。
不幸の到来がその分先伸ばしされただけで、結果的には、してもしなくても同じ結果を招いたことになる。
基本的に、人間は諍い続けながら生き延びるわけであって、諍いが避けられないものであるとするならば、それを克服する手段を常に考えて生きねばならないということである。
日本人の知識人としてアメリカを糾弾することは意図も安易に行われているが、アメリカが今日の世界で史上最高で最強の軍事国家ということは誰しも認めざるを得ない。
つまり世界のトップなわけで、トップの地位にいるということは、周りからは糾弾の嵐が吹き叫ぶわけで、それを擁護する論調は低調をきたし、それをあえて展開する者はいない。
ユーゴの紛争とは別の場面でも、アメリカのユニラテラリズム・唯我独尊的な行いを非難する論調は数々あれど、それは逆に、アメリカでさえも容易に解決できない難問を、迅速、かつ明快に決着できないことへの焦りのようでもある。
ユーゴの地での民族紛争が、乱れた麻のように輻輳した現状を、誰もが有効に解決できないままでいながら、その問題解決をアメリカにぶつけておいて、アメリカがそれをスムースに処理出来ないからといって非難しているようなものだ。
アメリカの力に頼る前に、自分たちでことを解決すれば、アメリカの出る幕は無いわけで、アメリカの出る幕がなければ、アメリカのユニラテラリズムもあり得ない。
それと、国連に対する期待においても、国連に紛争解決の手段と方法を期待する方が最初から間違っている。
国連というのは、わかりやすい例にたとえるならば、町内会で、町内会に入ったからといって町内のごたごたが一気に解決するというものでもなく、町内会に入ることと問題解決とは別の次元の話である。
町内のごたごたを提訴したから、そこで話し合いがもたれ、話し合ったらそれで一気に問題解決に向かうというものではない。
町内会のメンバーになったならば、メンバー同士のごたごたを、その長老が納得のいくように治めてくれるというようなものではない。
この地球上に生きている人間は、自然の真理に基づいて生きているわけで、理念や、理想や、知性や、理性で生きているわけではない。
人間は本来持っている人間としての欲望に支配されて、自然の欲求に基づいて生きているわけで、ユーゴスラビアの内紛もその顕著な例である。
この本の著者も単純明快に答えているが、その内紛の根源は領土問題である。
それぞれの民族にとって「生きるべき土地を如何に確定するか」という問題である。
旧ユーゴスラビアも第2次世界大戦後は共産主義国の一員として東側陣営の中にいたわけで、その時には共産主義という大きな重しが、そこに住む様々な民族の上に均等に被さっていた。
ところが旧ソビエット連邦が崩壊すると、その重しがなくなってしまったわけで、言葉は悪いが、いわゆる言いたい放題ものが言える時代が来たわけである。
共産主義の抑圧から解かれて見ると、「俺たちの土地は一体どこなんだ!」という疑問がわいてきたわけである。
今までは様々な民族が様々に入り混じって住み分けていたが、自分の隣に気に入らないものがいることに何となく居心地の悪い思いをしていたものが、それを共産主義の手前、我慢していた。
ところが、それぞれに自由にものを言ってもいい状況に置かれると、自由にものを言うことが自己主張につながったわけである。
この自己主張で、意見や思考が合うもの同士が集まると、いわゆる民族意識というものが醸成され、それに様々な利害得失が絡み、紛争に発展したとみなさなければならない。
こういう場面で、あくまでも「血で血を洗う抗争は厭だ」と言って、妥協に妥協を重ねて隠忍自重することも、生き方の選択としてはありうるが、果たしてそれを受け入れるものがいるかどうかはわからない。
ユーゴスラビアの紛争というのは、ある意味で共産主義という抑圧の重しが取れたことによって、人間が原始の心に先祖返りしたことでもある。
昔も今も、学問を積んだ知識人は、頭の中が知識で一杯なものだから、何でもかんでも知識と学問で分析したり解明しようとするが、物事はもっと単純明快で、自然そのものを見つめていれば、事の次第はなるようにしかならないということが分かる。
この本の著者も、アメリカや国連がユーゴスラビアの内紛の解決に冷淡だ、ということを嘆いているが、それは言うまでもなく当然のことだ。
「アメリカは世界一の軍事力を持った国だから、ユーゴの内紛にもっと力を入れよ」と、願う方が最初から間違っている。
アメリカはアメリカの国益を図って行動しているわけで、アメリカの国益にとって利するものがない、という話に積極的になるわけがないではないか。
それに反し、国連というのは、最初から各国間の福祉に貢献すべく設立された組織なのだから、国益とか利害関係で行動を左右することは理念に反している。
アメリカも主権国家の一つとして国策を誤ることはたびたびある。
そのアメリカの国策の誤りを、部外者としての我々がとやかく言ったところで、アメリカは痛くも痒くもないないわけで、そういう批判に応じてアメリカが国策を変えるということもあり得ない。
この本の表題の「なぜ戦争は終わらないのか」という主題は、「ユーゴスラビアの内紛はなぜ終わらないのか」ということであって、我々のイメージしている戦争とはいささか異なっている。
戦争など、内紛であろうが、内戦であろうが、テロであろうが、無いに越したことは無い。
しかし、繰り返し繰り返し起きているわけで、そのことから見れば、これは人間のもって生れた業だと思う。
人間が生きるということは、平和と戦争の二つしかないわけで、平和でないときは戦争中ということである。
ならば、平和な時を長引かせればいいわけで、その為には如何なるノウハウがあるか、と考えればいい。
この本でも述べているように、ユーゴスラビアの内紛も、最初の内は話し合いでことを解決しようとしていたが、その話し合いが暗礁に乗り上げた時、それを武力で解決しようとしたから、それがエスカレートしたわけで、ここが最大のポイントである。
話し合いが暗礁に乗り上げた時、それを如何に切り抜けるかで戦争は回避されるが、ここで双方がそれぞれに少しずつ妥協すれば、最悪の事態は避けられるはずである。
ここで双方が妥協に応じれない、応じようとしないから、話し合いが暗礁に乗り上げ、我慢しきれなくなった方が、最初に拳を振り上げることになる。
妥協に応じれないという部分に、国益があり、それに付随した権益や権能があり、メンツがあり、誇りがあり、名誉が掛かっているわけで、そういうものを一切合催投げ捨てるとなれば、それは自死を意味するわけで、それを容認できるかどうかの問題にいきつく。
共産主義が世間を席巻していた時は、人々は言いたいことも言えず、それこそ耐えるのみであったが、その重しが取れたとたんに、今までの鬱憤が一気に息を吹き返して、収集がつかなくなったという図式であろう。
この地に10年も滞在した日本人から見ると、この紛争は日本でいえば青森の人と、東京の人と、名古屋の人と、大阪の人と、九州の人が、「俺の土地はどこだ」、「ここは俺の土地だから出て行け」、「お前は自分の仲間のところに行け」と言い合っている図のように見えるのではなかろうか。
その言い合いの中で、自己主張を押し通そうとするから、妥協点が見えず、最終的には殺し合いに発展しているわけで、その殺し合いには号令を掛けるリーダーが必要なことは言うまでもない。
今までは、狭い土地にいくつもの民族がひしめき合って生きてきたが、共産主義という共通の重しがなくなったとたんに、自分たちの我の応酬になったわけである。
世界的規模、あるいは地球規模でみれば、あくまでもコップの中の嵐にすぎないわけで、そんな些細な紛争に大国がシャシャリ出る方がおかしいわけで、それを期待するなどもっとおかしい話だと思う。
国連が介入してくることは、ある程度、整合性があるが、アメリカやNATOの出る幕ではないと思う。
国連は確かにこういう小さな紛争に介入しても許されるであろうが、国連は国連で万能ではないわけで、日本でいえば村と村の水争いのような紛争にまで介入するにはいささか小廻りが効かないように見える。
当事者がお互いに殺し合いをやめて、平和裏に生きる道を模索するほか、この地に平安は無いと思う。
領土を巡る争いといったところで、前世紀のような帝国主義的な植民地獲得戦争とは意味が違うわけで、要するに自分たちの住む場所の取り合いなわけで、部外者が介入できる筋合いのものではない。
アメリカが出てくれば、当然、空爆という手法を使うことは必然である。
アメリカだとて自分の国の兵士が殺されるのを黙って見ているわけにもいかないので、当然安全な場所からの攻撃という意味で空爆になるのは当然のことだ。
紛争解決のための話し合いというのも実に虚しいことの積み上げで、明石康さんでも緒方貞子さんでも、そういう虚しい実績の積み上げである程度の功績を挙げているが、当事者にはこういう仲介者の虚しさというのは理解しがたいことに違いない。
何度も何度も同じことの繰り返しの議論を積み上げて、妥協点を探るという行為は、実に敬虔な行為だと思うが、当事者からみれば、自分たちが得する事案は全くないわけで、きっと腹立たしい気持ちでいたに違いない。
彼らにしてみれば、目に見える形で相手からの妥協が欲しいわけで、そういう手土産もないまま、交渉の場に付くということは、相当に危険でもあったであろう。
民族紛争というのは実に無意味な争いである。
どちらが勝ったとしても勝利を祝うような気持ちにもならない虚しい行為だと思う。
民族の間のお互いの嫌悪感というのは、よくよく掘り下げて考えてみれば、長年の間に醸成され、人為的に作られた概念にすぎないわけで、科学的な根拠は全くない筈である。
問題は、この作られた概念にある。
自分たちの民族が統一国家として独立するということも、独立したからと言っていきなり裕福な国になれる訳でもなく、実態は今までの続きでしかないわけで、明らかに独立した、自主独立を獲得した、という概念の産物でしかない。
独立してもしなくても、今までの生活がいっぺんに良くなるものでもない。
しかし、このユーゴスラビアではそういう機運が高まって、それぞれに独立しようとしたが、したらしたで自分たちの領地を拡大しようという欲望が押さえられなくなった。
そこで自己主張の連鎖反応が起きて、際限なく殺し合いが継続するという事態を招いたのである。
何度も言うが、この内紛は、この地に住む人たちの、自分たちの問題なわけで、アメリカも国連もただの部外者にすぎない。
そういうものの介入に期待してはならないと思う。
この本の著者は旧ユーゴスラビアの民族紛争を戦争という言葉で一括りしているが、戦争という言葉をこういう使い方をしてはいけないのではなかろうか。
言葉というのは、人間の意志や、気持ちや、あらゆる事象を人に伝えるツールであるので、厳密な使い方をしないことには、その真意が伝わらないように思う。
広い意味では経済戦争とか、人材獲得戦争などと比喩的に使われることも往々にしてあるが、民族紛争とか、テロとの戦いを、戦争という言葉で言い表すことには妥当性があるだろうか。
人の殺し合いという意味では同じであるが、人が殺し合うということは人間・人類のもっている業のようなもので、太古から連綿と引き継がれてきた行為ではなかろうか。
戦争という状況下では、人が人を殺しても許されるということは、これも人間の都合によって都合よく定められた、人為的な概念であって、今に生きる人間は、それを容認している。
そもそも生きた人間の作る社会において、正しいとか正しくない、正義・不正義、善悪、善し悪しなどこういう思考そのものが、人間の作りだした人為的な概念にすぎないわけで、自然界の生き物の一種という視点からみれば、人類・人間の奢りではないかと思う。
生き物の一種族としての人間の在り方も、基本的には弱肉強食の世界で、優勝劣敗という自然の法則に支配されているわけで、そこでは同情とか、慈愛とか、博愛という感情が入り込むこと自体、人類・人間の奢りではないかと思う。
人間は「考える葦」と言われているが、その「考える」という行為が、人為的な概念を作りだしているのではなかろうか。
太古の人々は、戦争も天変地変と同じ感覚で受け入れていたのではなかろうか。
地震、雷、火事、親父というのが日本人としての怖い物の代表として認知されているが、天災とか自然災害というのは諦めがつく。
しかし、戦争も普通の人々にとっては、災害と同じようなもので、人為的には何らコントロールのきかないものという認識であったのではないかと思う。
戦争も「人々の努力で回避できるものだ!」という認識は、ずいぶん後になってから生まれ出た概念であって、これも人々が頭の中で描いた人為的な概念の一つではなかったかと思う。
人々が殺し合うという現象・事象は、人間の誕生以来、連綿と継続された人々の生き様である。
人々は、この世に誕生して以来、お互いに殺し合って生きてきたように思う。
今日の平和な日本においても、親の子殺し、子の親殺し、怨恨による殺し、金の貸借にかかわる殺し、全く理由のない無差別殺人、こういうものが日常生活の中にごろごろあるのに、戦争による殺し合いだけが罷りならぬ、という論法も全く整合性に欠けるではないか。
日本の平和主義の人たちも、われわれの周りで起きている日常的な殺し合いに対しては、どう考えているのであろう。
テレビドラマは毎日毎日殺しのテクニックを開陳しているわけで、毒殺、扼殺、車を使った轢き殺し、突き落とし、刃ものによる殺傷などなど、殺人のノウハウをこれでもかこれでもかと見せびらかしているではないか。
「はぐれ刑事純情派」、「相棒」、「水戸黄門」などなど、必ず人が殺される場面が登場しているではないか。
これは人間というものが如何に人を殺すことに執着しているかということだと思う。
我々の身の回りの殺し合いは刑法で管理されていると言ってもいい。
しかし、主権国家同士の殺し合いは、これを裁く法律というものが存在していない。
あるにはあるが、それを実効あらしめ、管理し、維持し、権威を持った組織がないので、弱肉強食の自然の原理が作用して、極めて不整合な効果しかえられない。
公平な措置が取られないので、不平不満、不信感の連鎖反応が起きて、再び自然界の原理に帰趨して、強い国の我を飲まざるを得ないということになる。