このところ、2月にしては暖かい日が続いています。このような陽気になると、西行法師の「願わくば はなのしたにて春死なむ そのきさらぎの 望月のころ」という歌が思い出されます。
西行法師は、その願いどおり、建久元年2月16日に入滅したそうですが、私は長い間、疑問に思っていたことがあります。それは、はな(花)は「桜」、きさらぎ(如月)は「2月」とすると、桜が2月に咲くというのは早過ぎると思えるからです。
最近になって、やっとこの謎が解けました。陰暦の基本的な約束事として、2月には春分がなければなりません。言いかえれば、ある朔の日から次の朔の日の前日までの、どの日かが春分であれば、その暦月が2月になるというのが陰暦のルールなのですから、きさらぎと言っても現在の3月になることは十分にあり得るわけです。
暦に関する豊富な情報をWEB上で提供している「こよみのページ」の和暦・西暦対応表示で確認してみると、西行法師が入滅したとされる建久元年2月16日は、西暦でいえば1190年3月30日となります。これなら、如月に桜が咲くのも不思議ではありませんね。
それにしても、自分の死期を歌い切るなんて、西行法師はすごい人ですね。私なんぞは、「願わくば はなのしたにて酒飲まむ その杯に もうちっと入れろ」ぐらいのことしか言えないのですが・・・
西行法師は、その願いどおり、建久元年2月16日に入滅したそうですが、私は長い間、疑問に思っていたことがあります。それは、はな(花)は「桜」、きさらぎ(如月)は「2月」とすると、桜が2月に咲くというのは早過ぎると思えるからです。
最近になって、やっとこの謎が解けました。陰暦の基本的な約束事として、2月には春分がなければなりません。言いかえれば、ある朔の日から次の朔の日の前日までの、どの日かが春分であれば、その暦月が2月になるというのが陰暦のルールなのですから、きさらぎと言っても現在の3月になることは十分にあり得るわけです。
暦に関する豊富な情報をWEB上で提供している「こよみのページ」の和暦・西暦対応表示で確認してみると、西行法師が入滅したとされる建久元年2月16日は、西暦でいえば1190年3月30日となります。これなら、如月に桜が咲くのも不思議ではありませんね。
それにしても、自分の死期を歌い切るなんて、西行法師はすごい人ですね。私なんぞは、「願わくば はなのしたにて酒飲まむ その杯に もうちっと入れろ」ぐらいのことしか言えないのですが・・・



















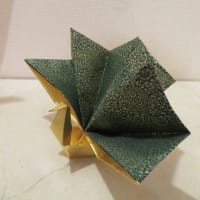
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます