熈代勝覧(きだいしょうらん)の舞台は日本橋通りのおよそ七町(760m)で、作者はその表店の商家と蔵、町木戸や自身番屋、橋や高札などのほか、そこで働いたり往来する人々の姿を実にきめ細かく描いています。

先ず目につく商家としては、呉服問屋、京糸物木綿太物問屋、絹紬木綿問屋、小間物問屋、袈裟衣問屋などの衣料品を扱う店で、三井越後屋の繁盛ぶりが伺えます。そして、瀬戸物問屋、指物屋、煙草問屋、煙管問屋、薬種問屋、紙問屋、小道具問屋、印版所、墨筆硯問屋などの生活用品を扱う店も軒を並べます。
飲食店や食材を扱う店も多く、鮨屋、二八蕎麦屋、汁粉餅・雑煮屋、お茶漬け屋、居酒屋、水飴屋、八百屋、酒問屋、蒲鉾屋、味噌問屋、乾物屋、仕出屋などが見られます。
いかにも江戸時代と思える店は、桐油合羽問屋、帳面問屋、算盤問屋、蝋燭問屋、紅問屋、白粉問屋、鏡師、笠・雪踏問屋、結納品問屋などですね。また、この時代は識字率が高かったと言われますが、それを裏づけるように書物問屋も多く見られます。変わったところでは御入歯所などという店もあります。


次に人に目を向けると、男女比は、男8割、女2割ほどで、江戸の町は男が多かったことが分かります。駕籠や馬に乗る武家の一行などもいますが、日本橋通りという土地柄から圧倒的に庶民の姿が多く描かれています。
大工や按摩といった時代劇にお馴染みの登場人物のほかに、行商の姿としては魚売り、菜売り、古着売り、薬売り、箍屋、竹笊売り、板売り、搗米屋、雪踏直し、水売り、木売り、付け木売り、菓子の立売り、刃物研ぎ、鬢付油売り、菓子の立売り、煙管売り、煙草売り、塗師、回り髪結、金山時味噌売りなどが往来を埋め尽くしています。
また、信仰に関わる人としては、琵琶法師、托鉢、虚無僧、本堂建立の勧進、巡礼、願人坊主、金毘羅参りなどの姿も少なくありません。そして、こんなことまでと思われるものとしては、手習い入門に机を持参する父と子、結納途上の一行、高齢者の引越し、喧嘩を仲裁する鳶なども丹念に描いています。
東京に行かれた折には、ぜひ東京メトロ「三越前」駅地下コンコースに足を運ばれることをお勧めします。なお、名橋「日本橋」保存会のホームページでも動画配信されていますので、こちらも一見の価値があると思います。

先ず目につく商家としては、呉服問屋、京糸物木綿太物問屋、絹紬木綿問屋、小間物問屋、袈裟衣問屋などの衣料品を扱う店で、三井越後屋の繁盛ぶりが伺えます。そして、瀬戸物問屋、指物屋、煙草問屋、煙管問屋、薬種問屋、紙問屋、小道具問屋、印版所、墨筆硯問屋などの生活用品を扱う店も軒を並べます。
飲食店や食材を扱う店も多く、鮨屋、二八蕎麦屋、汁粉餅・雑煮屋、お茶漬け屋、居酒屋、水飴屋、八百屋、酒問屋、蒲鉾屋、味噌問屋、乾物屋、仕出屋などが見られます。
いかにも江戸時代と思える店は、桐油合羽問屋、帳面問屋、算盤問屋、蝋燭問屋、紅問屋、白粉問屋、鏡師、笠・雪踏問屋、結納品問屋などですね。また、この時代は識字率が高かったと言われますが、それを裏づけるように書物問屋も多く見られます。変わったところでは御入歯所などという店もあります。


次に人に目を向けると、男女比は、男8割、女2割ほどで、江戸の町は男が多かったことが分かります。駕籠や馬に乗る武家の一行などもいますが、日本橋通りという土地柄から圧倒的に庶民の姿が多く描かれています。
大工や按摩といった時代劇にお馴染みの登場人物のほかに、行商の姿としては魚売り、菜売り、古着売り、薬売り、箍屋、竹笊売り、板売り、搗米屋、雪踏直し、水売り、木売り、付け木売り、菓子の立売り、刃物研ぎ、鬢付油売り、菓子の立売り、煙管売り、煙草売り、塗師、回り髪結、金山時味噌売りなどが往来を埋め尽くしています。
また、信仰に関わる人としては、琵琶法師、托鉢、虚無僧、本堂建立の勧進、巡礼、願人坊主、金毘羅参りなどの姿も少なくありません。そして、こんなことまでと思われるものとしては、手習い入門に机を持参する父と子、結納途上の一行、高齢者の引越し、喧嘩を仲裁する鳶なども丹念に描いています。
東京に行かれた折には、ぜひ東京メトロ「三越前」駅地下コンコースに足を運ばれることをお勧めします。なお、名橋「日本橋」保存会のホームページでも動画配信されていますので、こちらも一見の価値があると思います。



















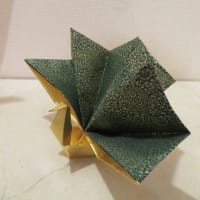
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます