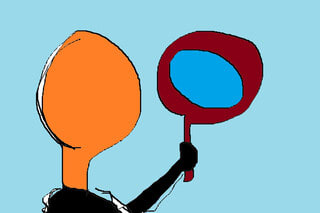
高倉院の法華堂の三昧僧、なにがしの律師とかやいふもの、ある時、鏡を取りて顔をつくづくと見て、我がかたちのみにくく、あさましき事を余りに心うく覚えて、鏡さへうとましき心地しければ、その後長く鏡を恐れて手にだに取らず、更に人にまじはる事なし。御堂のつとめばかりにあひて、籠り居たりと聞き侍りしこそ、ありがたく覚えしか。
鏡というものは怖ろしいものでいろいろな物が映っている。普段は自分の死角に入っているものすべてが映っているのである。自分の姿だけじゃないかといわれるかもしれないが、自分の姿とともにあるその物達は見え方が違う。
独歩や藤村がくろうしてつくりあげた風景の中の人間達は、いわば鏡に映っている物たちを前景化して、人物を縮小したようなものである。ここには何か心理的なからくりが必要だったはずで、明治時代の研究者がいろいろ苦労されて考えているところである。
その縮小に我々は耐えられなかったが、その際、自分をアイコン化することを覚えて苦労している。今日の授業では、そのあたりを扱った。
思うに、自分の鏡の中の姿を長い間無視してみることは、兼好法師も言うように案外効用がある。自分の顔を自分の認識と切り離して考えてみる段階が我々には必要だ。自己対話などと言う美名に惑われてはならぬ。
「鏡……。ほんとうに鏡が埋められていたのか。」と、わたしは炬燵の上からからだを乗出して訊いた。
「まったく古い鏡が出たのだから不思議です。」と、彼は小声に力をこめて言った。「お照がそれを掘出したところへ、染吉があとから来ました。染吉もまだ思い切れないので、今夜は日の暮れるのを待ちかねて、二本目の柳の下を掘りに来ると、お照がもう先廻りをしているので驚きました。どちらもあからさまに口へ出して言えることではありませんから、お互いにまあいい加減な挨拶などをしているうちに、お照がなにか鏡のようなものを袖の下にかくしているのを、常夜燈のひかりで染吉が見付けたのです。お照も早く常夜燈を消しておけばよかったのでしょうが、年が若いだけにそれ程の注意が行き届かなかったので、たちまち相手に見付けられてしまったのです。一方のお照が死んでいるので、詳しいことはわかりませんが、染吉はそれを見せろと言い、お照は見せないと言う。日は暮れている、あたりに人はなし、もうこうなれば仇同士の喧嘩になるよりほかはありません。なんといっても、染吉の方が年上ですし、お照は足が不自由という弱味もあるので、その鏡をとうとう染吉に奪い取られました。それを取返そうとしがみつくと、染吉ももうのぼせているので、持っている鏡で相手の額を力まかせに殴りつけた上に、池のなかへ突き落して逃げました。」
――岡本綺堂「鴛鴦鏡」
鏡よ鏡、と念じる魔法使いまでいたことからも分かるように、鏡というのは自らの意志を持つのである。だから埋められていた古い物など、何をしでかすかわからない。鏡を永い間みなかった法師も、ひょんのことで自分を瞥見する羽目になったときに、案外自分を美しいと思うこともある。人生はそこからが問題だ。









