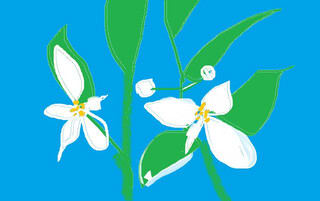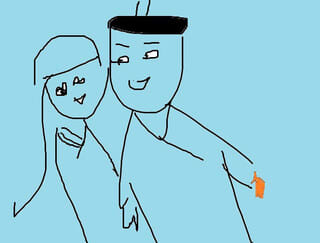言ひつづくれば、みな源氏物語・枕草子などにこと古りにたれど、同じ事、また、いまさらに言はじとにもあらず。おぼしき事言はぬは腹ふくるるわざなれば、筆にまかせつつ、あぢきなきすさびにて、かつ破り捨つべきものなれば、人の見るべきにもあらず。
思っていることを言わないことをお腹が膨れてくるかんじなんだそうだが、わたくしのお腹もそうであったのか。毎日言いたいことを書いていてもそうであるのか。たしかに、大学に行っただけでなんとなくストレスのたまる我々はお腹がでたひとが多いようである。
むかし、論文を書けば書くほど太っているのは絶対おかしいと萬★学の先生に怒られたことがある。中年になってもまったく太っていなかった先生はいろいろなことに気を遣って全力運転であった。わたくしはそこまでの能力もないのだ。
汽車に乗り込んで一時間も経った頃から、私はだんだん空腹に悩まされ始めてきた。それはそうだろう。前の日の昼飯(それも船酔いをおもんぱかって少量)を食っただけで、あとは何も食べていないし、それに中学二年というと食い盛りの頃だ。その上汽車の振動という腹へらしに絶好の条件がそなわっている。おなかがすかないわけがない。蘇澳で弁当を買って乗ればよかったと、気がついてももう遅い。
昼頃になって、私は眼がくらくらし始めた。停車するたびに、車窓から首を出すのだが、弁当売りの姿はどこにも見当らぬ。もう何を見ても、それが食い物に見えて、食いつきたくなってきた。海岸沿いを通る時、沖に亀山島という亀にそっくりの形の島があって、私はその島に対しても食慾を感じた。あの首をちょんとちょん切って、甲羅をはぎ、中の肉を食べたらうまかろうという具合にだ。
――梅崎春生「腹のへった話」
そういえば、わたくしは小学校後半まであまり食い気がなく、食欲もわかなかった。湧いてきたのは大学頃だったような気がする。こういうわたくしからすると、梅崎の話もまったく理解不能である。もっとも、梅崎の話は、食うや食わずの人々がたくさんいたことと裏腹なのだ。