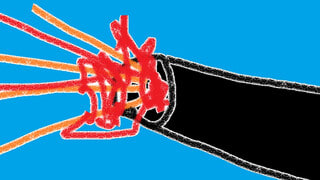余、年、志学にして外氏阿二千石文学の舅に就いて伏膺し鑚仰す。二九にして槐市に遊聴す。雪蛍を猶怠れるに拉ぎ、縄錐の勤めざるに怒る。爰に一の沙門有り。余に虚空蔵聞持の法を呈す。其の経に説かく、「若し人、法に依つて此の真言一百万遍を誦すれば、即ち一切の教法の文義諳記することを得」。
三教指帰の最初に出てくる、この虚空蔵聞持の法ってやっぱいいとこついてんだろう。暗唱を中心とする猛勉強は今も昔も一種の世界を把握する神秘体験であり、一度それ体験すると、もう娑婆には帰れないわけだ。勉強しないと死ぬような体になってしまうのである。
それにしても、空海は結局、勉強していたら抜けられなくなってしまった、と言っているにすぎないが――これに比べて、優先順位をつけてまずは一位のものからやって行くみたいなみみっちいやり方をしている我々が駄目なわけである。どうしてこんな世の中に、こんなひどい人たちがいるの、という歎きがけっこうあり、そりゃそうだと思うが、我々が仕事の優先順位とやらをつけて自分のことを優先したからだよな、どうみても。空海みたいな猛烈な勉強家だと、勉強即ち世界であり、目の前に現れるモノから片っ端から解く他はない。かくして、池でもうどんでもなんでもござれである。
哲学の方から来た「中動態」という観念がみんなすきである。責任論や主体性論の余りのくだらなさに辟易した結果出てきた概念であることはわかる。しかし、よのなか議論よりも人間の方がつねにくだらなく出来ており、「中道隊」の群れみたいな感じになっている。それは、極端な事例をさけて――なにもしない主体である。で、その實そのなにもしないというのは主観の方からみた場合であって、びっくりするようなことを想定外として片付ける評論家精神である。寺田寅彦がむかし問題にしようとしてた偶然性とは、日本人のある行動とロシア革命とか、日本人のある行動とウクライナ侵攻のようなものの繋がりである。シュルレアリスムもそうで、解剖台での出会いは、猫がピアノを弾くのとは違って、現実の世界のことである。
そんなものを眺めるときには、優先順位をつけることはできない。