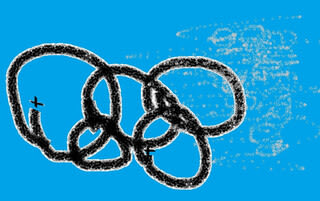
鎌倉の海に、鰹と言ふ魚は、かの境ひには、さうなきものにて、この比もてなすものなり。それも、鎌倉の年寄の申し侍りしは、「この魚、己れら若かりし世までは、はかばかしき人の前へ出づる事侍らざりき。頭は、下部も食はず、切りて捨て侍りしものなり」と申しき。かやうの物も、世の末になれば、上ざままでも入りたつわざにこそ侍れ。
わたくしは山国育ちのせいか、魚の種類がよくわからない。サンマとブリぐらいなら分かる。。。鰹のタタキもなんとなくおいしいとは思わないのであるが、細から「それはあまりおいしくないものを食べていたのであろう」と言われ、確かにおいしいものもあると最近発見した。だいたい、われわれは、おいしいものをその名前と一緒に認識する癖がつきすぎているのではなかろうか。
だいたいオリンピックも言葉の争いであるために、スポーツが魚のおいしさに似たものであることが忘れられ不幸なことである。音楽もまたスポーツであり、言葉の世界とは結びついているとはいえ、それとは別の時間のようなものを作り出している。オリンピックは、それらを言葉に従属させるような行事になりはててしまった。
先日、オリンピックを文化行事として思い出せみたいなことを書いた覚えがあるが、やや勘違いしていたかも知れない。我々が言葉の狂気である国家に対して文化をもって立ち向かうことは不可能であり、無理にやろうとすると、今日の開会式にみたいに、魂のテンションが不全であるところのメニューが雑然と並ぶことになる。無論、国家が、多様性みたいなモラルや観念と手を結んでいることが更に事態をややこしくしている。そのメニューの雑然さがやんわりと肯定されてしまうのである。これが一種の多くの精神に対する全体主義であることは言うを俟たない。
芸術やスポーツに必要なのは、無論、どこかで皆気付いているように、多様性や雑然さを目指したとしても、精神の専制なのである。我々が奪われているのはこれだ。
開会式の最後の音楽は、吉松隆の交響曲第二番であったが、この曲の精神の専制が実現されるためには、ボレロのあとではなく、ちゃんと第1楽章から始まっていなければならない。
思うに、オリンピックも、人しれず始まって終わらなければならないのであるが、今回は、怖ろしく無残な前奏曲が長く続いてしまった。だいたい、開会式の前のNHKのくだらない番組もひどかった。開会式さえも純粋に専制がゆるされないのだ。
こんなことが続けば、別の意味で専制的に五輪から離脱した北朝鮮が超然的によろしく見えてきてしまうではないか。トランプがよく見えた人がいたと同様の事態だ。
朝子は二三日、その事は忘れていた。七草過ぎの朝、島吉は七つ八つの女の子を連れて書きものをしている朝子の椽先に立った。そして、何とも言わずに朝子と女の子とを見較べて、うふふふふふと笑った。片眼が少し爛れているが、愛くるしい女の子だ。朝子は、ふと思い出して言った。「この女の子、この間言ったあんたのお嫁さんじゃないの」
島吉は矢張り、うふふふふふと笑って、「奥さんにおじぎしないかよ」と、女の子に命令するように言った。女の子は朝子に、ぴょこんと頭を下げてから、島吉を見て、
「あ は は は は」
と笑った。すると、島吉は矢庭に鋭い眼をして女の子を睨み込んだ。その眼は孤独で専制的な酋長の眼のように淋しく光っていた。
――岡本かの子「酋長」









