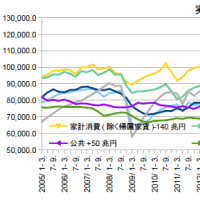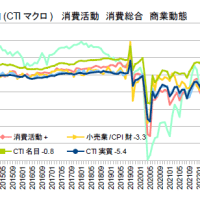少子化が進むのは、若者が結婚しにくくなったからで、結婚しにくいのは、経済的に苦しいからである。しかし、そこからは目を逸らして、結婚できた人への支援をもっと手厚くすることで、出生を増やそうと考える。子育てが大変という声は大きいが、非正規でカネがない者が「結婚できるようにしてほしい」と主張したりはしない。的を外し続けるのは、政治的な理由がある。
………
異次元の少子化対策は、メニューが出揃い、財源論に移っている。非正規への育児休業の拡大は入っているようだが、注目を集めるのは、児童手当の拡大だ。高校生への拡大、第3子以上への増額、所得制限の撤廃と、必要な施策とは思うが、それで出生が大きく増えるかというと、望み薄だろう。今、子供を持つか決める立場からは、高校生手当は15年後であり、第3子以上は出生の2割足らずである。まして、保育の充実は目に見えない。
少子化を緩和するには、若者の認識を変えなければならないのだから、非正規であっても育児休業給付があるから生活に困らないとか、高校までの学校教育費は児童手当で賄えるから心配いらないとかの明確なメッセージがいる。今は、非正規だと、給付も受けられないし、保育所にも預けられない。こうした政策上の「死の谷」が埋まるというアピールが必要であろう。
出生率は、コロナ前の2019年から大きく下がり始めている。このときの若者の雇用環境を見ると、25歳~34歳の男性の就業率は、2018年半ばに改善が止まって、2019年半ばには下がり出している。そして、コロナ禍で急落し、足下ではいくらか戻したものの、低迷したままである。女性がコロナを乗り越えて水準を上げているのとは対照的だ。若者の経済的な苦しさへのテコ入れがなければ、結婚への道は厳しい。
この1-3月期の出生数は、前年同期比-5.1%となり、当月を含む過去1年間で見ると、減少は深まっている。このペースだと、2023年の合計特殊出生率は、過去最低の2022年を更に下回り、1.1人台に転落するおそれもある。先行指標の婚姻も、当月を含む過去1年間が-5.3%となって、深刻さが増しており、コロナ禍が過ぎ去っても、いまだ反転が見られないところがつらい。
(図)

………
異次元の少子化対策の規模は3兆円程のようであり、1兆円程を保険料アップで賄うというのは、まあ予想どおりである。意外なのは、残りを社会保障費の削減で捻出するというもので、少子化によって国と地方の学校教育費の減少が見込まれるのに、対象になっていないらしいことだ。税収も大幅に増加しているし、財源についてより、少子化の深刻化が止まらないことの方が心配である。
(今日までの日経)
低成長で税収増の不思議 初の70兆円へ。円安と株高共振 円、半年ぶり140円。社保歳出改革、少子化対策最大1.1兆円捻出案。出生数、年70万人前半ペース 1~3月5.1%減18.2万人 「中位」割れも、婚姻再び減少 若者の結婚に支援乏しく。中国金融市場に3つの逆風 景気回復鈍化・デフレ懸念・海外資金流出。パート・バイトにも雇用保険、28年度までに。厚生年金加入漏れ100万人 従業員数の過少申告、後絶たず。
………
異次元の少子化対策は、メニューが出揃い、財源論に移っている。非正規への育児休業の拡大は入っているようだが、注目を集めるのは、児童手当の拡大だ。高校生への拡大、第3子以上への増額、所得制限の撤廃と、必要な施策とは思うが、それで出生が大きく増えるかというと、望み薄だろう。今、子供を持つか決める立場からは、高校生手当は15年後であり、第3子以上は出生の2割足らずである。まして、保育の充実は目に見えない。
少子化を緩和するには、若者の認識を変えなければならないのだから、非正規であっても育児休業給付があるから生活に困らないとか、高校までの学校教育費は児童手当で賄えるから心配いらないとかの明確なメッセージがいる。今は、非正規だと、給付も受けられないし、保育所にも預けられない。こうした政策上の「死の谷」が埋まるというアピールが必要であろう。
出生率は、コロナ前の2019年から大きく下がり始めている。このときの若者の雇用環境を見ると、25歳~34歳の男性の就業率は、2018年半ばに改善が止まって、2019年半ばには下がり出している。そして、コロナ禍で急落し、足下ではいくらか戻したものの、低迷したままである。女性がコロナを乗り越えて水準を上げているのとは対照的だ。若者の経済的な苦しさへのテコ入れがなければ、結婚への道は厳しい。
この1-3月期の出生数は、前年同期比-5.1%となり、当月を含む過去1年間で見ると、減少は深まっている。このペースだと、2023年の合計特殊出生率は、過去最低の2022年を更に下回り、1.1人台に転落するおそれもある。先行指標の婚姻も、当月を含む過去1年間が-5.3%となって、深刻さが増しており、コロナ禍が過ぎ去っても、いまだ反転が見られないところがつらい。
(図)

………
異次元の少子化対策の規模は3兆円程のようであり、1兆円程を保険料アップで賄うというのは、まあ予想どおりである。意外なのは、残りを社会保障費の削減で捻出するというもので、少子化によって国と地方の学校教育費の減少が見込まれるのに、対象になっていないらしいことだ。税収も大幅に増加しているし、財源についてより、少子化の深刻化が止まらないことの方が心配である。
(今日までの日経)
低成長で税収増の不思議 初の70兆円へ。円安と株高共振 円、半年ぶり140円。社保歳出改革、少子化対策最大1.1兆円捻出案。出生数、年70万人前半ペース 1~3月5.1%減18.2万人 「中位」割れも、婚姻再び減少 若者の結婚に支援乏しく。中国金融市場に3つの逆風 景気回復鈍化・デフレ懸念・海外資金流出。パート・バイトにも雇用保険、28年度までに。厚生年金加入漏れ100万人 従業員数の過少申告、後絶たず。