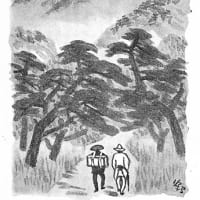日本近代文学の森へ 282 志賀直哉『暗夜行路』 169 爽やかな「竹さん」 「後篇第四 十六」 その3

2025.6.7
彼は机に凭(もた)れたまま開放しの書院窓をとおしてぼんやり戸外を眺めていた。座敷の前、三間ほどの所が白壁の低い土塀で、それから下が白っぽい苔の着いた旧い石垣で路、路から更らに二、三間下がって金剛院という寺がある。朝からの霧がまだ睛れず、その大きな萱屋根(かややね)が坐っている彼の眼の高さに鼠色に見えている。
彼はまだ何か書き足りないような気がした。それよりも直子には寝耳に水で何の事か分らぬかも知れぬという不安を感じた。急に自家(うち)が恋しくなり、発作的にこんな手紙を書いたと思われそうな気もした。彼は洋罫紙(ようけいし)の雑記帳を取り、その中から三枚ほど破って、余白に「こんなものを時々書いている」と書き、手紙に同封した。二、三日前この書院窓の所で蠅取蜘蛛(はえとりぐも)が小さな甲虫を捕り、とうとう、それが成功しなかった様子を精(くわ)しく書いておいたものだった。自分の生活の断片を知る足しになると思ったのだ。
手紙を書き終えた謙作は、しばし、ぼんやり外を眺める。「書院窓」からみえる光景が、カメラが移動していくかのように描かれる。視線は、土塀から石垣、路、金剛院へと移る。そうした「部分」を包みこむ「霧」が後から描かれ、視線は「大きな萱屋根」へと上昇する。映画なら、カメラをわざわざ移動して撮影することなく、ワンシーンで描くだろうが、この細かい移動は、やはり小説ならではのものだ。もちろん、映画でも、こうした移動撮影は可能だが、そんなことをすると、やけに大げさで何かそこに意味があるのかと勘ぐられてしまうだろう。
謙作は「書き足りない」ような気がする。自分の気持ちは丁寧に書いた。直子への思いもちゃんと書いた。でも、この手紙を書くに至った自分の心境というか、状況というか、そういうことを書いていないので、直子にとっては「寝耳に水」の手紙と思われるんじゃないだろうかと「不安」になったというのだ。
そんなことはないだろうとは思う。直子にしてみれば、待ちに待った手紙だ。びっくりはするだろうけど、「急に自家が恋しくなり、発作的にこんな手紙を書いたと」と直子が思うとは思えないが、そう思ったとしたら何が不都合なのだろうか。それは、恐らく、自分が「発作的」に、あらぬことを口走っているかのようの思われたら困るということだろう。自分は考えに考えた末にこういう心境に至ったのだということを、正確に直子に伝えたいのだろう。自分は、「発作的」にこんなことを考えたのではなく、自分は落ち着いているのだ。冷静なのだ。それを分かってほしい。そう思ったのだろう。
だから、ハエトリグモのことを書いた断片を同封したのだ。それにしても、ハエトリグモの観察の文章が、「自分の生活の断片を知る足しになると思った」というのはおもしろい。「ハエトリグモの失敗」の描写が「自分の生活の断片」なのだということは、この頃の謙作にとって、「小さな自然」がいかに重要な意味をもっていたかを示唆しているといえるだろう。これはあの『城の崎にて』とつながっている志賀文学の「芯」のようなものだ。
そういえば、しばらく読み返していないが、尾崎一雄の『虫のいろいろ』という短編も、こうした「自分の生活の断片」を記したものだ。志賀よりも、もっと即物的だったような気がするけど。
彼は買置きの煙草が断(き)れたので、それを買いかたがた、今の手紙を出しに河原を越し、鳥居の所まで行った。霧で湿ったバットをよく買わされるので、新しい函を開けさせ、その一つを吸って見てからいくつか買い、また同じ道を引還(ひきかえ)して来た。何となく、睛々した気持になっていた。彼は自分の部屋の窓から余分の煙草を擲込(なげこ)んで、今度は今行った方向とは反対の方へ出かけた。杉の葉の大きな塊が水気を含んで、重く、下を向いていくつも下がっている。彼はその下を行った。間からもれて来る陽が、濡れた下草の所々に色々な形を作って、それが眼に眩(まぶ)しかった。山の臭(にお)いが、いい気持だった。
タバコを買うついでに、手紙を出しに外へ出る。こんな単純で、当たり前なことが、現代では失われつつある。タバコは買わない、手紙は出さない。たとえタバコを買いがてら手紙を出しに出かけたることがあっても、こんな豊かな自然は、ない。まあ、100年も前の話なのだから、そんなことを言っても詮無きことだけど、でも、現代のぼくらが、生活の大切なディテールを喪失していることは確かで、それは不幸なことだと思う。しかし現代には現代の「生活のディテール」はきっとあるのだろう。でもそれは、ジイサンには分からないことだ。それはそれで仕方がない。
「バット」(念のために書いておくがこれはタバコの銘柄です。)一つ買うにも、いつも湿ってるから、函を明けさせて確かめてから買う、なんてことはそうはできないにしても(謙作の傲岸不遜ともいえる態度が垣間見える。それは一種の階級意識からくるものだろう。)、そこには自動販売機で買うことからは生まれない、人情の機微のようなもの、感情の揺らぎのようなものが、ある。
その後の、杉の下を歩いていく描写の素晴らしさ。書き写していても、うっとりとしてしまう。その緻密な描写のあとにくる、「山の臭いが、いい気持だった。」という小学生のような素朴で直接な言葉は、ぼくらの心をさっと明るくし、解放する。
路傍(みちばた)に山水(やまみず)を引いた手洗石(てあらいいし)があり、其所だけ路幅が広くなっている所で、竹さんが仕事をしていた。枝を拡げた大きな水楢(みずなら)がその辺一帯を被(おお)い、その葉越しの光りが、柔かく美しかった。竹さんは短く切った水楢の幹から折板(へぎ)を作っている。既に出来た分が傍(わき)に山と積んであった。彼を見ると、竹さんは軽いお辞儀をした。
「竹さん」の登場である。やっぱりこの人は重要人物なのだ。
「水楢」がさりげなく登場するが、スギや、ヤマザクラなんかと違って、この類いの木はみんな似ていて、「ミズナラ」「コナラ」「イヌシデ」「アカシデ」など、そんなに簡単に識別できるものではない。現代人は、よほどの趣味がないと、下手をするとイチョウだって識別できないだろう。
こういうところは、昔の文学者の知識というのはなかなかすごくて、謙作は一目で「ミズナラ」だと分かるわけである。ということは、志賀も知っているということだ。
ミズナラの「葉越しの光」、つまりは「木洩れ日」が「柔らかく美しかった」というのは、それを見たものにしか伝わらない。こうした光を「木洩れ日」と名づけたのは誰だったのだろう。
「日本国語大辞典」によれば、最古の用例は「「杉の木の間ものおもふわが顔のまへ木漏日(コモレビ)のかげに坐りたる犬」という若山牧水の歌(1911)だから、古語にはないようだ。国木田独歩の『武蔵野』とか、二葉亭四迷の『あひびき』あたりに出てきそうな言葉だが、出でこない。堀辰雄の『風立ちぬ』には、一例だけあった。ちなみに、英語にも中国語にも、「木洩れ日」にあたる特別な言い回しはないようだ。中国人の水墨画の師匠、姚先生にも伺ったら、そういう言葉もないし、そういう現象に注目もしないとのことだった。
で、この「折板(へぎ)」とは何だろう。辞書には、「杉または檜(ひのき)の材を薄くはいで作った板。」(日本国語大辞典)とあるが、これを何に使うかというと、この後の二人の会話で詳細に語られる。
「そんなに要(い)るのかね」
「どうして、この三倍位は要るんですよ」
「材料から拵(こしら)えてかかるのだから大変だな」謙作は其所に転がしてある、幹の一つに腰を下ろした。「第一こんな立派な木を無闇と伐(き)ってしまうのは勿体ない話じゃないか。やはりこの辺にある奴を伐るのかね」
「まあ、なるべく人の行かないような所から伐って来るんです」
「それにしても、そう木の多い山ではないから惜しいものだね」
「水屋の屋根にする位、知れたもんですよ」
竹さんはよく桶屋が使っている、折れた刀の両端に柄をつけたような刃物を、傍に置くと、カーキー色の古い乗馬ズボンのポケットからバットを出して吸い始めた。
「こんな大木を伐るのは、自分でやるのかしら」
「これは本職でないと駄目だね。本職の木挽(こびき)が挽(ひ)いて、持って来てくれるんです」
「そうだろうね」
「それはそうと、山へはいつ登ります?」
「僕はいつでもいいよ。竹さんの都合のいい時でいい」
「実は明日の晩、一卜組案内を頼まれているんだがね。学生四、五人という話で、それと一緒にどうです?」
「うん、いいよ」
「中学生なんか、かえって、無邪気でいいでしょう」
「そうだ」
濡れて、苔の一杯についた手洗石のふちに何か分らない、見馴れない虫がウヨウヨ這廻っている。桜にいる毛虫より小さく、黒い地肌の見える、毛の少い奴で、何千だか何万だか、重なり合って、脈を打っている。群をなしているのが堪らなかった。虫もこういうのに会っては興醒(きょうざめ)だと思った。
「やはり毛虫の類かね」
「昨日は一疋もいなかったが、今日急に出て来たね」
「普通の奴とは大分(だいぶん)異(ちが)うが、やはり、毛虫の類だろうな」
「……寺を十二時に出て、ゆっくり登って、頂上で御来迎(ごらいこう)を拝む事になるんだが、月があると楽なんだが、この頃は宵のうちに入ってしまうね」
「そうかな。月がないとすると提灯をつけて行くのか」
「晴れてさえいれば星明りで充分ですよ。登り出せば木がないからね。もっともその用意だけはして行くが」
「少し昼寝をしておかないと弱りそうだが、そいつが出来ないんで困る」
「夜、早く寝ておけばいい。いい頃に行って、私が起して上げましょう」
「そのまた、早寝も習慣で出来ないんだ」
「そりゃあ、困ったね」と竹さんは笑い出した。
竹さんは煙草を喫いおわると、足で踏消し、また仕事にかかった。謙作はいつも行く阿弥陀堂の方を廻って帰って来た。
この「折板」は、「水屋」の屋根に使うのだと分かる。「水屋」には、いろいろ意味があるが、ここでは「社寺の前にあって参詣人が手や口をすすぎ清めるための手水(ちようず)鉢を備えた吹放ちの建物。」(平凡社・世界大百科事典)の意味。「竹さん」は、寺の仕事をしているので、こういう仕事もあるのだろう。
この場面での物語進行上の大事なことは、山へは、明日の晩に行く事にきまったということだけなのだが、竹さんの仕事の細かい内容とか、突然現れた毛虫のこととか、ずいぶん余計なことが書き込まれている。この「余計なこと」が、小説の細部として、よく生きている。それがなくちゃ困るという情報ではないが、小説は、情報ではないのだ。
月がなければ、真っ暗だけど、それでも「星明かりで充分」というのは、「情報」としてではなくて、「情景」として美しい。月明かりで、真夜中の林道を歩いた経験は忘れがたいが、星明かりで歩いたという経験はついぞない。残念なことだ。
竹さんには、謙作の「不眠」が理解できない。「そりゃあ、困ったね」と笑う竹さんには、近代知識人の悩みは無縁なのである。それだけに、爽やかだ。