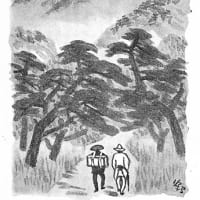日本近代文学の森へ (183) 志賀直哉『暗夜行路』 70 「弱さ」と「強さ」 「前篇第二 十」 その4
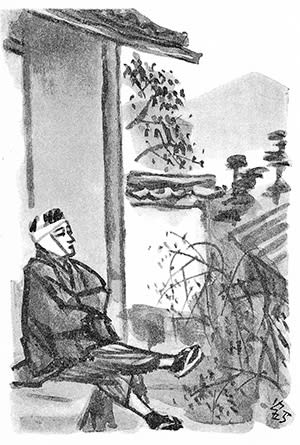
2021.1.27
「禅をやる事もお父さんに話したの?」
「話した。とても承知しまいと思ったが、例の(考えておこう)だから、大概いいだろうと思う。お前の事もあるし、重ねて、そんな話をするのは気の毒だったが、絶えずそういう気持で煮え切らない自分がいやで堪らなくなったのだ。今度の場合でもお前にはいつも或る一つの焦点があって、総ての針が直ぐそれを指すのが、俺は非常に羨しかった。ところで、俺にはその焦点がないのだ。ぐうたらな性格からも来ているが、今の俺の生活が悪いのだ。どうしても其処から建て直して行かなければ駄目だと思ったのだ」
謙作は父の信行に対する案外寛大な態度が、自分に対するそれと全く違うのをちょっと不快に感じた。しかしそれが当然な事とも思った。不快に思うのが間違っているとも思った。そして信行が自身の喜びから、謙作の気持に顧慮する余裕もなくむしろ自分のそうなる事で謙作を喜ばそうという、子供らしい、一種のフラッタリーさえあるのを見ると、謙作は信行に好意を感じないではいられなかった。しかし禅をやれば、そういう点で本統に安心出来る気でいそうな所が危なっかしい気もした。謙作は近頃の禅流行には或る反感を持っていた。
信行の悩みというのは、なんだかよく分かる気がする。生きている上での「焦点」がないという不満あるいは不安。まわりに流されてしまって、確固たる自分を持てない自分を信行は「自我が弱い」と言っていたが、そういう信行が、謙作をみて「羨ましい」と感じる気持ちはとてもよく分かるのだ。
ぼくの「自我」らしきものも、やっぱりそんなに強いものではなくて、常にフラフラしているから、「この道一筋」とか「思い込んだら百年目」とか「石の上にも三年」とかいった生き方をする人をテレビなんかでみると、「羨ましい」とまではいかないけれど、スゴいなあと感心してしまう。感心はしてしまうけど、「羨ましいとまではいかない」のは、どこかでそういう人のことを、「別世界の人」のように感じてしまうからだろう。「羨ましい」と思うというのは、なんとか努力すればその域に達することができるとどこかで思っているからで、世界が違うんだと思えば、「羨ましい」とすら思わない。
まあ、少なくとも、謙作という人間には、信行が言うほどの「強さ」を感じてはいない。信行には強く見えるということだろう。
父の態度が自分と信行とでは違うことに謙作は「不快」を感じるのだが、それは理性的に解消しうる「不快」さだったようだ。それよりも、信行に対する「好意」は、面白い観察から来ている。
「フラッタリー」とは「お世辞」とか「おべっか」という意味だが、自分のよころびを話すことで、相手も愉快になるだろうと考えるのが「子どもっぽいおべっか」なんだと考え、そんな信行に好意を感じる謙作は、決して我利我利亡者ではないのだ。むしろ、他者の心に敏感な人間なのだといえるだろう。
信行の言葉を真に受けて、信行は弱く、謙作は強いなんて思ってはならない。
謙作の「近頃の禅流行」に対する反感というのは、記憶に値する。
「行く寺は決めたの?」
「円覚寺へ行こうと思う。何といっても、SN は当代随一の人だからね」
謙作は黙っていた。
彼は何となくそのSN 和尚を好まなかった。三井集会所あたりでよく話をするSN を荒地に種蒔く人間のような気がして好まなかった。
しかし他にどういういい和尚があるかもまるで知らなかったから、彼は黙っていた。
このSN 和尚というのは実在しそうな感じだ。
円覚寺といえば、すぐに漱石の「門」が思い浮かぶ。「門」は明治43年の作品だから、この「暗夜行路」よりも十数年前ということになるが、漱石が参禅した頃も禅は流行していたのだろう。そういう流行に対する謙作の(あるいは志賀直哉の)醒めた意識が伺えて面白い。
SN 和尚を謙作が好まない理由が「荒地に種蒔く人間のような気がして」とあるのだが、これはいったいどういうことなのだろうか。「荒地に種蒔く人間」というのは、言うまでもなく聖書の言葉で、そこでは種蒔く人が否定されているのではなくて、「荒地」の方に問題があるとされていたはずだ。せっかくイエスの教えを聞いても、聞く人が「荒地」(聞く耳を持たない、受容性がない、など)だったら、その教えは決して実を結ばないということだろう。こういう文脈では、SN 和尚を好まない理由としてはどうも成り立たない話だが、しかし、どうせ無駄だと分かり切っているところで説教をする、ということで、謙作の好みじゃない、ということなのかもしれない。
この後、信行はほんとうに会社を辞めて、禅をやるために鎌倉に移住することになる。信行もけっこう「強い」。