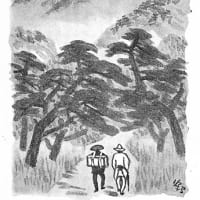日本近代文学の森へ 283 志賀直哉『暗夜行路』 170 「ChatGPT」の力を借りて 「後篇第四 十六」 その4

2025.6.21
今日の手紙は早くて、明後日(あさって)、隔日しか登って来ない郵便脚夫が今日来なければもう一日遅れて直子の手に入るわけだと思った。彼は机に向い、読みかけて、そのままになっていた、元三大師(がんさんだいし)の伝を読み始めた。よく田舎家の入口などに貼ってある元三大師鬼形(きぎょう)の像のいわれを面白く思った。上野にある両大師の一人が元三大師だという事も初めて知った。
よく言われることだが、今のネット社会からすれば、悠長な話である。といっても、そんなに大昔のことではない。つい50年ほど前、ぼくが学生だったころは、手紙をポストに入れてから、返事が返ってくるのは、はやくても1週間後ぐらいだったのではなかろうか。メールの返事が、翌日になってもない、なんて怒るのは贅沢というものだ。
家に帰った謙作は、読みかけになっている帝国文庫の『高僧伝』の元三大師のくだりを読み始めた。この元三大師というのは、文庫本の注によれば、「天台宗の僧、良源のこと。永観三年(九八五)正月三日に入滅したのでこう呼ばれた。」とある。この元三大師は、疫病などが流行したとき、自らが鬼の姿に変身して魔を退けたという伝説があり、その鬼になった姿を絵にしたのが「角大師(つのだいし)」で、この絵を玄関や門口にはっておくと、魔除けになるといわれ、大変にはやったらしい。これが、謙作が言う「よく田舎家の入口などに貼ってある元三大師鬼形(きぎょう)の像」だろう。
当時は、そんなお札はごく普通に見られたのだろうが、現在のぼくらがここを読んでも何のことやらわからない。ちなみに、ぼくもそんなお札は見たことがない。ただ一般に「厄除け大師」と言われるときの「大師」は、この「元三大師」を指すらしい。ただし、ぼくも行ったことがある川崎大師も厄除けで有名だが、それは「弘法大師」ということだ。また、今でもはやりの「おみくじ」も、元三大師が創始したという説がある。
などと知ったかぶりして書いているが、この辺は、ぜんぶ「ChatGPT」にぼくが質問して得た回答をまとめたもの。だから、絶対正しいっていえないかもしれないが、案外ちゃんとしているようだ。
それにしても、そろそろ大詰めだというのに、こんな寄り道をしていていいのだろうか。ここに元三大師が出てきてもこなくても、話の展開には関係なさそうなのだが。
さて、話はつぎのように展開する。
その時、彼は玄関に聴き馴れない男の声を聴いたが、自分に客のあるはずはなく、庫裏への客が間違えているのだろうと少時(しばらく)そのままにしていたが、また、同じ声がしたので、出て行った。四十前後の坊主が如何にも慇懃(いんぎん)な様子で立っていた。
「ちょっとお邪魔致してもお差支(さしつか)えございませんか」
何か間違いだろうと思ったが、謙作は書院と玄関とのあいだの間(ま)に通した。坊主は具合悪そうに奥の間、玄関の間などを見廻していたが、本の積んである床の間に眼をやると、
「何か御研究でもなさっておいでですか」といった。
「いいえ」謙作は坊主の何となく俗な感じがいやだった。間違いでないとすれば、どうせ《ろく》な用ではないだろうと思い、故意に不愛想に黙っていた。
初対面の人間に対して(いや、初対面じゃなくても)、謙作は、すぐに「好き・嫌い」の感情をむき出しにする。表面には出さなくても、心の中でむき出しにする。ここでも、「謙作は坊主の何となく俗な感じがいやだった。」といきなり感じるのだが、「坊主」は、ただ、挨拶して、入ってきて、本棚の本をみて、質問をしただけである。それなのに、謙作は、そこから「俗な感じ」を受け取る。「坊主」の描写をあまりしないから分からないのだが、あえていえば「如何にも慇懃(いんぎん)な様子で立っていた。」といったところに、「俗な感じ」を受ける理由があるのかもしれない。「慇懃」というのは「人に接する物腰が丁寧で礼儀正しいこと。」であるが、その前に「如何にも」という言葉が挿入されている。つまりは、その丁寧で礼儀正しい物腰が、「わざとらしい」と謙作は受け取るのだ。敏感といえば敏感である。今でいえば、訪問販売員の物腰みたいなものだろう。しかし、ここは「坊主」なのだから、そこまで「俗」(つまりは欲得目当て)であるはずもないのだが、案外謙作のこの直感は当たるのである。
それはまた『暗夜行路』冒頭の、幼い謙作がいきなり現れた「祖父」に感じた「嫌悪」を思い起こさせる。
で、この「坊主」は、謙作を禅の講習会に誘いに来たのだが、その裏には、謙作の使っている広い部屋を講習会のために貸してもらえないかと言いだすのだ。
この辺のことを、引用すると長いので、かいつまんで書いておくと、こんなふうになる。(ここでも「ChatGPT」にお願いして、まとめてもらいました。いやあ、便利だなあ。ちなみに、「ChatGPT」にお願いしたのは、今回が初めてです。「ChatGPT」のご紹介も兼ねてということで。)
ある日、謙作のもとに、万松寺の住職を名乗る坊主が訪れ、金剛院で開かれる十日間の禅の講習会への参加を勧める。講習会は小学校教員の希望で企画されたもので、講義をするのは住職本人ではなく、天竜寺の峨山和尚に師事した修行僧だという。住職自身は禅宗ではないが、主催者として協力しているという立場であった。
謙作は最初は無関心だったが、信行から以前聞いていた「峨山の弟子」ならば一通りの修行を積んだ坊主かもしれないと少し関心を持つ。「臨済録」をテキストにするという話を聞くと、ちょうど兄からその本をもらって持っていることを話し、住職を驚かせる。
住職は謙作が禅に詳しいのではと期待するが、謙作は「全然知りません」と答える。それでも住職は、「それも因縁」として、難しく考えずぜひ参加してほしいと熱心に勧誘を続ける。公案の話題にも触れるが、謙作は「考えてから返事します」とやや曖昧に返す。
しかし謙作の内心には、今目の前にいるこの住職と十日間も関わることになるのかと思うと、すでに気が重く、気乗りしない気持ちがあった。住職はなおも言葉を尽くして誘うが、謙作は最後まで返事をしなかった。
これが文庫本で3ページにわたる、ほぼ会話で描かれる事情である。それを「ChatGPT」は、会話文をつかわず、話し合われた内容をじつに見事にまとめている。しかも、このまとめには、ぼくは一切手を加えていない。いやあまったく何という世の中になったんだろう。
さて、「あとでお返事します。」という謙作に住職は「そう仰有(おっしゃ)らんでぜひ……」と食い下がる。その後を引用しておこう。
謙作は返事をしなかった。坊主はちょっと具合悪そうにしていたが、急に改った調子で、
「実は、そこで一つお願い致したい事があるのでありますが……」といいだした。
話の要領は、下の金剛院には離れがなく、師家と講習生とが襖(ふすま)一重で隣合っているため、一人一人に授ける公案が他(た)に漏れてしまう。それが困るので、もし謙作が講習生の一人になり、他の人々と合宿してくれれば、この離れを師家のために使う事が出来る。もしそうしてもらえれば非常に好都合なのだ、幸い禅に理解があり、公案がどういうものかを御存知なので、お願いするにもし易く、大変幸であった。────こういう話だった。
謙作はすっかり腹を立ててしまった。坊主の話にいくらか釣られた形だったのでなお腹を立てた。
「最初から、それをいうなら、考えようもありますが、おだてるような事を貴方はいわれた。それでは貴方に乗せられる事になる」謙作は腹立(はらだち)から、こういう言葉を繰返した。
「それは誤解です。私は最初からそんな目的で伺ったのではないのです。一人でも多く、求道の方を得たいと思いまして、それで、お勧めに伺ったのですが、伺うて初めて、この離れが師家に大変好都合な御部屋だと考えたので、甚だ不躾(ぶしつけ)とは思いましたが、ついお願いして見たまでで、最初から此所(ここ)を空渡(あけわた)して頂きたい────そんな考で伺ったのではないのです。この点をよく御諒解戴かんことには私が如何にもずるい人間かなぞのよ
うで……」
「それは嘘だ!」とうとう、謙作は怒鳴った。
「どうしてですか」坊主もちょっと調子を変え、青い顔をした。
「そんな見えすいた嘘をいっても駄目だ」
二人は黙って暫く睨合(にらみあ)っていた。そのうち、坊主は不意に衣の袖をばっと両方へ拡げると、おかしいほど平蜘蛛になって、
「御海容を願います」といった。その急な変り方に謙作はちょっと呆気にとられた。
結局、静かな部屋を他に探してくれれば此処を空渡してもいい、必ずしもこの寺でなければならぬという事はないのだから、と謙作もいい、坊主ももしそうしてもらえればありがたい事だ、といって帰って行った。謙作は下らぬ事で、折角(せっかく)の静かな気分を打壊した事を馬鹿馬鹿しく思った。しかしそれに余り拘泥しない事にした。
でました! 謙作の癇癪、ってとこだね。怒鳴ってしまってから、「下らぬ事で、折角の静かな気分を打壊した事を馬鹿馬鹿しく思った。」なんて反省しているけど、「しかしそれに余り拘泥しない事にした。」と開き直っている。謙作の自然と同化したかのような境地は、実に馬鹿馬鹿しいこんなレベルのことで、簡単に壊れてしまい、なんのことはない、いつもの癇癪持ちの謙作に戻ってしまう。こんなことなら、今後の直子との生活だって、どうなることやらと思いやられる。
しかし、「それに余り拘泥しない事にした」というのは、開き直りではなくて、そういう癇癪を起こすことはあっても、すぐに「静かな気持ち」に戻ることができるだろうという自信の表れなのかもしれない。これからの直子との生活で、謙作がまったく癇癪を起こさずにいられるということは、現実的ではない。なんども、癇癪を起こしながら、何度もそれをやりすごしながら生きて行く、それしか謙作にはできないだろう。そのことを、謙作自身が深く納得しているのかもしれない。
それにしても、この二人のやりとりは妙にリアルで、おもしろい。大の大人が睨み合って、そのあと、「坊主」が「平蜘蛛」になってしまう。それを「おかしいほど」と書く。謙作は呆気にとられて思わず心の中で笑ってしまったのだろう。それで急に話がまとまってしまう。こういった事の成り行きは、謙作には珍しい体験だったのかもしれない。都会の知識人では、あり得ないような「坊主」の行動だろう。話をどこまで詰めていっても、煮詰まるだけで、解決の糸口がみつからないような状況で、とつぜん「平蜘蛛になる」という行為は、案外効果的なのだ。
ちなみに、「平蜘蛛」というのは、「ヒラグモ」という薄べったい蜘蛛の一種らしいが、かなり古くから「平身低頭する。はいつくばるさま。」(日本国語大辞典)で、江戸時代の浄瑠璃にすでに用例がみえ、また森鷗外も「平蜘蛛になってあやまる」という用例が「ヰタ・セクスアリス」にある。今では、まず使わない言い方だが、当時はかなり一般的だったのだろう。
そんなこんなで、「十六」は終わる。残るは、あと四章である。