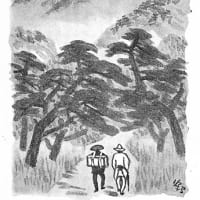日本近代文学の森へ (110) 徳田秋声『新所帯』 30 暖かい日差し

2019.5.21
まったく人間というものは、やっかいなものである。新吉、お作、お国の三人の奇妙な同居だが、三人の間の感情のもつれが、単純なようでいて、実に複雑で、どこをどうすればスッキリするのか皆目分からない。どこをどうしても、結局のところスッキリしないというのが人生なのだろうか。というか、もともと「スッキリした人生」というものが幻想にすぎず、ぼくらの人生は、こんなおかしな形をとらなくても、どこかスッキリしないものを抱えて行かねばならぬ運命にあるのではなかろうか。
小野の刑期が、二年と決まった通知が来てから、お国の様子が、一層不穏になった。時とすると、小野のために、こんなにひどい目に逢わされたのがくやしいと言って、小野を呪うて見たり、こうなれば、私は腕一つでやり通すと言って、鼻息を荒くすることもあった。
お国にのさばられるのが、新吉にとっては、もう不愉快でたまらくなって来た。どうかすると、お国の心持がよく解ったような気がして、シミジミ同情を表することもあったが、後からはじきに、お国のわがままが癪に触って、憎い女のように思われた。お作が愚痴を零し出すと、新吉はいつでも鼻で遇(あしら)って、相手にならなかったが、自分の胸には、お作以上の不平も鬱積していた。
三人は、毎日不快(まず)い顔を突き合わして暮した。お作は、お国さえ除(の)けば、それで事は済むように思った。が、新吉はそうも思わなかった。
「どうするですね、やっぱり当分田舎へでも帰ったらどうかね。」と新吉はある日の午後お国に切り出した。
お国はその時、少し風邪の心地で、蟀谷(こめかみ)のところに即効紙など貼って、取り散(みだ)した風をしていた。
「それでなけア、東京でどこか奉公にでも入るか……。」と新吉はいつにない冷やかな態度で、「私(あっし)のところにいるのは、いつまでいても、それは一向かまわないようなもんだがね。小野さんなんぞと違って、宅は商売屋だもんだで、何だかわけの解らない女がいるなんぞと思われても、あまり体裁がよくねえしね……。」
新吉はいつからか、言おうと思っていることをさらけ出そうとした。
ずっと離れて、薄暗いところで、針仕事をしていたお作は、折々目を挙げて、二人の顔を見た。
お国は嶮相(けんそう)な蒼い顔をして、火鉢の側に坐っていたが、しばらくすると、「え、それは私だって考えているんです。」
新吉は、まだ一つ二つ自分の方の都合をならべた。お国はじっと考え込んでいたが、大分経ってから、莨を喫し出すと一緒に、
「御心配入りません。私のことはどっちへ転んだって、体一つですから……。」と淋しく笑った。
「そうなんだ。……女てものは重宝なもんだからね。その代りどこへ行くということが決まれば、私もそれは出来るだけのことはするつもりだから。」
お国は黙って、釵(かんざし)で、自棄(やけ)に頭を掻いていた。晩方飯が済むと、お国は急に押入れを開けて、行李の中を掻き廻していたが、帯を締め直して、羽織を着替えると、二人に、更まった挨拶をして、出て行こうとした。
その様子が、ひどく落ち着き払っていたので、新吉も多少不安を感じ出した。
「どこへ行くね。」と訊いて見たが、お国は、「え、ちょいと。」と言ったきり、ふいと出て行った。
新吉もお作も、後で口も利かなかった。
新吉とお国は、体の関係を持ったからといって、親密な仲になったわけでもない。体のことはただなりゆきでそうなっただけのことで、それが二人の関係を決定的なものにするわけでもなかった。
新吉は、もともとお国に惚れたわけではなかった。そればかりか、嫌悪も感じていたのだ。という言い方もおかしなもので、惚れた相手に嫌悪を感じることだって多々あること。好きになったり嫌いになったり、それが男女の関係というものだろう。
ただ、お国に対する新吉の感情は、基本は嫌悪のようだ。容姿や肉体に惹かれるものの、お国の図々しさ、我が儘にはうんざりしてもいたのだ。それがここへ来て吹き出す。
自分は商売人だから、家に変な女がいるって思われるのも体裁が悪い、というのが新吉の「言おうと思っていたこと」だという。新吉にとっては、商売が何よりの優先事項で、それには体裁が大事だというわけだ。しかし、「わけの解らない女がいる」なんてことは、とっくに町内の噂になっているだろう。ほんとに体裁が大事なら、とっくに追い出していなければおかしい。
結局のところ、新吉はあくまで自分の家の君主でいたいだけで、その領地を荒らされるのが嫌なのだ。自分の言うことをハイハイと聞いて、テキパキと働いて家業を助ける女を求めているのだ。それにはお作はダメ、またお国もダメなのだ。
お作は、お国にさえいなくなれば平穏な生活が戻ってくると思うのだが、それもまた幻想だった。新吉は、お国を憎みながらも、また惹かれていたからだ。
それにしても、この辺のお国の描き方は実に水際立っている。コメカミに「即効紙(薬を塗った一種の紙。頭痛などの時、患部に貼って使うもの。)〈日本国語大辞典〉」を貼ったお国がツンツンしてタバコをすっているところなどは、やっぱり杉村春子にやらせたい。
いざとなれば、どっちへ転んだって体一つだという潔さは女ならではのものだろうが、それを新吉は「女てものは重宝なもんだからね。」と揶揄する。お国は答えない。そして「ひどく落ち着き払った」態度で家を出ていく。そうなると新吉は不安になってくる。川に身でも投げるのではと思ったのだろうか。お国はそんなヤワな女じゃないだろうけど、男ってものは、そういう女のことが結局分からない。
高ッ調子のお国がいなくなると、宅は水の退いたようにケソリとして来た。お作は場所塞(ばしょふさ)げの厄介物を攘(はら)った気でいたが、新吉は何となく寂しそうな顔をしていた。お作に対する物の言いぶりにも、妙に角が立って来た。お国の行き先について、多少の不安もあったので、帰って来るのを、心待ちに待ちもした。
が、翌日も、お国は帰らなかった。新吉は帳場にばかり坐り込んで、往来に差す人の影に、鋭い目を配っていた。たまに奥へ入って来ても、不愉快そうに顔を顰めて、ろくろく坐りもしなかった。
お作も急に張合いがなくなって来た。新吉の顔を見るのも切ないようで、出来るだけ側に寄らぬようにした。昼飯の時も、黙って給仕をして、黙って不味(まず)ッぽらしく箸を取った。新吉がふいと起ってしまうと、何ということなし、ただ涙が出て来た。二時ごろに、お作はちょくちょく着に着替えて、出にくそうに店へ出て来た。
「あの、ちょっと小石川へ行って来てもようございますか。」とおずおず言うと、新吉はジロリとその姿を見た。
「何か用かね。」
お作ははっきり返辞も出来なかった。
お国がいなくなると、新吉はいっそう機嫌が悪くなる。お国の帰りを待ってばかりいる。そんな新吉を見るのも辛い。そしてまた、お作自身、「急に張合いがなくなって来た」というのだから人間って複雑だ。
お国の存在は、お作にとっては悩みの種だったことは確かだが、それが日常になってしまうと、お国の存在は自分のアイデンティティにとって欠かせないものとなった、と言っては大げさだが、お国と自分なりに対抗することで、自分の心を確かめてきたという面があるのではなかろうか。
お作はお国に面と向かって対抗してきたわけではないが、それでも、何かの折には、新吉が、お国よりやっぱりオマエだ、って言ってくれる日が来ることを楽しみにして辛い日常を耐えてきたのではなかろうか。
その「張り合い」がなくなったとき、お作はどうするか。「過去」へ戻っていくのである。
出にくそうに家を出るお作を「ジロリと見る」新吉の冷たさにお作ならずとも身も凍る思いがする。
出ては見たが、何となく足が重かった。叔父に厭なことを聞かすのも、気が進まない。叔父にいろいろ訊かれるのも、厭であった。叔父のところへ行けないとすると、さしあたりどこへ行くという的(あて)もない。お作はただフラフラと歩いた。
表町を離れると、そこは激しい往来であった。外は大分春らしい陽気になって、日の光も目眩(まぶ)しいくらいであった。お作の目には、坂を降りて行く、幾組かの女学生の姿が、いかにも快活そうに見えた。何を考えるともなく、歩(あし)が自然(ひとりで)に反対の方向に嚮(む)いていたことに気がつくと、急に四辻の角に立ち停って四下(あたり)を見廻した。
何だか、もと奉公していた家がなつかしいような気がした。始終拭き掃除をしていた部屋部屋のちんまりした様子や、手がけた台所の模様が、目に浮んだ。どこかに中国訛りのある、優しい夫人の声や目が憶い出された。出る時、赤子であった男の子も、もう大きくなったろうと思うと、その成人ぶりも見たくなった。
お作は柳町まで来て、最中(もなか)の折を一つ買った。そうしてそれを風呂敷に包んで一端(いっぱし)何か酬(むく)いられたような心持で、元気よく行(ある)き出した。
西片町界隈は、古いお馴染みの町である。この区域の空気は一体に明るいような気がする。お作はかなめの垣根際を行(ある)いている幼稚園の生徒の姿にも、一種のなつかしさを覚えた。ここの桜の散るころの、やるせないような思いも、胸に湧いて来た。
家は松木といって、通りを少し左へ入ったところである。門からじきに格子戸で、庭には低い立ち木の頂が、スクスクと新しい塀越しに見られる。お作は以前愛された旧主の門まで来て、ちょっと躊躇した。
もと奉公していた家ではお作はずいぶん可愛がられた。かつて愛情を注いでくれた家の人々。それが、お作の心の支えなのだ。冷酷な感情の支配する場面が続いたあと、このシーンを読むと、とても気持ちが和らぐ。風景も明るく、風も暖かい。