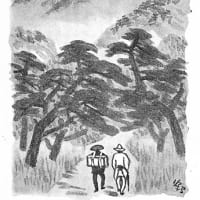日本近代文学の森へ (116) 志賀直哉『暗夜行路』 4 どっちだろう 「前篇第一 一 」その1
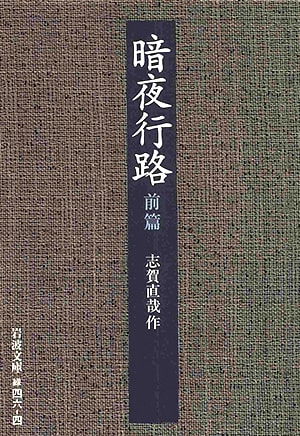
2019.6.23
時任謙作の阪口に対する段々に積もって行った不快も阪口の今度の小説でとうとう結論に達したと思うと、彼は腹立たしい中にも清々しい気持になった。そして彼はその読み終った雑誌を枕元へ置くのも穢らわしいような心持で、夜着の裾の方へ抛って、電気を消した。三時近かった。
彼はやはり興奮していた。頭も身体も芯は疲れていながらなかなか眠る事が出来なかった。彼は頭を転換さすために何か気楽な読物を見ながら睡むくなるのを待とうと考えた。が、そういう本は大概お栄の部屋へ持って行ってあった。ちょっと拘泥したが、拘泥するだけ変だとも思い返して、再び電気をつけて二階を降りて行った。
「序章」の後に始まる『暗夜行路』前篇の冒頭部だ。
最初の一文からしてずいぶんと特徴的な文章だ。なんの前触れもなく、いきなり主人公時任謙作の不快感が出現する。いったい何が不快なのかというと、坂口が不快だというのだ。それも「段々に積もって」きた不快だ。それが「今度の小説」で「結論に達した」というのだ。
そんなことを言われても、何のことか分からない。それはおいおい話すということなのだ。こういう書き方というのは、小説においては常套手段なのだろうが、この時代は、どうだったのだろうか。案外新しいのかもしれないし、そうでもないのかもしれない。
阪口に対する不満が高じてきて、それが「結論に達し」たと思うと、「腹立たしい中にも清々しい気持になった」というのは、いったいどういうことだろう。
それまで何だか阪口には不快感を感じていたのだが、いったいどこが不快なのかがいまいち言葉にできなかった。それが、この小説を読んで、ああ、オレはコイツのこういう点が気にくわなかったのだとハッキリした。そのハッキリしたということで、気分は「清々しい」ものとなった、ということだろうか。
確かに、何となく気にくわないという気分は、つかみようがなくて、それだけに対処のしようがない。「ここが」気にくわないのだとハッキリすれば、自分の気持ちも整理できて、ひょっとしたら対処法も見つかるかもしれないと期待もできる。そういうことだろう。
眠れなくなったとき、「気楽な読み物」を読むと眠くなるものかどうかぼくは知らないが(ぼくはきわめて寝付きがいいので、そういうことをほとんどしたことがないので)、謙作は「塚原卜伝」を読もうと思うのだが、「お栄の部屋」にそういう本は持って行ってある、という。ここでまたいきなり「お栄」の登場だ。しかも、同じ家に住んでいる。「お栄」は「序章」で、祖父の家にいた女であり、主人公が「好きになった」と書いてあった女だ。いったいどういうことなのだろうと興味がわく。うまいね。
本がお栄の部屋にあるので、とりにいこうと思うのだが、「ちょっと拘泥したが、拘泥するだけ変だとも思い返して」とりにいく。この「拘泥」は、「あることを必要以上に気にしてそれにとらわれること。」〈日本国語大辞典〉の意だが、謙作は何を「必要以上に」気にしたのか、そしてなぜ「必要以上に気にする」のは「変だ」と思ったのか。なんか、現国の試験問題みたいだけど、ちょっと問題にしたいところだ。
夜中の三時に、どういう関係かしらないが、女のいる部屋に行くことは十分に「気にする」に値することで、それはそんなことをしたら、その女が「誤解」する恐れがあるということだろう。けれども、自分にはそんなやましい気持ちはないのだから、「必要以上に気にする」ことはかえっておかしなことだ。むしろ気にすれば気にするだけ、「その気」があることを証明する結果になってしまう。まあ、そう考えれば分かりやすい。
「ちょっと本を貰いに来ました」と声をかけて、「塚原卜伝は戸棚ですか」といった。
お栄は枕元の電燈をつけた。
「床の間か、茶箪笥の上ですよ。まだ起きてたの?」
「眠むれなくなったんで、見ながら眠むるんです」
謙作は茶箪笥の上から小さい講談本を持って、「明日」といってその部屋を出た。
「御機嫌よう」こういって、お栄は謙作が襖を締めるのを待って電燈を消した。
ちょっと声をかけただけで、パッと電灯がついて、返事をする。ねぼけてない。
「ちょっと本を貰いに来ました」「塚原卜伝は戸棚ですか」という謙作の敬語。それに対して、「まだ起きてたの?」というお栄のくだけた言葉遣い。
これだけで、何となく二人の関係性が透けて見えるような気がする。もっともそれは、すでに「序章」でお栄の方が謙作よりも年上らしいと分かっているからでもあるが。それにしても「まだ起きてたの?」に、ちょっとドキドキするのは、「気にしすぎ」だろうか。
「御機嫌よう」というお栄の言葉は、今では上品すぎる印象だが、当時はどうだったのか。「謙作が襖を締めるのを待って電燈を消した。」お栄の心遣い。謙作が襖を締める前に電灯を消せば、いかにも「用が済んだんだからもういいわ」といった素っ気なさが、謙作に伝わってしまう。謙作が襖を締めたことを見極めたうえで、電灯を消すことで謙作に不快感を感じさせずに済む、ということだろうが、この場面の「視点」はどうなっているのだろうか。つまり、誰の視点で書いているかということだ。第三者の視点なら、別にいいのだが、このあたりは謙作の視点で多く書かれている。もし、この部分も謙作の視点なら、謙作はいつお栄が電灯を消すのかに注意を払っていたことになる。としたら、お栄は、そういう謙作の細かい神経をよく知っていて、そのように行動したのだということになるわけだ。どっちだろう。
さて、謙作は、せっかく気楽な読み物を手に入れたのに、結局は眠れなかった。
謙作はその気楽な講談本を読みながら、朝露のような湿り気を持った雀の快活な啼声を戸外に聴いた。
見事な一文である。「朝露のような湿り気を持った雀の快活な啼声」という表現に魅了される。
それと同時に、いったい眠れなかったのは、「塚原卜伝」が面白かったからなのか、阪口のことがまだ頭から離れなかったからなのか、それともお栄のことを考えていたからなのか、どっちだろうとまた思わされる。