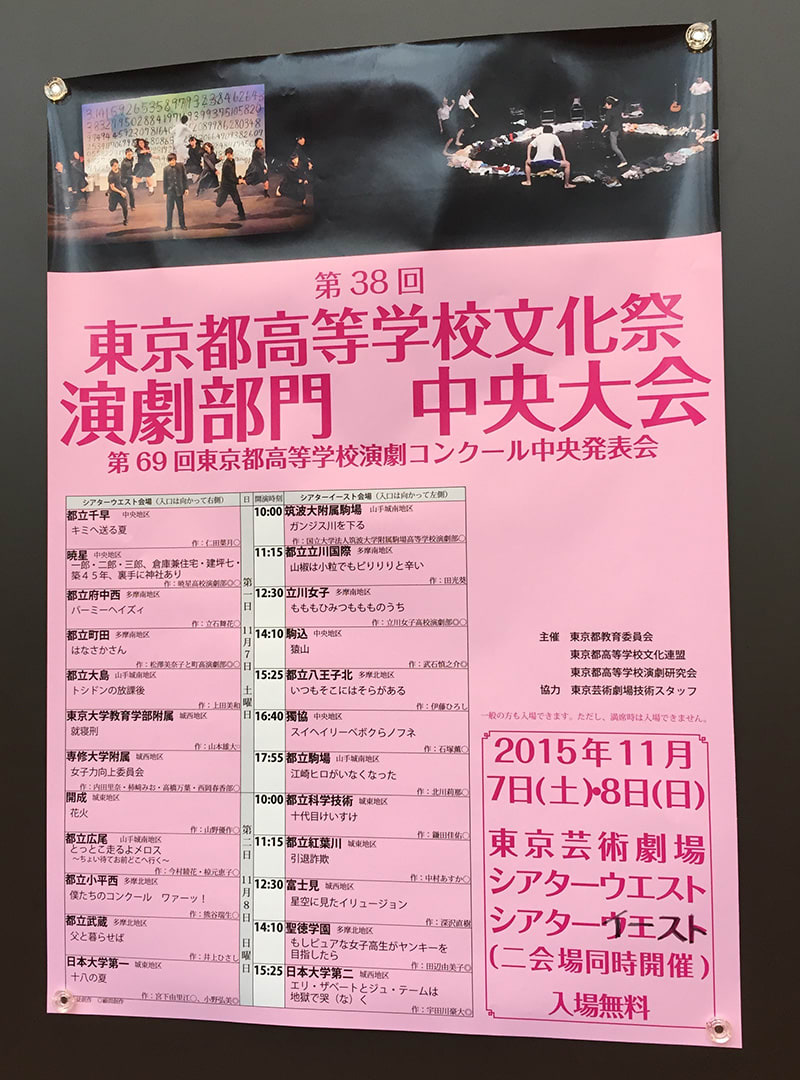65 わが「師」の「恩」

2015.12.9
教師というのは、つくづくフシギな職業だと思う。
「先生と呼ばれるほどの馬鹿でなし」という言葉をいつ覚えたのか知らないが、教師をしている間、そしてやめてからも、この言葉が頭のどこかで響いている。ちなみに、『大辞林』によればこの言葉の意味するところは、「〔先生という敬称が必ずしも敬意を伴うものではないことから〕先生と言われて気分をよくするほど、馬鹿ではない。また、そう呼ばれていい気になっている者をあざけって言う言葉。」とあるわけだが、しかし、いい気になるかどうかは別として、教師を呼ぶのに「先生」以外の言い方が日本語にはないのだからしょうがない。
「恩師」という言葉もまたそうである。卒業生がかつての先生をなんと表現すればいいのか考えてみると、どうしても「恩師」しかないことが分かる。「この方は、私の『先生』です。」と言うと、今習い事などを教えてもらっている人かと思われてしまいかねない。「恩師」と言えば、そういう誤解はなくて、ああ、かつて、どこかの学校で教師をしていたんだなと分かってもらえるというわけだ。だから、「恩師」という便利な言葉を使うのだが、だからといってその言葉を使う人間が、対象たる教師に「恩」を感じているかどうかはまた別の問題なのである。
かつての教え子に「恩師」と言われると、どうにも居心地が悪いのは、どう考えても、ぼくは「恩」を感じてもらえるような教師ではなかったからだ。でも教え子の中には、あなたは「恩師」以外のなにものでもないのだ、と断言する人もいるわけで、そうなると、もうぼく自身がどう思うかにかかわりなく、教え子の方で「恩」としかいいようのないものを感じているのだろうと最近では納得することにしている。
卒業式が近づいてくると、都立高校時代は、毎年のように、「仰げば尊し」を歌わせて欲しいという要望が生徒から出たものだ。そのころのぼくはいわゆる「アラサー」だったので、超生意気盛りで、かつ超ヒネクレ者だったから、「冗談じゃない。『尊し』なんてこれっぽっちも思ってないくせに、そんな歌は聞きたくないぜ。あのセンチメンタルなメロディに酔って泣きたいだけなんじゃないの!」って言って突っぱねたものだ。今から思うと、ひねくれすぎである。センチメンタルになって泣きたいだけだって、それはそれでいいじゃないか。思う存分泣かせてあげればよかったのだ、と今なら思う。たぶんぼくは、そんな彼らの「青春」のありかたに嫉妬していたのだと思う。
ところで、「恩」とは、「目上の人から受ける感謝すべき行為。」(日本国語大辞典)の意だが、ここにも如実に表れているように、どこか「上」の者から施された行為であり、それに対して「感謝すべき」だと規定されているニュアンスがある。つまり、おれはお前にこれだけの「感謝すべき」ことをしてやったんだから、そのことを忘れるな、っていう「上から目線」の感じを持つ言葉なのだ。それがぼくが「恩師」と教え子から言われたときに、どうしても居心地が悪い思いをする原因のようだ。
ぼくは、今でも、教え子たちに謝りたいことだらけで、「感謝しろ」なんていえることなんてほとんどない。(ちょっとだけある。)太宰治は『人間失格』で、その主人公たる大庭葉蔵(ヨウゾウ、である)に「恥の多い生涯を送ってきました。」と言わせ、寅さんは、「思い返せば恥ずかしきことの数々」といつも言っていた。それこそ、ぼくのためにあるような言葉である。
「恩」だとか「師」だとか「先生」だとかいう言葉が、どうしても人間の「上下関係」に根付いてしまうのは、たぶん、封建的な時代の名残なのだろうが、封建主義的道徳の根源のように言われる儒教も、「論語」をきちんと読めばそれほど上下関係を重視していないところもある。
孔子は、「三人行えば、必ず我が師あり。」と言っている。つまり、「上下関係」なんてどうでもいいんで、どこにでも「師=学ぶべき人」はいるよ、といっているのだ。何かを学ばせてもらったこと、それこそが本当の意味での「恩」だ。とすれば、「恩」というのは、それを感じる人の感性の問題だということになる。空にうかぶ雲を見て、なにかを「学んだ」とすれば、ぼくらは雲に「恩」があるということになるわけだ。雲はなにかを「教えよう」とはしていない。それでも、そこから「学ぶ」人はいる。
大自然が「師」となることもあり、生徒が先生の「師」となることもある。いや、あるどころではない。かつての教え子に、今、ぼくはどれほどの「恩」を感じていることだろう。
孔子はこうも言っている。「六十にして耳順う」と。六十歳になって、やっと人の言うことを素直に聴けるようになったというのだ。ということは、六十歳になるまで、孔子でさえ、他者から学ぶことは容易ではなかったということになる。人一倍生意気で、ヒネクレ者だったぼくもこの「耳順」を遙かに越えてしまったが、ようやく「耳順」の境地に到達できたような気がする。
あとは七十歳の、「心の欲するところに従いて矩(のり)を喩(こ)えず。」という境地が待っているらしい。やりたい放題やっても、人の道をはずれることはない、というわけだが、さて……。