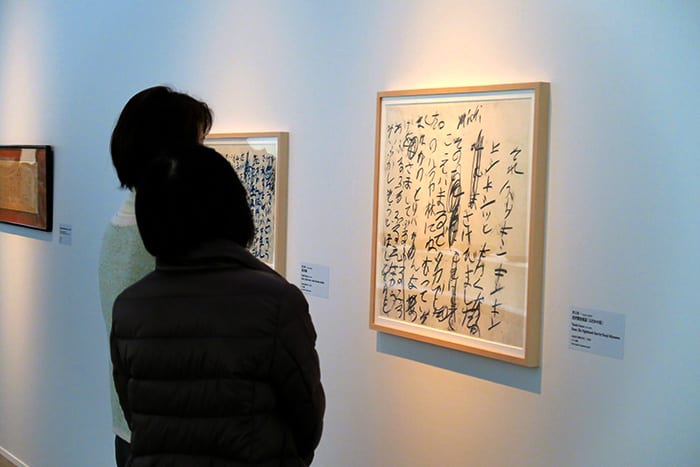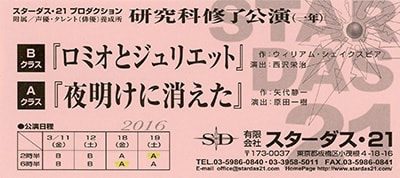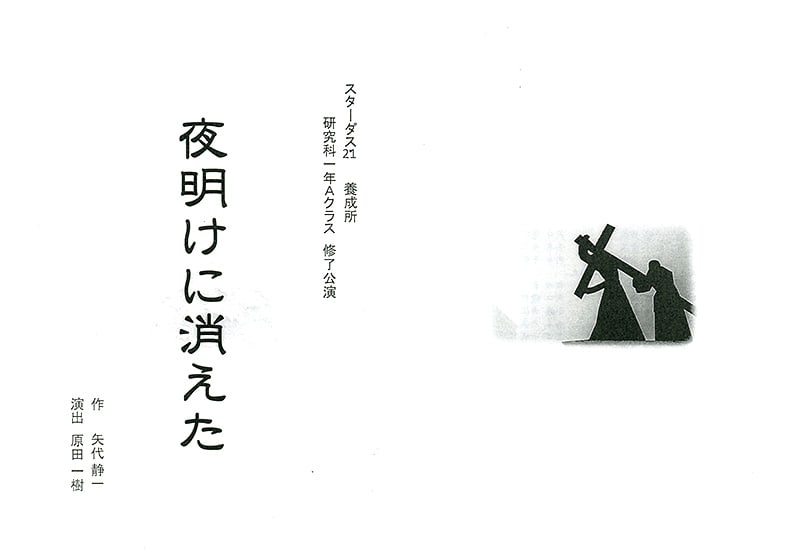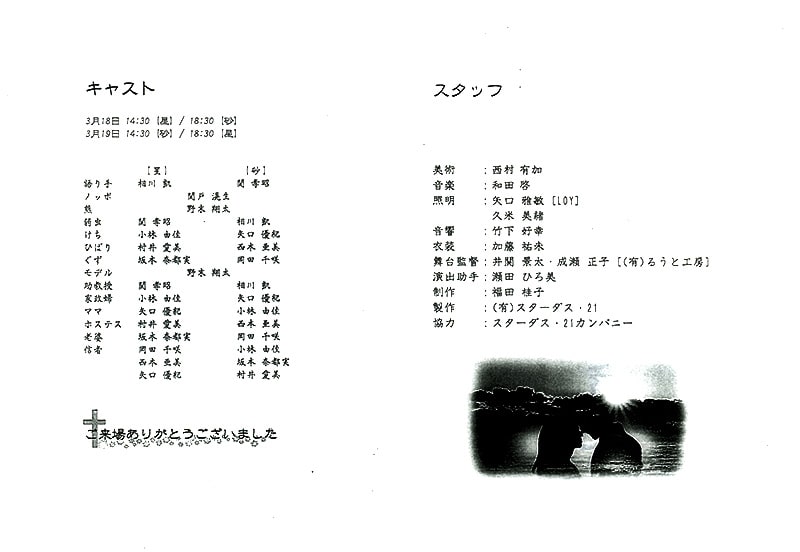80 幸福な時間

2016.4.7
鶴見川へ、桜の写真を撮りに出かけた。詳しくいうと、青葉区の市が尾を流れる鶴見川へ、センダイヤザクラというヤマザクラの写真を撮りに出かけたのである。ちょうどソメイヨシノが満開で、天気もよくて、これが「お花見」のラストチャンスという昨日、「お花見」で有名な大岡川へは行かないで、なんでそんなところへ行ったのかというと、たまたま1週間ほど前、フェイスブックで「センダイヤザクラ」という耳慣れないサクラのことを知ったからだ。
耳慣れないサクラといえば、それより更に1週間ほど前に、ヨコハマヒザクラというサクラのことをこれもやはりフェイスブックで知り、それが、みなとみらい地区で満開であるということも知って、そのサクラを求めて車を駆って写真を撮りにいったのだが、更にその後、そのサクラの原木が、本牧頂上公園というこれまた耳慣れない公園にあると知り、またまた車を駆って出かけて行き、その見事なピンク色のサクラを心ゆくまで撮影することができたのであった。
そこへこのセンダイヤである。息つく暇もありゃしない。満開のソメイヨシノなんて目じゃなくなってしまった。
鶴見川は、下流の方は、電車でそれこそ何百回と渡ってきた川だが、そのちょっと上流の方にはとんと縁がなく、今までまったく行ったことがなかった。青葉区なんていうと、今でこそ横浜では人気の区だが、昔は港北区の一部で、横浜のハズレもいいとこ、ぼくのように横浜の中心部に生まれ育ったものからすると「横浜じゃない」ぐらいの認識で、なんでそんなところに人気があるのかさっぱり分からなかったし、鶴見川の上流っていったって、そもそも下流の鶴見川はキタナイ川という認識しかなくて、行く気にもならなかったのだ。
けれども、高知県の「仙台屋」というお店の前に植えられていたヤマザクラが他のとはちょっと違っていたのか、それに目をつけたかの牧野富太郎博士によって「センダイヤザクラ」と命名されたというそのサクラが、地元もボランティアの方々によって80本あまりが川の土手に植えられているということをネット検索で知ったのだ。普通ならソメイヨシノを植えるところだが、それじゃ芸がないというか、ここはひとつヤマザクラで行こうじゃないかと思ったらしく、その中でもこの由緒の面白い、そしてピンクの濃いセンダイヤに目を付けたということらしい。
とにかく、50分ほど電車に乗って、その鶴見川に辿りついて驚いた。川沿いには、なんとものどかな田園風景が広がり、その土手に植樹からまだ10年ほどしか経っていない小ぶりのセンダイヤが今まさに満開の枝を連ねている。こんなきれいな場所のあるのが青葉区なんだと思ったら、今まで田舎呼ばわりしていたのが申し訳ない気分になってしまった。
お目当てのセンダイヤの写真を撮ったり、土手に咲く野草を撮ったりしていると、その昔、そう、中学生のころに、昆虫採集のために訪れた相模川を思い出した。冬に行ったり春に行ったりしたものだが、特に春は、採集を一休みして、同行した友人と土手でお弁当を食べたり、寝っ転がって雲雀の声を聞いたりしたあのなんともいえない幸福な気分が蘇ってくるような気がした。
あれからもう半世紀経ってしまったが、やっぱり人間というものは、「好き」なことは変わらないものなのだとつくづく思った。あの頃、とにかく生物が好きで、生物の研究を一生の仕事としよう思っていたのに、気がついてみれば、まったく違った方向へ向かい、そこで生きてきたけれど、ぼくがほんとうに幸福を感じるのは、こういう時間なのだった。
ほんとうに、中学3年生の1年間は、ぼくが繰り返し書いてきたことだが、ぼくの人生の中でもっとも幸福な1年間、まさに「黄金の時間」だった。勉強もほっぽり出して(といっても、小心者だからいちおうすることはしたのだが)、山や川や海へ昆虫を求めて出かける日々だった。その1年間というのは、時間の隅から隅までが幸福に満たされ、すべての瞬間が楽しいという、ほんとうに稀な1年間だったのだ。その後、ぼくが別に不幸な人生を歩んできたわけではないが、それでも鬱屈し、悩み、こんな人生のはずじゃなかったと思った時にも、この1年間があったからこそ、何とか乗り越えることができたような気がするのだ。
その「幸福な時間」が、どのように具体的に作用したのかはしらない。けれども、かつてこんな「幸福な時間」があったという記憶は、人間が長くて辛い人生を生きていくための、基本的なエネルギー源となるものなのかもしれない。
まだ始まったばかりの朝ドラの『とと姉ちゃん』を見ていても、はやくに父を亡くしても、その父と過ごした「幸福な時間」が、この子供たちのその後の人生の支えになっていくのだろうということがよく分かる。
ぼくはもう高齢者だから、今更、新たな「幸福な時間」を作れなくてもいい。今回のことでいえば、昨日の「幸福な時間」は、どこかかつての「幸福な時間」のコピーのような気がする。それでいいと思っている。けれども、これからの人は、まだ若い人は、どこかでこういう若い日々の特権的な「幸福な時間」を何としても味わっておいてほしいものだと、おせっかいにも思っているのである。

センダイヤザクラ

ヨコハマヒザクラ