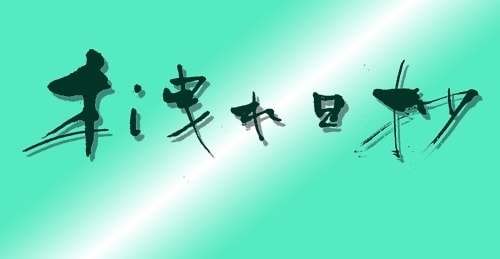木洩れ日抄 85 歌謡曲雑感──森昌子の魅力

2022.1.29
フェイスブックで、「今日の1枚」と称して、毎日、昔撮った写真をアップしているのだが、先日、法善寺横丁の写真をアップした際に、コメントとして、「藤島恒夫」の「月の法善寺横丁」って歌がありました、などと書いたのだが、その原稿を書いているとき、「藤島恒夫」のところを「藤島一郎」って書いてしまった、あれ? そうだっけ? と思って、試しに「藤島一郎」で検索したが、お医者さんは出てくるけど、歌手はおろか、俳優も出てこない。やっぱり違うんだと思ったが、それにしても、「藤島一郎」って俳優がいたはずだけどと思いつつ、あてづっぽうに検索を続けたら、なんと、俳優は「有島一郎」だった。そうだった、そうだった。あんなに有名な俳優なのに、私としたことが、「藤」と「有」の取り違えるとはと思いつつ、そういえば、昔、「有島一郎」と「有島武郎」をよく取り違えていたなあと懐かしくなった。文学史の試験なんかで、よくそういう間違えがあったような気がする。
と、そのとき、なんで「藤島一郎」と最初書いてしまったかが、なんとなく分かった気がした。「有島一郎」「有島武郎」「藤島恒夫」あたりが頭の中でごっちゃになってしまったのだろう。
しかし、「藤島恒夫」って、「ふじしまつねお」だったっけ? とふと疑問に思った。もう記憶が曖昧すぎて、なにがなんだか分からないけれど、「つねお」っていうんじゃなかった気がする。それで、再度検索したら、なんと、「藤島桓夫」だった。「恒」ではなくて「桓」。桓武天皇の「桓」だ。Wikipediaには、丁寧に、「藤島恒夫と表記されることがあるが誤り。」と書いてある。よほど注意しないと、「恒」と「桓」とを区別することは難しいし、そもそも「桓」なんて字は、桓武天皇以外にはほとんど目にしないし、今では、人名漢字表にもない。
そんなこんなで「藤島桓夫」について調べているうちに、フェイスブックでは、「月の法善寺横丁」が大好きだみたいなことを書いたのに対して、教え子が歌は聞いたことがあるけど、歌手までは知りませんでしたとコメントしてきたので、調子に乗って、「お月さん今晩わ」なんてのも有名ですよ、みたいなコメントをしたが、「それはわかりません」ということだった。自分でも、そういえば、どういう歌だったっけ? とYouTubeで聞いてみたら、やっぱり馴染みの歌だった。そのYouTubeで、関連動画として、森昌子の「お月さん今晩わ」があったので、聞いてみた。うまい! 福田こうへいの歌もあり、それはそれでうまいけれど、森昌子は絶品だ。すると、今度は関連動画で、森昌子の「矢切の渡し」があった。へえ〜、森昌子の「矢切の渡し」なんて珍しいなあと思って聞いてみたら、これがまたうまいのなんのって。
「矢切の渡し」という歌は、今まで何度か書いたことがあるけれど、細川たかしの歌ではない。あれはカバーである。「矢切の渡し」は、ちあきなおみの歌なのだ。しかも、発売当時は、シングルのB面で、ヒットしなかったのだが、それが、テレビドラマの名作「淋しいのはお前だけじゃない」の中で、旅役者役の梅沢富美男が舞台で踊るときに流れたのがきっかけで、急に注目されるようになったのだ。
というか、ぼくが、その曲にびっくりしたのだった。その当時の女形としての梅沢富美男の美しさもさることながら、そこに流れるちあきなおみの聞いたこともない歌に、すっかり魅了された。いったいこれは何という曲なのだろうと調べ、シングル版も買った。そういうぼくみたいなのが全国に大勢いて、この曲はよく知られるようになり、やがてA面になったというわけなのだ。
しかし、やがて、細川たかしがカバーすると、これがもう大ヒットとなり、今ではこの曲が細川たかしの曲のように思われる始末である。ちあきなおみが切々と情感を込めて歌った名曲を、細川たかしは、ただただ声を張り上げて、民謡で鍛えた小節と声質を自慢するかのように笑顔で歌う。これでは、ひっそりと駆け落ちする男女の心情がどこかへふっとんでしまう。ちあきなおみの歌には、いつも「櫓の音」が通奏低音として聞こえていて、寒々とした細い川が北風に向かって進んでいくが、細川たかしの歌では、モーターボートをぶっ飛ばして、大きな川を渡っていくようなもので、情緒のかけらもありゃしない。
なんて、悪口を書くと、細川ファンの方に叱られそうなので、この辺にしておくが、とにかく、「矢切の渡し」は、ちあきなみの歌なのだ、ということは再度強調しておきたい。
話がちっとも本題に入らないが、森昌子である。
桜田淳子、山口百恵とともに、「花の中三トリオ」と呼ばれたデビュー当時は、森昌子がもっともぱっとしなかった(あくまで個人の感想です。)顔もちっともかわいくないし(ぼくだけの好みか?)、歌も、「せんせい」なんて、気持ち悪かった。(ぼくが先生なだけに。)山口百恵もなんだか暗くて、顔も地味で、これもぱっとしなかったし、あんまり人気もなかったように思う。つまり、そのころは、圧倒的に桜田淳子だったのだ(と思う。)なにしろ、いちばんカワイイのは彼女だったし、音程は実に不安定で、歌もうまくなかったが、「私の青い鳥」はいい歌だった。しかし、その桜田淳子にしても、いきなりファンが押し寄せたわけではない。彼女がデビューしたのは、1973年で、ぼくはすでに就職して2年目だったわけだが、その頃、伊勢佐木町のレコード店の店先で、サイン会をやっていたことがある。しかし、そこには誰も並んでいなかった。ぼくも、お! っと思ったけれど、結局サインをもらいにはいかなかった。そんなものだったのだ。
ちなみに、ちあきなおみも、売れる前は大変で、いつだったか、銀座のデパートの婦人服売り場の片隅に小さなステージを作って、そこで歌っているのを見かけたことがある。そのときは、誰? この人? ってな感じで、立ち止まりさえしなかったことが、あとあとまで悔やまれることとなった。(桜田淳子にサインもらわなかったことも。)
山口百恵が、爆発的に売れ出したのは、ぼくの記憶では、東大生が騒ぎ出して以来のように思う。今でこそ、東大生がアイドルを追っかけたって別に不思議でもなんでもないが、やはり当時は「あの東大生が?」というところがあって、漫画や劇画だって、東大生とはいわず「大学生が読んでる」ということが、格を上げたように思うのだ。平岡正明の「山口百恵は菩薩である」なんていう本が飛ぶようにうれたらしく、あっという間に、山口百恵は「別格」となっていった。
そういう中で森昌子は、相変わらずの野暮ったさで、「東大生が森昌子を聞いてる」なんて話は聞いたこともない。(もちろん、聞いていた人も多かっただろうけど。)
ぼくはといえば、へんてこな東大コンプレックスがあったから、そんな山口百恵には違和感があって、積極的には聞かなかったけれど、テレビをつければ出てきたので、だいたいは聞いてきたのだが、桜田淳子に至っては、途中で新興宗教に走ってしまうし、森昌子のほうは、「歌がうまい」なんてことにも気づかずに、まだ歌ってるのか、程度の認識だった。それでも「悲しみ本線日本海」あたりで、ぐっときたものの、「越冬ツバメ」で、そんなツバメがいるか! って腹をたてて(実際には、「越冬せざるを得ないツバメ」はいるらしいから、ぼくの腹立ちは間違いだったのだが)、それ以来あまり聞かなくなってしまっていたのである。
それが、それが、である。彼女がこんなにも、多くの曲をカバーしているのかと、今回、愕然とした。YouTubeの「矢切の渡し」などは、再生回数が55万回である。知ってる人は知っていたんだなあと、つくづく不明を恥じたことである。
女性歌手(演歌系)で、歌がうまいと思ってきたのは、第一に美空ひばりで、第二位がちあきなおみだが、この二人の特徴は、声の多彩さだ。とくに、美空ひばりは、まるで万華鏡のように声が変化し、その声を自在に操る、なんてことを今更書いてもしかたのない常識だろう。ちあきなおみも、美空ひばりほどの声の変化はないにしても、その低音域の声に恐ろしいほどの奥行きがある。それが歌に限りない陰影を与える。
それに比べて、ぼくが第三位として推したいと今更ながら思いはじめた森昌子の声は、一筋の線である。絹のようにはりつめた、つやのある、一筋の線である。その一筋の線で、すべてを歌いきる。すべての感情を歌いきる。これは考えてみればすごいことではないか。
それに加えて、森昌子には、嫌みがない。あっさりとしていて、うまい。酒でいえば、純米吟醸酒のようなものである。そこへいくと、美空ひばりは、嫌み満載だ。(ついでに言えば、細川たかしは「嫌みのてんこ盛り」だ。)ぼくは、彼女が存命中は、大嫌いだった。今おもえば、うますぎたのだろう。そのうまさを隠さなかったのだろう。それが「嫌み」に聞こえたのだろう。ちあきなおみには、そうした嫌みはないにしても、ちょっと感情を掘り下げすぎるところがあって、それが時として鼻につくときもある。これもまたうますぎる故だろう。
そうしたことが、森昌子にはいっさいない。これもまたすごいことではないか。こうした嫌みのなさ、あっさり加減でいえば、島倉千代子がいた。彼女は、一種の「へたうま」で、ちょっと聞くとすごくへたなのに、よく聞くとすごくうまい、としかいいようがない不思議な歌手だ。
美空ひばりがオーケストラだとすれば、ちあきなおみは弦楽四重奏。そして、その伝でいけば、森昌子は、バイオリンのソロとなるだろうか。いや、バイオリンよりももっと音色の変化の少ない楽器、そうだなあ、三味線とか、三線とか、そんなことになるのだろうか。そんなことを、無責任に、勝手に、つらつら考えるのもまた楽しいものである。