6日
三時から鈴木研のゼミ。明日の歴史系全体ゼミにすずきせんせいが来られないので、僕を含む鈴木研のM2二人が修論のテーマ発表をする。普段からずっと考えていることだったので、つくったレジュメを読み上げなくてもしゃべれた。先生からはおおむね賛同を得られたけれど、「そういうテーマで行くなら当然定量的な構造解析までやってくださいね」と笑顔で。それは僕にとっても最も苦手な分野なのだけど、頑張らねば。資料収集の方法としては、19世紀当時の製品カタログを読んでみたらどうかとアドバイスをいただく。もう一人のM2のとうさんも研究対象はイギリス。海外研究につきものの資料収集の難を指摘されていて身につまされた。
夕方髪を切りに行って、夜は歩道橋コンペのスタディ。1/50で模型をつくり始めてみる。敷地の正確な図面がまだ手に入っていないのだが、扱う範囲はおよそ野球場一つ分くらいの規模。模型製作のためには膨大なスペースが必要なことがわかる。この季節、院試対策のために四年生が三階の演習室を占有する。困った。
7日
40人分の資料を印刷して歴史系のゼミに臨む。昨日お墨付きをもらっているテーマなので自信を持ってしゃべれた。つくったレジュメを読まずに大声でしゃべる僕に先生方はニヤニヤ。いろいろ前向きなアドバイスをいただく。東大の図書館には古い時代のRIBAの会報誌がストックされているらしく、それを当たれば19世紀の詳細な図面も手に入るのではないか、など。こうした領域横断的なテーマはやはり歴史系においては過去に例がないらしい。構造系の先生も喜ばれるでしょう、と好感触。ただし最後に、技術の話だけにとどまらず形而上学的な領域まで到達してねと釘を刺された。今まで歴史系が避けてきたテーマだから頑張ってほしい、と博士の先輩からも声をかけてもらう。うれしい。
四時からArchiTVのミーティング。三田の商店街を舞台に、二時間ほど案出しのブレスト。次回は町内会へのプレゼン用に模型とパネルをつくってみることに。
六時からこばやしさんと歩道橋コンペのスタディ。何気ない一言から前回とは少し違う意外な方向に転がりだす。こういうことがあるから三人でやるのは楽しいね。
終了後、畳プロジェクトのブレスト。インテリア系の雑誌を見たり家具見本市やデザイナーのWEBページを閲覧しながら、二時間ちょっと。また一つ案ができる。
休憩中に後輩から「最近、建築以外のことしてますか?」と。彼は最近、拘束のドローイングで知られるマシュー・バーニーの映画を観てきたらしい。彼は「建築における、無用なもの」を修士での研究テーマとしている。建築そのものとは直接関係なく、宗教や遊興等のルールや作法によって生まれ、建築の中に「残ってしまった」もの。日本の伝統家屋の中にはそんなものがたくさん存在しているという。
先週僕が送った「不合格でした」というメールに対して、返事に困っていたという父からパソコンにメールが来ていた。自分にとって何が今一番大切なやるべきことか、いつか優先順位が建築士試験になったときには頑張ってくれ、と。父は、期待はしてないけどいつでも帰ってくればいい、と僕に言う。ただしそのときはゼロからの修行が始まると思ってくれ、と最後に添えられていた。ありがたいと思った。
先月からDECoのメンバー5人で書かせていただいていた原稿が無事校了を迎えたと担当編集さんから連絡をいただく。「建築に溶けていく設備」というタイトルで、『新建築 住宅特集』誌8月号に特集記事の一つとして4ページ掲載されます。
環境系の院生室と歴史系の院生室を行ったりきたりする生活を送っています。
そんな身のおき方がこれからもずっと続いたらいいなと思いながら、二階と三階の階段を上り下りしています。
三時から鈴木研のゼミ。明日の歴史系全体ゼミにすずきせんせいが来られないので、僕を含む鈴木研のM2二人が修論のテーマ発表をする。普段からずっと考えていることだったので、つくったレジュメを読み上げなくてもしゃべれた。先生からはおおむね賛同を得られたけれど、「そういうテーマで行くなら当然定量的な構造解析までやってくださいね」と笑顔で。それは僕にとっても最も苦手な分野なのだけど、頑張らねば。資料収集の方法としては、19世紀当時の製品カタログを読んでみたらどうかとアドバイスをいただく。もう一人のM2のとうさんも研究対象はイギリス。海外研究につきものの資料収集の難を指摘されていて身につまされた。
夕方髪を切りに行って、夜は歩道橋コンペのスタディ。1/50で模型をつくり始めてみる。敷地の正確な図面がまだ手に入っていないのだが、扱う範囲はおよそ野球場一つ分くらいの規模。模型製作のためには膨大なスペースが必要なことがわかる。この季節、院試対策のために四年生が三階の演習室を占有する。困った。
7日
40人分の資料を印刷して歴史系のゼミに臨む。昨日お墨付きをもらっているテーマなので自信を持ってしゃべれた。つくったレジュメを読まずに大声でしゃべる僕に先生方はニヤニヤ。いろいろ前向きなアドバイスをいただく。東大の図書館には古い時代のRIBAの会報誌がストックされているらしく、それを当たれば19世紀の詳細な図面も手に入るのではないか、など。こうした領域横断的なテーマはやはり歴史系においては過去に例がないらしい。構造系の先生も喜ばれるでしょう、と好感触。ただし最後に、技術の話だけにとどまらず形而上学的な領域まで到達してねと釘を刺された。今まで歴史系が避けてきたテーマだから頑張ってほしい、と博士の先輩からも声をかけてもらう。うれしい。
四時からArchiTVのミーティング。三田の商店街を舞台に、二時間ほど案出しのブレスト。次回は町内会へのプレゼン用に模型とパネルをつくってみることに。
六時からこばやしさんと歩道橋コンペのスタディ。何気ない一言から前回とは少し違う意外な方向に転がりだす。こういうことがあるから三人でやるのは楽しいね。
終了後、畳プロジェクトのブレスト。インテリア系の雑誌を見たり家具見本市やデザイナーのWEBページを閲覧しながら、二時間ちょっと。また一つ案ができる。
休憩中に後輩から「最近、建築以外のことしてますか?」と。彼は最近、拘束のドローイングで知られるマシュー・バーニーの映画を観てきたらしい。彼は「建築における、無用なもの」を修士での研究テーマとしている。建築そのものとは直接関係なく、宗教や遊興等のルールや作法によって生まれ、建築の中に「残ってしまった」もの。日本の伝統家屋の中にはそんなものがたくさん存在しているという。
先週僕が送った「不合格でした」というメールに対して、返事に困っていたという父からパソコンにメールが来ていた。自分にとって何が今一番大切なやるべきことか、いつか優先順位が建築士試験になったときには頑張ってくれ、と。父は、期待はしてないけどいつでも帰ってくればいい、と僕に言う。ただしそのときはゼロからの修行が始まると思ってくれ、と最後に添えられていた。ありがたいと思った。
先月からDECoのメンバー5人で書かせていただいていた原稿が無事校了を迎えたと担当編集さんから連絡をいただく。「建築に溶けていく設備」というタイトルで、『新建築 住宅特集』誌8月号に特集記事の一つとして4ページ掲載されます。
環境系の院生室と歴史系の院生室を行ったりきたりする生活を送っています。
そんな身のおき方がこれからもずっと続いたらいいなと思いながら、二階と三階の階段を上り下りしています。
















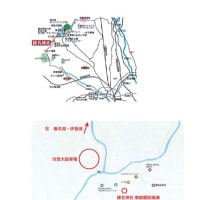
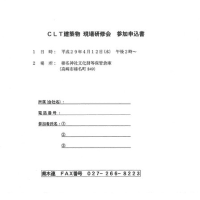
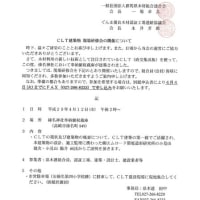







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます