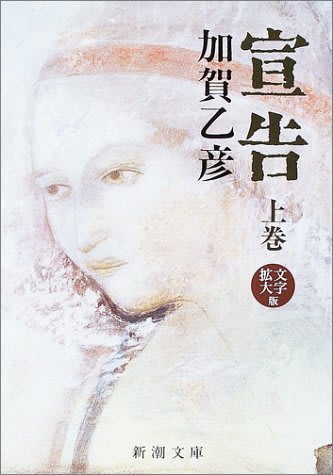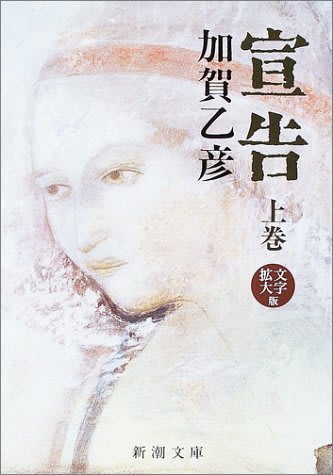
加賀乙彦『宣告』上中下1500頁弱
死刑囚の刑務所内での生活と心理を延々と細密に描いているこの長編を読み切るのには難儀した。
独房の扉に付けてある番号札は黒塗りの板で、水で融かした白墨で六一〇番と書いてある。
主人公の感慨:
「おれは人間であることを許されていない。法律規則という人間が作った文章が、おれから人間の属性を一つ一つ剥ぎとっていった。
しかし・・・しかし、それでもなおおれは考える、おれは死刑囚でも番号でも一枚の板でもなく、人間でありたいと。なぜならばおれは絶望することができるから、一枚の板のように従順に静かに平和に存在するのではなくて、おれには絶望する自由が残されているから。絶望する自由をもつかぎりにおいておれは人間であるのだから、おれは絶望しなくてはならぬ。絶望によってのみおれは人間に復帰できる。」
監獄医の若い精神科医の自問:
「お前、近木医官、善良で無邪気な青年よ。形而上学にひそむ苦しみを知らぬ若き科学者よ。死ぬまで悪人であらねばならぬ恐怖、それが本当の死の恐怖なんだ。いいかね、安らかに処刑台に上がるには、自分が処刑台に価する人間だと百パーセント納得していなくてはならないだろう。もし悔悟し改心し悪人であることをやめたら、信仰によって神の許しを得てしまったら、もはや自分は処刑台に価しないじゃないか。お前にこの矛盾が解けるかね。イエスと立場が正反対なんだよ。無垢なる人は殺されることに意義があった。しかし悪人は殺されることに意義がないことで、はじめて意義があるんだ。おれが死がこわいと言ったのはそのためさ。わかるかね、お医者さん。」
六一〇番は最後に宣告されて従容として刑に服する。
死刑制度反対を声高に叫んでいる小説ではない。読者に論理的思考を促している。
さて、上の若い監獄医の自問にどう応えたらいいのか。それが問題だ。