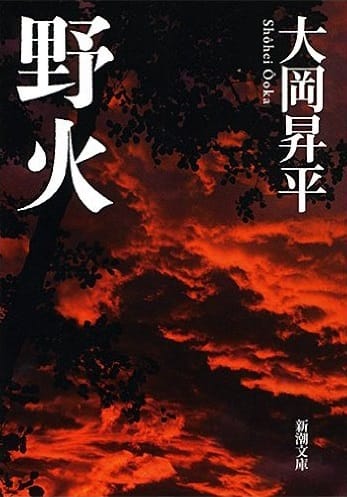作家(代表作『阿弥陀堂だより』)で内科医の南木佳士(なぎけいし)がパニック障害(僕はこの障害がどんな障害なのか、詳しい事を知らない)を発病し、十年間死ななかった理由を3つ挙げている。
(1)医者としてのプライドを捨て去り、患者になりきり、主治医の指示通りに薬を飲んだこと。
(2)病んでいる間にも時は過ぎ行くのだから、元の状態に戻ることが治癒だと考えるなら、それはあり得ないと諦めたこと。
(3)未来は己の意志で切り開けるものなのではなく、降って湧く出来事におろおろしながら対処していく、そのみっともない生き様こそが私の人生なのだと恥じ入りつつ開き直ること。
この3つを適切に言い換えれば、生きる指針になるかもしれない。しかし、生きる為の「主治医」は自分自身である他は無く、矢張り自分が自分自身を世話しなければならないのだと思う。ただ、その場合、(2)と(3)は充分に指針となるのだろうと思う。とりわけ若い人が自分自身に自信を無くした時は。そういう時は幾ら前向きになろうとしても、上手くいかないものなのだ。「恥じ入りつつ開き直る」ことがあってもいいではないか。
(1)医者としてのプライドを捨て去り、患者になりきり、主治医の指示通りに薬を飲んだこと。
(2)病んでいる間にも時は過ぎ行くのだから、元の状態に戻ることが治癒だと考えるなら、それはあり得ないと諦めたこと。
(3)未来は己の意志で切り開けるものなのではなく、降って湧く出来事におろおろしながら対処していく、そのみっともない生き様こそが私の人生なのだと恥じ入りつつ開き直ること。
この3つを適切に言い換えれば、生きる指針になるかもしれない。しかし、生きる為の「主治医」は自分自身である他は無く、矢張り自分が自分自身を世話しなければならないのだと思う。ただ、その場合、(2)と(3)は充分に指針となるのだろうと思う。とりわけ若い人が自分自身に自信を無くした時は。そういう時は幾ら前向きになろうとしても、上手くいかないものなのだ。「恥じ入りつつ開き直る」ことがあってもいいではないか。