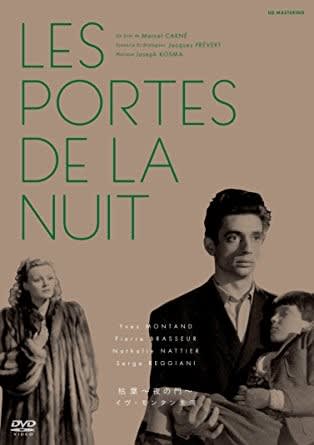『そして誰もいなくなった』(ルネ・クレール監督、1945年)を久し振りに観た。
本土から遠く離れた孤島に8人の男女が招待されてやって来る。
だが孤島の別荘には主人の姿が見えず、召使いのロジャース夫婦がいるだけだった。
不思議に思った彼らが話し合った結果、彼らはいずれも手紙で招かれたもので、差出人のユー・エヌ・オーエン(U. N. Owen)を誰も知らなかった。
ロジャース夫婦も周旋所から手紙で雇われ、1週間前に島に来たばかりだった。
本土との連絡は、数日後に来るボートだけで、それまで彼らは島から出られない。
食事の時、食卓にある“10人のインディアン”の置き物を見て若い女性ヴェラが古い子守唄を思い出し、スターロフがその曲を弾く。
そして、ロジャースがかけたレコードから10人の罪を告発する声が聞こえてきた。
10人はいずれも殺人を犯したというのだが、皆一様にそれを否定する・・・
(Movie Walkerより一部抜粋修正)
スターロフが毒入りの酒を飲んで死んだのを皮切りに、彼らは唄の歌詞にあるように一人ずつ殺されてゆく。
それに連動して、インディアンの人形が一体ずつ壊されていく。
姿を見せないオーエンとは、何者か。
ひょっとしたらオーエンは、インディアン島に集まった者の中にいるのではないか。
アガサ・クリスティの有名な作品を、ルネ・クレールはサスペンス調でなくコメディの味を振り掛けながら物語を進めていく。
当時はアメリカへ逃れていた最中でもあり、本来のルネ・クレールの作品らしさはないが、これはこれで、軽くても趣きがあったりする。
ただ驚くのは、この作品は小説の映画化ではなく、クリスティ自身の戯曲をベースにしているので、ラストで“そして誰もいなくなった”わけでなくハッピーエンドとなる。
思い返せば、これはルネ・クレールの作品の内で唯一劇場で鑑賞した映画である。
ルネ・クレール(1898~1981)の映画は、世代が違ってくるので同時代的に観ることはできなかった。
でもこの作品の日本公開は遅かったと言われるので、その時観たのか、それともリバイバルだったのか定かではないが、どこの劇場で観たかは憶えている。
と言っても、作品のラストでは誰もいなくなると憶えていたように思うので、自分の記憶も案外いい加減なものである。
本土から遠く離れた孤島に8人の男女が招待されてやって来る。
だが孤島の別荘には主人の姿が見えず、召使いのロジャース夫婦がいるだけだった。
不思議に思った彼らが話し合った結果、彼らはいずれも手紙で招かれたもので、差出人のユー・エヌ・オーエン(U. N. Owen)を誰も知らなかった。
ロジャース夫婦も周旋所から手紙で雇われ、1週間前に島に来たばかりだった。
本土との連絡は、数日後に来るボートだけで、それまで彼らは島から出られない。
食事の時、食卓にある“10人のインディアン”の置き物を見て若い女性ヴェラが古い子守唄を思い出し、スターロフがその曲を弾く。
そして、ロジャースがかけたレコードから10人の罪を告発する声が聞こえてきた。
10人はいずれも殺人を犯したというのだが、皆一様にそれを否定する・・・
(Movie Walkerより一部抜粋修正)
スターロフが毒入りの酒を飲んで死んだのを皮切りに、彼らは唄の歌詞にあるように一人ずつ殺されてゆく。
それに連動して、インディアンの人形が一体ずつ壊されていく。
姿を見せないオーエンとは、何者か。
ひょっとしたらオーエンは、インディアン島に集まった者の中にいるのではないか。
アガサ・クリスティの有名な作品を、ルネ・クレールはサスペンス調でなくコメディの味を振り掛けながら物語を進めていく。
当時はアメリカへ逃れていた最中でもあり、本来のルネ・クレールの作品らしさはないが、これはこれで、軽くても趣きがあったりする。
ただ驚くのは、この作品は小説の映画化ではなく、クリスティ自身の戯曲をベースにしているので、ラストで“そして誰もいなくなった”わけでなくハッピーエンドとなる。
思い返せば、これはルネ・クレールの作品の内で唯一劇場で鑑賞した映画である。
ルネ・クレール(1898~1981)の映画は、世代が違ってくるので同時代的に観ることはできなかった。
でもこの作品の日本公開は遅かったと言われるので、その時観たのか、それともリバイバルだったのか定かではないが、どこの劇場で観たかは憶えている。
と言っても、作品のラストでは誰もいなくなると憶えていたように思うので、自分の記憶も案外いい加減なものである。