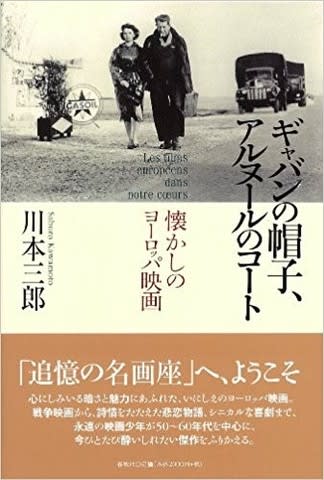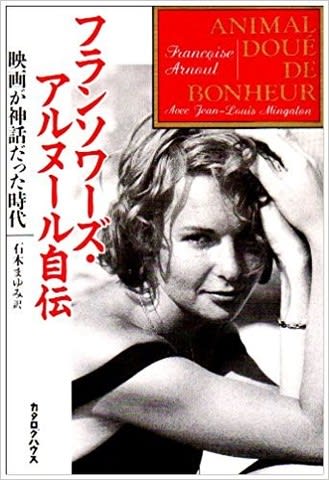3月3日、老衰だとのことである。まだ88歳だったというのに。
そう言えば、もう何年も近況の情報が聞けなかった。
今現在、どのように過ごしてみえるのかと気にはなっていた。
このブログ記事は書かないでおこうと思った。
しかし、後々、大江はいついなくなってしまったのだろうと振り返ってみた場合のためにメモしておきたい。
私が大江健三郎の作品に衝撃を受けたのは、家にあったそれこそ初期の全集の中の『奇妙な仕事』、『死者の奢り』を読んだのがきっかけだった。
なぜ、学生がこのような作品を書けるのか、そのテーマの捉え方にとてもではないが想像を絶するものを感じた。
私は大江よりそれこそ『遅れてきた青年』だったとしても、同じ20歳前後の人間として共感以上のものを感じた。
それ以後、『われらの狂気を生き延びる道を教えよ』(1969年)からは同時代の人間として、新刊が出るたびにそれを手にした。
20代後半には講演を聴くチャンスにも巡り会え、あの四国の森の谷間の村についての歴史や伝承は、いつしか私の確固たるイメージ世界となって行った。
その世界ばかりでなく退職をしたら未読となっている作品を余生の糧として、ノンビリすべて読もうと考えていたが現実は案外と難しくて、
あの多大な作品数の中で、まだ3分の1ぐらいは未読のままとなっている。
でありながらも、大江健三郎は私にとって常に身近な存在としてあり、ものの見方、考え方はそこから吸収してきたと思っている。
今回の訃報を機に、今後もこの作家の作品を少しずつでも読み続けていきたいと心を新たにした。
ご冥福をお祈りいたします。