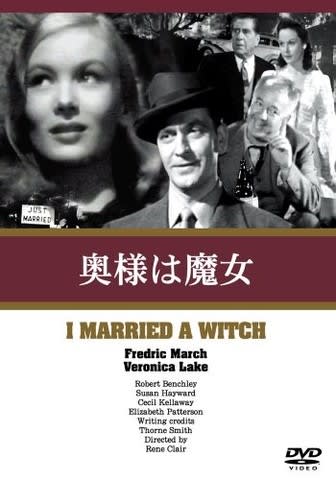『嘆きのテレーズ』(マルセル・カルネ監督、1953年)を観る。
フランスのリヨン。
裏町の布地店のテレーズは、気弱なくせに傲慢な夫カミーユと、この息子を溺愛する義母に挟まれて、冷たく暗い日常生活を送っている。
ある日、貨物駅に勤めるカミーユは、イタリア人でトラック運転手のローランと知り合い、意気投合して酔い、ローランに家まで送ってもらう。
それ以後、カミーユの家に出入りするようになったローランは、テレーズの立場を知れば知るほど、彼女に惹かれていった。
そして、思いつめたローランは駆落ちを迫る。が、テレーズの方は躊躇し・・・
幼い頃に両親が亡くなった後、面倒を叔母にみてもらっていたテレーズ。
カミーユとは元々一緒に住んでいた従兄妹関係で、テレーズとしては単に妻になっただけの間柄。
だから、家政婦のような生活に、店の手伝い。
何事にも興味を失って、毎日を淡々とこなすだけのテレーズ。
そこに現れたのが、逞しく男らしいローランだから、テレーズの気持ちもぐらつく。
そのテレーズをシモーヌ・シニョレが、無表情に近い表現で、諦めとやるせなさを表す。
日々に嫌気がさしているテレーズは、叔母親子に恩もあって苦悩するが、とうとう夫に別れを切り出す。
半狂乱になる夫。
カミーユは、テレーズの気持ちを変えさせようするが、それも無駄となると一つの案を思いつく。
パリ行きの列車に一緒に乗り込んだ、カミーユとテレーズ。
それに気付き、その列車に追いつき乗り込んでくるローラン。
その後半の、息も付かせない緊張感の成り行き。
そのサスペンス感が堪らない。
もうこうなると、ラストまでノンストップ。
思い出話になるが、この映画は昔、どうしても観たかった作品の一つだった。
ある時、自主上映グループが、上映してくれてやっと目にすることができた。
その時の感動は、今でも甦るものがある。
特にラストで、午後5時に教会の鐘が鳴るなか、ホテルのメイドが手紙を持ってポストに向かうところ。
二人の運命を決する、このシーンはそうそう簡単に忘れられるものではない。
だから私にとって、“カルネ”と言えば『嘆きのテレーズ』が一番となってしまう。
因みに、上映してくれたグループは後に、独自路線のミニシアターとして現在に至る、「名古屋シネマテーク」であることを付記しておきたい。
フランスのリヨン。
裏町の布地店のテレーズは、気弱なくせに傲慢な夫カミーユと、この息子を溺愛する義母に挟まれて、冷たく暗い日常生活を送っている。
ある日、貨物駅に勤めるカミーユは、イタリア人でトラック運転手のローランと知り合い、意気投合して酔い、ローランに家まで送ってもらう。
それ以後、カミーユの家に出入りするようになったローランは、テレーズの立場を知れば知るほど、彼女に惹かれていった。
そして、思いつめたローランは駆落ちを迫る。が、テレーズの方は躊躇し・・・
幼い頃に両親が亡くなった後、面倒を叔母にみてもらっていたテレーズ。
カミーユとは元々一緒に住んでいた従兄妹関係で、テレーズとしては単に妻になっただけの間柄。
だから、家政婦のような生活に、店の手伝い。
何事にも興味を失って、毎日を淡々とこなすだけのテレーズ。
そこに現れたのが、逞しく男らしいローランだから、テレーズの気持ちもぐらつく。
そのテレーズをシモーヌ・シニョレが、無表情に近い表現で、諦めとやるせなさを表す。
日々に嫌気がさしているテレーズは、叔母親子に恩もあって苦悩するが、とうとう夫に別れを切り出す。
半狂乱になる夫。
カミーユは、テレーズの気持ちを変えさせようするが、それも無駄となると一つの案を思いつく。
パリ行きの列車に一緒に乗り込んだ、カミーユとテレーズ。
それに気付き、その列車に追いつき乗り込んでくるローラン。
その後半の、息も付かせない緊張感の成り行き。
そのサスペンス感が堪らない。
もうこうなると、ラストまでノンストップ。
思い出話になるが、この映画は昔、どうしても観たかった作品の一つだった。
ある時、自主上映グループが、上映してくれてやっと目にすることができた。
その時の感動は、今でも甦るものがある。
特にラストで、午後5時に教会の鐘が鳴るなか、ホテルのメイドが手紙を持ってポストに向かうところ。
二人の運命を決する、このシーンはそうそう簡単に忘れられるものではない。
だから私にとって、“カルネ”と言えば『嘆きのテレーズ』が一番となってしまう。
因みに、上映してくれたグループは後に、独自路線のミニシアターとして現在に至る、「名古屋シネマテーク」であることを付記しておきたい。