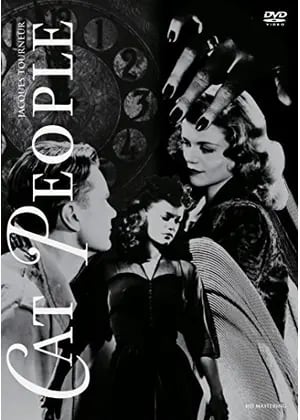以前から加藤登紀子の歌で馴染みの『百万本のバラ』を、最近、他の歌い手で聴いていたりする。
歌っているのはYOYOMI(パク・ユンア)
【YouTubeより】
ロシアのアーラ・プガチョワの持ち歌であるこの歌の内容は、グルジア(現ジョージア)の画家ニコ・ピロスマニがフランス人の女優マルガリータに恋をし、
彼女の泊まるホテルの前の広場を花で埋め尽くしたという逸話をもとにしている。
【YouTubeより】 百万本のバラ/アーラ・プガチョワ
原曲である「マーラが与えた人生」は、バルト三国のラトビアの作曲家ライモンド・パウルスがソ連統治時代の1981年に作曲した。
アイヤ・ククレが歌唱する歌詞は、大国に翻弄されるラトビアの苦難を暗示する内容で、現在のウクライナ・ロシアの関係に通じる。
【YouTubeより】 マーラが与えた人生/アイヤ・ククレ(「百万本のバラ」の原曲)
そのロシアによるウクライナ侵攻に関連して、歌手アーラ・プガチョワは、夫のガルキンが今年秋、ロシア政府から「外国の代理人」(スパイ)として認定されると、
「私も『代理人』に認定せよ、私も夫と同じく平和を望み、軍事作戦の幻想に踊らされて若者が死ぬことに心を痛めている」と、ロシア政権を批判した。
(Wikipediaより)
歌っているのはYOYOMI(パク・ユンア)
【YouTubeより】
ロシアのアーラ・プガチョワの持ち歌であるこの歌の内容は、グルジア(現ジョージア)の画家ニコ・ピロスマニがフランス人の女優マルガリータに恋をし、
彼女の泊まるホテルの前の広場を花で埋め尽くしたという逸話をもとにしている。
【YouTubeより】 百万本のバラ/アーラ・プガチョワ
原曲である「マーラが与えた人生」は、バルト三国のラトビアの作曲家ライモンド・パウルスがソ連統治時代の1981年に作曲した。
アイヤ・ククレが歌唱する歌詞は、大国に翻弄されるラトビアの苦難を暗示する内容で、現在のウクライナ・ロシアの関係に通じる。
【YouTubeより】 マーラが与えた人生/アイヤ・ククレ(「百万本のバラ」の原曲)
そのロシアによるウクライナ侵攻に関連して、歌手アーラ・プガチョワは、夫のガルキンが今年秋、ロシア政府から「外国の代理人」(スパイ)として認定されると、
「私も『代理人』に認定せよ、私も夫と同じく平和を望み、軍事作戦の幻想に踊らされて若者が死ぬことに心を痛めている」と、ロシア政権を批判した。
(Wikipediaより)