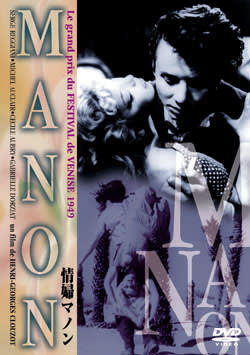ブログ「新・「言葉の泉」」の、ろこさんが『戦争絶滅へ、人間復活へ』(むのたけじ・聞き手黒岩比佐子著、岩波新書・2008年)を紹介されていたので、
『希望は絶望のど真ん中に』(岩波新書・2011年)、『日本で100年、生きてきて』(朝日新書、2015年)と共に読み終えた。
正直な話、ろこさんの紹介があるまで、「むのたけじ」というジャーナリストが存在するということさえ知らなかった。
太平洋戦争で日本が敗戦したその当日、「われわれは間違ったことをしてきたんだから、きちんとけじめをつけるべきだ」と、ひとり朝日新聞を辞職した人。
そして、1948年から秋田県で週刊新聞「たいまつ」を創刊し、その地域新聞を30年間発行し続けた人。
だから、どこを読んでみても、言う内容の言葉自体の重みが違う。
「今見る日本のていたらくは、今はじまったことではない。
同様また共通の状態は、すでに過去に幾度も現れていた。現在は過去の子どもだ。」と言い、
「戦後の歩みが日本の現状を生んだ直接の要因なら、根本の要因は1931年の満州事変という中国への侵略開始から
連合国のポツダム宣言への屈服に至る十五年戦争の時期に存在していた。」と分析する。
「つまり、私たちの国を今の姿にした根本の要因は、・・・少なくとも十五年戦争当時まで引き返して、
そこから吟味しなければよみがえる活路は作れない」と、力説する。
「今の世は明るいものは余りに少なく、暗いものは余りに多く見えるが、両者は別個のばらばらではない。
絶望と見える対象を嫌ったり恐れたりして目をつぶって、そこを去れば、もう希望とは決して会えない。
絶望すべき対象にはしっかと絶望し、それを克服するために努力し続ければ、それが希望に転化してゆくのだ。
そうだ、希望は絶望のど真ん中、そのどん底に実在しているのだ。」
それがホントだ、と気付くようになったのは90歳代になってからだ、それだけの経験を必要としたのだ。と言う。
「自分にも言い聞かせているけど、中途半端なことはするな。迷ったらやめろ。
やろうと思ったら死に物狂いで頑張る。奇跡なんてない。奇跡は自分でつくる。
そう思って生きれば、日本社会はみるみる変わると思うんです。」
「私は90歳以降は、1年ごとに生きるのが大変になった。それでも頭だけはしっかりしている。
年をとればとるほど経験と知恵は重なる。それを生かしていける。死ぬ時が人間てっぺん。今もそう思っている。」
『戦争絶滅へ、人間復活へ』が93歳、『希望は絶望のど真ん中に』は96歳の時の刊行。
『日本で100年、生きてきて』は94歳から100歳までの聞き書きで、去年の刊行。
鋭い批評精神にただただ自然と頭が下がり、その「むの」さんから見れば私なんかまだまだ子供である。頑張らなきゃと思う。
『希望は絶望のど真ん中に』(岩波新書・2011年)、『日本で100年、生きてきて』(朝日新書、2015年)と共に読み終えた。
正直な話、ろこさんの紹介があるまで、「むのたけじ」というジャーナリストが存在するということさえ知らなかった。
太平洋戦争で日本が敗戦したその当日、「われわれは間違ったことをしてきたんだから、きちんとけじめをつけるべきだ」と、ひとり朝日新聞を辞職した人。
そして、1948年から秋田県で週刊新聞「たいまつ」を創刊し、その地域新聞を30年間発行し続けた人。
だから、どこを読んでみても、言う内容の言葉自体の重みが違う。
「今見る日本のていたらくは、今はじまったことではない。
同様また共通の状態は、すでに過去に幾度も現れていた。現在は過去の子どもだ。」と言い、
「戦後の歩みが日本の現状を生んだ直接の要因なら、根本の要因は1931年の満州事変という中国への侵略開始から
連合国のポツダム宣言への屈服に至る十五年戦争の時期に存在していた。」と分析する。
「つまり、私たちの国を今の姿にした根本の要因は、・・・少なくとも十五年戦争当時まで引き返して、
そこから吟味しなければよみがえる活路は作れない」と、力説する。
「今の世は明るいものは余りに少なく、暗いものは余りに多く見えるが、両者は別個のばらばらではない。
絶望と見える対象を嫌ったり恐れたりして目をつぶって、そこを去れば、もう希望とは決して会えない。
絶望すべき対象にはしっかと絶望し、それを克服するために努力し続ければ、それが希望に転化してゆくのだ。
そうだ、希望は絶望のど真ん中、そのどん底に実在しているのだ。」
それがホントだ、と気付くようになったのは90歳代になってからだ、それだけの経験を必要としたのだ。と言う。
「自分にも言い聞かせているけど、中途半端なことはするな。迷ったらやめろ。
やろうと思ったら死に物狂いで頑張る。奇跡なんてない。奇跡は自分でつくる。
そう思って生きれば、日本社会はみるみる変わると思うんです。」
「私は90歳以降は、1年ごとに生きるのが大変になった。それでも頭だけはしっかりしている。
年をとればとるほど経験と知恵は重なる。それを生かしていける。死ぬ時が人間てっぺん。今もそう思っている。」
『戦争絶滅へ、人間復活へ』が93歳、『希望は絶望のど真ん中に』は96歳の時の刊行。
『日本で100年、生きてきて』は94歳から100歳までの聞き書きで、去年の刊行。
鋭い批評精神にただただ自然と頭が下がり、その「むの」さんから見れば私なんかまだまだ子供である。頑張らなきゃと思う。