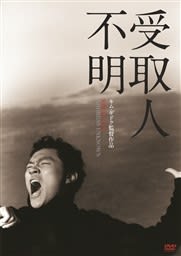またまたキム・ギトクの監督作品で、『殺されたミンジュ』(2014年)を観た。
5月のソウル市内。
夕闇の中、何者か達に追われ、必死に逃げ惑う女子高生のミンジュ。
路地の片隅に追い詰められたミンジュは、無残にも殺されてしまう。
事件は誰に知られることもなく、闇に葬りさられていく。
この事件から1年たった頃、ミンジュの死の真相を執拗に追いかける、不気味な謎の集団が動き始める。
謎の集団は、ミンジュ殺害に関わったそのうちの一人を誘拐して、拷問を加え「去年の5月9日のこと」を執拗に問いただす。
拷問の恐怖に怯える容疑者は、自白調書を書いて、許しを請い願う。
変装した謎の集団は、次にまた一人と、誘拐しては自白を強要していく・・・
この謎の7人の集団とは何者か?
物語が進んでわかるのは、実はリーダー格がネット呼びかけをして、集まった社会的弱者たち。
片や、ミンジュの殺害に絡んだ7人は?
拷問によって明らかになってくるのは、「上からの指示に従っただけ」ということ。
仕事だと割り切れば、社会的倫理感を批難されても敢て実行する者たち。
そして、一人ひとり問い詰めていけば、頂上に、政府に関係している人物まで行き着く構図。
このことは、社会的“負け組”が、社会の出世街道に乗ろうしている“勝ち組”に対して、
大義名分の「社会正義を遂行する」と言いながら、日頃の鬱憤晴らしをする筋書きに他ならない。
では、この集団のリーダーとは誰なのか?
ミンジュと二人で写っている写真からすると、ミンジュの父親なのか。
彼は世の中の悪を正そうとするが、自らの残虐行為によって相手の悪と何ら違わぬことをする。
その皮肉さ。
そこに表れる、復讐しかできないという空しい悲しさが否応なしに付いてまわる。
キム・ギドクは韓国の民主(ミンジュ)主義の危機を意識し、個人は社会の中でどう生き、働くか、それらを改めて問い詰める。
このことは、他国の話と済ますには、あまりにも身近すぎる内容を伴う。
ただ、この映画にそのような暗喩が含まれていても、残念ながらそれほどには成功していないと思う。
いうのも、キム・ギドクが監督・脚本・撮影・編集・製作総指揮と一人でこなし、おまけに10日程で撮り終えたとなると熟成された味とは言えない。
おまけに、殺害容疑者役の“キム・ヨンミン”が8役もやっているとなると、観ていて、同じ人物の役なのか他人として捉えたらいいのか、
出てくるその都度に考えながら画面を追わなければならない。
いくらなんでも、チョット手抜き過ぎではないかと思ってしまう。
それと残念なことに、では何のためにミンジュは殺されたのかという肝心なことは何も教えてくれない。
だから、どうしてもモヤモヤした不完全燃焼な宙ぶらりんな気持ちが残ってしまう。
でも、キム・ギドクを応援する立場から言えば、この監督の意図も汲み取れる力作であることは間違いない。
5月のソウル市内。
夕闇の中、何者か達に追われ、必死に逃げ惑う女子高生のミンジュ。
路地の片隅に追い詰められたミンジュは、無残にも殺されてしまう。
事件は誰に知られることもなく、闇に葬りさられていく。
この事件から1年たった頃、ミンジュの死の真相を執拗に追いかける、不気味な謎の集団が動き始める。
謎の集団は、ミンジュ殺害に関わったそのうちの一人を誘拐して、拷問を加え「去年の5月9日のこと」を執拗に問いただす。
拷問の恐怖に怯える容疑者は、自白調書を書いて、許しを請い願う。
変装した謎の集団は、次にまた一人と、誘拐しては自白を強要していく・・・
この謎の7人の集団とは何者か?
物語が進んでわかるのは、実はリーダー格がネット呼びかけをして、集まった社会的弱者たち。
片や、ミンジュの殺害に絡んだ7人は?
拷問によって明らかになってくるのは、「上からの指示に従っただけ」ということ。
仕事だと割り切れば、社会的倫理感を批難されても敢て実行する者たち。
そして、一人ひとり問い詰めていけば、頂上に、政府に関係している人物まで行き着く構図。
このことは、社会的“負け組”が、社会の出世街道に乗ろうしている“勝ち組”に対して、
大義名分の「社会正義を遂行する」と言いながら、日頃の鬱憤晴らしをする筋書きに他ならない。
では、この集団のリーダーとは誰なのか?
ミンジュと二人で写っている写真からすると、ミンジュの父親なのか。
彼は世の中の悪を正そうとするが、自らの残虐行為によって相手の悪と何ら違わぬことをする。
その皮肉さ。
そこに表れる、復讐しかできないという空しい悲しさが否応なしに付いてまわる。
キム・ギドクは韓国の民主(ミンジュ)主義の危機を意識し、個人は社会の中でどう生き、働くか、それらを改めて問い詰める。
このことは、他国の話と済ますには、あまりにも身近すぎる内容を伴う。
ただ、この映画にそのような暗喩が含まれていても、残念ながらそれほどには成功していないと思う。
いうのも、キム・ギドクが監督・脚本・撮影・編集・製作総指揮と一人でこなし、おまけに10日程で撮り終えたとなると熟成された味とは言えない。
おまけに、殺害容疑者役の“キム・ヨンミン”が8役もやっているとなると、観ていて、同じ人物の役なのか他人として捉えたらいいのか、
出てくるその都度に考えながら画面を追わなければならない。
いくらなんでも、チョット手抜き過ぎではないかと思ってしまう。
それと残念なことに、では何のためにミンジュは殺されたのかという肝心なことは何も教えてくれない。
だから、どうしてもモヤモヤした不完全燃焼な宙ぶらりんな気持ちが残ってしまう。
でも、キム・ギドクを応援する立場から言えば、この監督の意図も汲み取れる力作であることは間違いない。