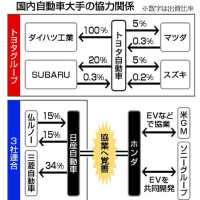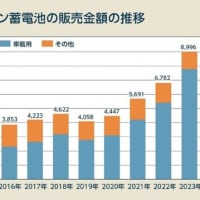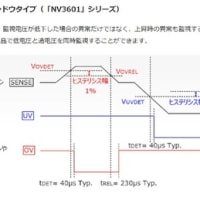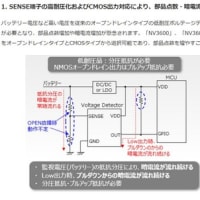スラップ訴訟と現代の雇用関係(ユニクロの現実)
最近時々聞かれる様になった「スラップ(英: SLAPP、strategic lawsuit against public participation)訴訟」とは、特に民事訴訟において「公的に声を上げたために起こされる」加罰的・報復的訴訟を指す言葉である。
一般的には、社会的にみて「比較強者(社会的地位の高い政治家、大企業および役員など)」が、社会的にみて「比較弱者(社会的地位の低い個人・市民・被害者)」など、公の場での発言や政府・自治体などへの対応を求める行動が起こせない者を相手取り、言論の封圧や威嚇を目的として行われる。つまり、強者は訴訟に必ずしも勝つ論理もないのに、訴訟を提起すること自体で、口封じ訴訟、恫喝訴訟、威圧訴訟、批判的言論威嚇目的訴訟などとの意味を含んでのものだ。
訴訟大国の米国では、複数州がスラップによる提訴を防ぐ法律を制定している。スラップ訴訟が憲法で保障される表現の自由を侵害するものとして問題視されたためだ。訴えを起こした原告が正当性を立証できなければ訴訟が打ち切られるほか、訴訟に州政府が参加して被告を支援することもあり、州ごとに多様な支援策があるという。
以下は、最近関心を傾けている作家である鎌田 慧 (ルポライター)氏の論評だが、現在鎌田氏の初期作といえる『自動車絶望工場』を読み進めているのだが、あの「蟹工船」をもある意味類似する、労働者の非人間的扱いに驚きつつ読み進めている。この書評は、完読後に改めて記したいが、Netで鎌田氏の論評で興味深い論評を見つけたので紹介してみたい。長くなるが、リング切れを怖れ、前文転載する。

--------------------------------------
020.08.10書評 出典:https://books.bunshun.jp/articles/-/5679?page=2
「『自動車絶望工場』から50年、日本企業は変わったのか」
文:鎌田 慧 (ルポライター)
『ユニクロ潜入一年』(横田 増生)
出典 : #文春文庫
『ユニクロ潜入一年』(横田 増生)
1/3P
ユニクロ社長・柳井正氏は、自社がブラック企業と批判されていることにたいして、「限りなくホワイトに近いグレー企業」と余裕をみせて答えている。完全なホワイトではない、とは謙遜かそれともホンネなのか。
「悪口を言っているのは僕と会ったことがない人がほとんど。会社見学をしてもらって、あるいは社員やアルバイトとしてうちの会社で働いてもらって、どういう企業なのかをぜひ体験してもらいたいですね」
挑発的である。この作品『ユニクロ潜入一年』がユニークなのは、前著『ユニクロ帝国の光と影』を出版して名誉毀損で訴えられ、損害賠償(二億二千万円!)、さらに出版差し止め処分を請求された文藝春秋と、訴えられなかった著者とが手を携え、地裁、高裁、最高裁と争ってユニクロの訴えを退けたあと、追撃の一冊として出版されたことにある。
これは、著者が柳井社長の挑発に乗ったかたちで、ユニクロのいくつかの販売店にアルバイトとして入職、さらにかつて働いていた労働者に取材して書いた、冷静沈着な一書である。サービス残業の恒常化などを自己体験で確認、柳井氏に叩き返した証拠であり、完璧な「勝訴」の記録である。
売り上げ額を誇るような大企業が、言論にたいして「フェイク」と声高に主張して、「スラップ」(恫喝訴訟)を構える典型的な事例である。しかし、企業は社会的存在であって、「コンプライアンス」(法令遵守)ばかりか、内外の批判を謙虚に受け止めて改革し、時代にあわせていかないかぎり生き残れない。いまの時代は内部の批判者としての労働組合が無力化し、経営者が社内民主主義を自己点検する志向が弱まっている。
企業経営は内外の批判に対応し、時代のニーズに合わせるのが賢明なはずだ。社内では箝口令を敷き、外部の批判にたいしては威丈高に高額な賠償請求を振りかざす。批判者を恫喝するのは、経営者の狭量を示して美しくない。世界から注目されているユニクロが、「巨大な柳井商店」の流儀のままでいるのか、企業内言論の自由を確立し、働くものを大事にする大らかな社風で、世界に迎え入れられるのか、その問いかけとしてこの本は貴重である。
本書を読んで意表を衝かれる想いがしたのは、年間売り上げ八七二九億円、純利益五二八億円、従業員五万二八三九人。世界に冠たる大企業が、つねにアルバイターを募集し続けるほど、人手不足が常態化している現状である。販売をささえているのは、主婦と学生、短時間勤務のアルバイターたち。五十過ぎの著者でも即決採用、翌日出勤で迎え入れられるほどに、労働者が払底している。
ユニクロは世界にむけて店舗を展開しているのだが、あたかも広大無辺の戦場をとりとめもない傭兵でカバーしていて、さほどの不安感をもっていない。それが流通業界に不案内なわたしをまず驚嘆させた。
2/3P
著者の最初の就職先は、千葉県の幕張新都心店だった。その店は六十人の従業員がおり、その構成は、二ヶ月間だけの短期アルバイト、半年ごとに契約を更新する長期アルバイト(月間百時間未満の労働)、それに準社員(月間百時間以上の労働)の三階層。「猫の手も借りたい」ほどの暮れなどの繁忙期には、販売員になりそうな客を物色し、勧誘する、というのも驚きだ。将来、社員化する、という約束で採用する「地域正社員」というものもあるが、採用基準はきびしいようだ。
「先日UNIQLOの記事が、ニュースになっていましたが、私の娘は息子と二人の母子家庭です。UNIQLOは子育て応援と言う事で、地域正社員希望で●●市の●●店に入社しましたが、一年以上が過ぎてもパートで、閑散期は週一~二日しかシフトをいれてくれませんし、当日ラインが来て出勤してと、日雇い労働者と同じです。完全なブラック企業です」
とのメールが編集部宛に送られてきたという。客が減れば出勤日を減らし、客がふえれば出勤を強制する。販売員は調達自在な資材扱いでしかない。
いま、非正規労働者は総労働人口の三八パーセント強に達する。が、非正規率はユニクロの方が、はるかに高水準である。日本有数の巨大アパレル企業が、非正規の殿堂であることが、日本人の生活不安定化を象徴している。
東京・新宿東口。二〇一二年九月に開店した、一階から三階までがユニクロ、地下三階から一階、四階から六階までがビックカメラ。開店日の朝、入り口に四千人が詰めかけたというこの「ビックロ」館のユニクロは、外国人労働者が「五割」を占める。外国人のアルバイトが多いのは、時給千円では、日本人のアルバイトがあつまらないからだ。
編集部にメールを送ってきた女性の娘は、結局「地域正社員」に到達する前に、中途退社した。人件費は削れるだけ削り、人手が足りなくなると、片っ端から動員をかけて残業を強制する。もっとも原始的な人件費削減法である。
ユニクロは製品を仕入れて販売するだけではなく、SPA(製造小売り)に大転換して成功の端緒をひらいた。一九九〇年代後半にアメリカのGAP、スペインのZARAなどの方式を採りいれるのがはやかったのだ。
「作った商品をいかに売るかではなく、売れる商品をいかに早く特定し、作るかの作業に焦点を合わせる」(前著文庫版58ページ)商法である。
企画、生産から販売までを串刺しして、ユニクロはすべてを管理。下請に生産させた商品は、自社で一〇〇パーセント引き取る。そのため、著者は前著の中国に続いて、この本の執筆のために、香港のユニクロ下請け、カンボジアの下請け工場の取材にでかけることになる。
「製造原価と販売価格の差額が、ユニクロの利益の源泉である。製造原価の大半を占めるのが人件費なのだから、人件費が安いところで作れば、利幅が大きくなる」
そのひとつの例として、横田さんが中国取材で着ていた焦げ茶色のポロシャツは、日本で買ったときは一九九〇円だった。しかし、そのポロシャツは、中国から仕入れたときは三五〇円だった、と前著に書いている。国際アパレル企業が、中国から東南アジアへ、最近ではカンボジアからバングラデシュまで移動したのは、より安い賃金をもとめてのことである。
一九六〇年代から日本企業は、韓国、シンガポールへ、さらにフィリピン、インドネシア、台湾、中国、ベトナム、カンボジア、バングラデシュへと進出した。公害企業の転進もあった。労働運動を回避する狙いもあったであろう。わたしもそれぞれの国へ日本企業を追いかけていった。たとえば、メキシコの自動車部品工場で、日本人経営者は「これからは賃金の安いべトナムへ移ります」といっていた。資本に国境はない。が、それを見直させたのが、新型コロナウイルスである。
新型コロナウイルス厄災が世界に拡がるなかで、「ジャスト・イン・タイム」の生産管理方式を前提にした、サプライ・チェーンが機能しなくなった。たとえば単価が低く、利益率も低いマスクは、人間の健康と生命の安全に必要であっても日本ではほとんど生産されていなかった。単価重視、利益第一主義、経済の外部化の脆さが明らかになった。
3/3P
ユニクロの企業経営の人間疎外を象徴している、次のような文章がある。
「レジでの精算業務を平均九十秒とすると、顧客のレジ誘導が課題となる。レジ列先頭からレジに到着するまで平均七秒をムダにしているからだ。ピークの一時間当たりの顧客数を千人とすると、千人×七秒=七千秒がムダになっている。この七千秒を有効に使えば、さらに七十七人のお客様をレジを通過させることができる」
客の誘導をまるでベルトコンベアー式に、一秒のムダもなく管理しようとする標準作業の思想は、人間と向い合う仕事ではない。人間がもつ時間をムダとして排除する、現代の工場生産の、あえていえば「トヨタ生産方式」の直輸入である。
生産と販売を機械的に直結させ、人間を介在させない疎外の方式は、サービス産業の自己否定であろう。まして衣類は人間を安らぎで包み込むもののはずだ。まもなく、膨大な商品の管理、販売はAIに代えられよう。
横田増生さんの世界的な流通現場への潜入ルポは、第三次産業での現在只今の人間疎外の報告である。もっとも人間的な関係で成立つ職場が、利益追求のために人間関係が解体されている。この矛盾を暴いて、二億二千万円の損害賠償請求と書籍回収請求の裁判を受けた。
五十年前、わたしは、自動車、鉄鋼、ガラス工場での解体された労働について、トヨタ自動車本社工場、新日鉄(現日本製鉄)八幡製鉄所、旭硝子(船橋工場)などでの体験ルポを発表したが、巨大企業三社は訴えるほど愚かではなかった。事実に謙虚、かつ報道を尊重したのだろうか。が、そのどちらにしても、労働現場の自由は、それ以降ますますちいさなものになったことを理解できる。
ユニクロの役員報酬額十億円が、二十億円に引き上げられた。社内役員は柳井正氏と二人の息子。柳井家以外のもう一人の役員に株式保有はない。柳井家一家で四十数%の株式保有。売上高に占める人件費は、十三・八%から十三・二%に下がった。柳井正氏個人の自社株配当金は、年間百億円。総資産二兆円。
ああ、「偉大なる柳井商店」はどこへいくのか? 前近代的な人間蔑視が、人間尊重の意識に変るのは、これからであろう。
--------------------------------------
最近時々聞かれる様になった「スラップ(英: SLAPP、strategic lawsuit against public participation)訴訟」とは、特に民事訴訟において「公的に声を上げたために起こされる」加罰的・報復的訴訟を指す言葉である。
一般的には、社会的にみて「比較強者(社会的地位の高い政治家、大企業および役員など)」が、社会的にみて「比較弱者(社会的地位の低い個人・市民・被害者)」など、公の場での発言や政府・自治体などへの対応を求める行動が起こせない者を相手取り、言論の封圧や威嚇を目的として行われる。つまり、強者は訴訟に必ずしも勝つ論理もないのに、訴訟を提起すること自体で、口封じ訴訟、恫喝訴訟、威圧訴訟、批判的言論威嚇目的訴訟などとの意味を含んでのものだ。
訴訟大国の米国では、複数州がスラップによる提訴を防ぐ法律を制定している。スラップ訴訟が憲法で保障される表現の自由を侵害するものとして問題視されたためだ。訴えを起こした原告が正当性を立証できなければ訴訟が打ち切られるほか、訴訟に州政府が参加して被告を支援することもあり、州ごとに多様な支援策があるという。
以下は、最近関心を傾けている作家である鎌田 慧 (ルポライター)氏の論評だが、現在鎌田氏の初期作といえる『自動車絶望工場』を読み進めているのだが、あの「蟹工船」をもある意味類似する、労働者の非人間的扱いに驚きつつ読み進めている。この書評は、完読後に改めて記したいが、Netで鎌田氏の論評で興味深い論評を見つけたので紹介してみたい。長くなるが、リング切れを怖れ、前文転載する。

--------------------------------------
020.08.10書評 出典:https://books.bunshun.jp/articles/-/5679?page=2
「『自動車絶望工場』から50年、日本企業は変わったのか」
文:鎌田 慧 (ルポライター)
『ユニクロ潜入一年』(横田 増生)
出典 : #文春文庫
『ユニクロ潜入一年』(横田 増生)
1/3P
ユニクロ社長・柳井正氏は、自社がブラック企業と批判されていることにたいして、「限りなくホワイトに近いグレー企業」と余裕をみせて答えている。完全なホワイトではない、とは謙遜かそれともホンネなのか。
「悪口を言っているのは僕と会ったことがない人がほとんど。会社見学をしてもらって、あるいは社員やアルバイトとしてうちの会社で働いてもらって、どういう企業なのかをぜひ体験してもらいたいですね」
挑発的である。この作品『ユニクロ潜入一年』がユニークなのは、前著『ユニクロ帝国の光と影』を出版して名誉毀損で訴えられ、損害賠償(二億二千万円!)、さらに出版差し止め処分を請求された文藝春秋と、訴えられなかった著者とが手を携え、地裁、高裁、最高裁と争ってユニクロの訴えを退けたあと、追撃の一冊として出版されたことにある。
これは、著者が柳井社長の挑発に乗ったかたちで、ユニクロのいくつかの販売店にアルバイトとして入職、さらにかつて働いていた労働者に取材して書いた、冷静沈着な一書である。サービス残業の恒常化などを自己体験で確認、柳井氏に叩き返した証拠であり、完璧な「勝訴」の記録である。
売り上げ額を誇るような大企業が、言論にたいして「フェイク」と声高に主張して、「スラップ」(恫喝訴訟)を構える典型的な事例である。しかし、企業は社会的存在であって、「コンプライアンス」(法令遵守)ばかりか、内外の批判を謙虚に受け止めて改革し、時代にあわせていかないかぎり生き残れない。いまの時代は内部の批判者としての労働組合が無力化し、経営者が社内民主主義を自己点検する志向が弱まっている。
企業経営は内外の批判に対応し、時代のニーズに合わせるのが賢明なはずだ。社内では箝口令を敷き、外部の批判にたいしては威丈高に高額な賠償請求を振りかざす。批判者を恫喝するのは、経営者の狭量を示して美しくない。世界から注目されているユニクロが、「巨大な柳井商店」の流儀のままでいるのか、企業内言論の自由を確立し、働くものを大事にする大らかな社風で、世界に迎え入れられるのか、その問いかけとしてこの本は貴重である。
本書を読んで意表を衝かれる想いがしたのは、年間売り上げ八七二九億円、純利益五二八億円、従業員五万二八三九人。世界に冠たる大企業が、つねにアルバイターを募集し続けるほど、人手不足が常態化している現状である。販売をささえているのは、主婦と学生、短時間勤務のアルバイターたち。五十過ぎの著者でも即決採用、翌日出勤で迎え入れられるほどに、労働者が払底している。
ユニクロは世界にむけて店舗を展開しているのだが、あたかも広大無辺の戦場をとりとめもない傭兵でカバーしていて、さほどの不安感をもっていない。それが流通業界に不案内なわたしをまず驚嘆させた。
2/3P
著者の最初の就職先は、千葉県の幕張新都心店だった。その店は六十人の従業員がおり、その構成は、二ヶ月間だけの短期アルバイト、半年ごとに契約を更新する長期アルバイト(月間百時間未満の労働)、それに準社員(月間百時間以上の労働)の三階層。「猫の手も借りたい」ほどの暮れなどの繁忙期には、販売員になりそうな客を物色し、勧誘する、というのも驚きだ。将来、社員化する、という約束で採用する「地域正社員」というものもあるが、採用基準はきびしいようだ。
「先日UNIQLOの記事が、ニュースになっていましたが、私の娘は息子と二人の母子家庭です。UNIQLOは子育て応援と言う事で、地域正社員希望で●●市の●●店に入社しましたが、一年以上が過ぎてもパートで、閑散期は週一~二日しかシフトをいれてくれませんし、当日ラインが来て出勤してと、日雇い労働者と同じです。完全なブラック企業です」
とのメールが編集部宛に送られてきたという。客が減れば出勤日を減らし、客がふえれば出勤を強制する。販売員は調達自在な資材扱いでしかない。
いま、非正規労働者は総労働人口の三八パーセント強に達する。が、非正規率はユニクロの方が、はるかに高水準である。日本有数の巨大アパレル企業が、非正規の殿堂であることが、日本人の生活不安定化を象徴している。
東京・新宿東口。二〇一二年九月に開店した、一階から三階までがユニクロ、地下三階から一階、四階から六階までがビックカメラ。開店日の朝、入り口に四千人が詰めかけたというこの「ビックロ」館のユニクロは、外国人労働者が「五割」を占める。外国人のアルバイトが多いのは、時給千円では、日本人のアルバイトがあつまらないからだ。
編集部にメールを送ってきた女性の娘は、結局「地域正社員」に到達する前に、中途退社した。人件費は削れるだけ削り、人手が足りなくなると、片っ端から動員をかけて残業を強制する。もっとも原始的な人件費削減法である。
ユニクロは製品を仕入れて販売するだけではなく、SPA(製造小売り)に大転換して成功の端緒をひらいた。一九九〇年代後半にアメリカのGAP、スペインのZARAなどの方式を採りいれるのがはやかったのだ。
「作った商品をいかに売るかではなく、売れる商品をいかに早く特定し、作るかの作業に焦点を合わせる」(前著文庫版58ページ)商法である。
企画、生産から販売までを串刺しして、ユニクロはすべてを管理。下請に生産させた商品は、自社で一〇〇パーセント引き取る。そのため、著者は前著の中国に続いて、この本の執筆のために、香港のユニクロ下請け、カンボジアの下請け工場の取材にでかけることになる。
「製造原価と販売価格の差額が、ユニクロの利益の源泉である。製造原価の大半を占めるのが人件費なのだから、人件費が安いところで作れば、利幅が大きくなる」
そのひとつの例として、横田さんが中国取材で着ていた焦げ茶色のポロシャツは、日本で買ったときは一九九〇円だった。しかし、そのポロシャツは、中国から仕入れたときは三五〇円だった、と前著に書いている。国際アパレル企業が、中国から東南アジアへ、最近ではカンボジアからバングラデシュまで移動したのは、より安い賃金をもとめてのことである。
一九六〇年代から日本企業は、韓国、シンガポールへ、さらにフィリピン、インドネシア、台湾、中国、ベトナム、カンボジア、バングラデシュへと進出した。公害企業の転進もあった。労働運動を回避する狙いもあったであろう。わたしもそれぞれの国へ日本企業を追いかけていった。たとえば、メキシコの自動車部品工場で、日本人経営者は「これからは賃金の安いべトナムへ移ります」といっていた。資本に国境はない。が、それを見直させたのが、新型コロナウイルスである。
新型コロナウイルス厄災が世界に拡がるなかで、「ジャスト・イン・タイム」の生産管理方式を前提にした、サプライ・チェーンが機能しなくなった。たとえば単価が低く、利益率も低いマスクは、人間の健康と生命の安全に必要であっても日本ではほとんど生産されていなかった。単価重視、利益第一主義、経済の外部化の脆さが明らかになった。
3/3P
ユニクロの企業経営の人間疎外を象徴している、次のような文章がある。
「レジでの精算業務を平均九十秒とすると、顧客のレジ誘導が課題となる。レジ列先頭からレジに到着するまで平均七秒をムダにしているからだ。ピークの一時間当たりの顧客数を千人とすると、千人×七秒=七千秒がムダになっている。この七千秒を有効に使えば、さらに七十七人のお客様をレジを通過させることができる」
客の誘導をまるでベルトコンベアー式に、一秒のムダもなく管理しようとする標準作業の思想は、人間と向い合う仕事ではない。人間がもつ時間をムダとして排除する、現代の工場生産の、あえていえば「トヨタ生産方式」の直輸入である。
生産と販売を機械的に直結させ、人間を介在させない疎外の方式は、サービス産業の自己否定であろう。まして衣類は人間を安らぎで包み込むもののはずだ。まもなく、膨大な商品の管理、販売はAIに代えられよう。
横田増生さんの世界的な流通現場への潜入ルポは、第三次産業での現在只今の人間疎外の報告である。もっとも人間的な関係で成立つ職場が、利益追求のために人間関係が解体されている。この矛盾を暴いて、二億二千万円の損害賠償請求と書籍回収請求の裁判を受けた。
五十年前、わたしは、自動車、鉄鋼、ガラス工場での解体された労働について、トヨタ自動車本社工場、新日鉄(現日本製鉄)八幡製鉄所、旭硝子(船橋工場)などでの体験ルポを発表したが、巨大企業三社は訴えるほど愚かではなかった。事実に謙虚、かつ報道を尊重したのだろうか。が、そのどちらにしても、労働現場の自由は、それ以降ますますちいさなものになったことを理解できる。
ユニクロの役員報酬額十億円が、二十億円に引き上げられた。社内役員は柳井正氏と二人の息子。柳井家以外のもう一人の役員に株式保有はない。柳井家一家で四十数%の株式保有。売上高に占める人件費は、十三・八%から十三・二%に下がった。柳井正氏個人の自社株配当金は、年間百億円。総資産二兆円。
ああ、「偉大なる柳井商店」はどこへいくのか? 前近代的な人間蔑視が、人間尊重の意識に変るのは、これからであろう。
--------------------------------------