
文化の日。
祝日法によると「自由と平和を愛し、文化をすすめる」とあります。
町田市民文化祭、のづた丘の上秋祭り、つくしのコミュ二ティセンターまつりなど、市内各地で文化に彩られるイベントが多数開催されています。
町田市民文学館で行われている「白洲正子のライフスタイル―暮らしの遊び展」。
この中で、紹介されている言葉の中に、次のようなものがあります。
近頃は、暮らしの中の陶器とか、美術ということが盛んにいわれている。そういう言葉もはやりすぎるとおかしくなるもので、私の経験からいえば、はじめに「暮らし」があったわけではなく、好きで集めた美術品が、ろくでもない私の暮らしを、いくらか楽しく、意義のあるものに育ててくれたといえるであろう。(「陶芸のふるさと」)
日本人の美意識は、室町・桃山期の茶道において極まったと私は思っているが、それ以前に倍ほどの時間をかけて、中国や朝鮮からの輸入品を模倣することに専念し、ついにそれらを超越することによって、「自分のもの」を発見することに成功した。このことは、一人の人間が成長していく過程によく似ている。というより、まったく同じだといっていい。したがって、美しいことを見ることは、そして使う事は、自分を豊かにすることだ。(「骨董との付き合い」)
なるほど、と思う文章です。
以前に、武相荘の牧山館長が、いいものは使わないといけない、使うことによって生活を豊かにすることなのだとおっしゃっていました。
文化をすすめ、生活を豊かにしていくために、政治が役割を発揮する時です。
「美しい骨董を見ることは、そして使うことは、自分を豊かにすることだ」──町田市民文学館「白洲正子のライフスタイル─暮らしの遊(すさ)び展」で紹介されていた言葉。
— 池川友一🏳️🌈 (@u1_ikegawa) October 27, 2019
文学館まつりは、ゆるやかな雰囲気でとても好き。 pic.twitter.com/tdqMeOGiON
にほんブログ村←日本共産党池川友一のオフィシャルブログ「都政への架け橋」を見ていただきありがとうございます。一日1回、応援クリックをお願いします。











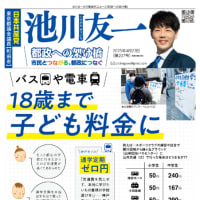


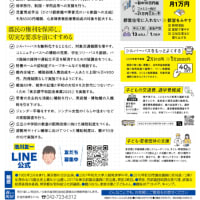
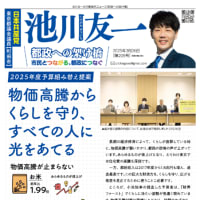



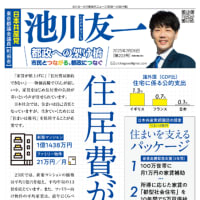
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます