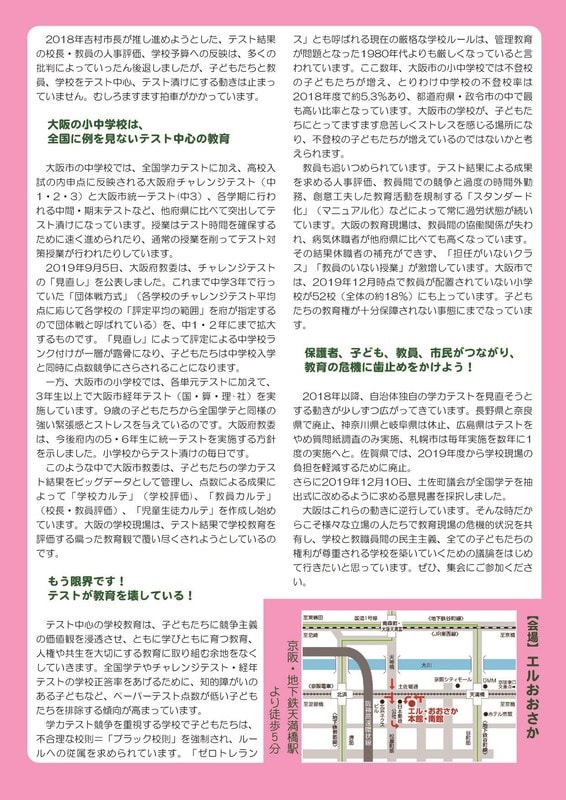子どもをテストで追いつめるな!市民の会からの緊急の呼びかけです。ぜひ、賛同をお願いします。
大阪をはじめ全国のみなさまへ
大阪府中学生統一テスト「チャレンジテスト」をご存知でしょうか。
これは、大阪維新の会府政・市政において生み出された教育施策のなかでも、過度な競争主義と格差肯定施策の典型ともいえ、深刻な問題を含んでいます。
高校入試の際の内申(5段階絶対評価)を統一テストによって学校ごとの評定平均を予め行政が決め、各学校はそれに合わせて生徒の評定をつけるという制度です(尤も説明では粉飾していますが、実質はこうです。)
「子どもをテストで追いつめるな!市民の会」は、学校(教員)の評価権に対する行政の介入であり、何より学校格差を肯定し、拡大する不公平な制度であると、その問題性を広く市民に伝える活動を行なってきました。
さて、4月7日、安倍首相は新型コロナウイルス感染症対策本部で特別措置法に基づく緊急事態宣言を発令しました。東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県が対象、実施期間は7日から5月6日までです。それを受け、感染が拡大している大阪では、4月13日吉村知事によって休業要請がなされました。
現在、大阪の学校はすべて休校中です。児童・生徒をはじめ教職員も保護者も、感染の危険を抱えながらこの未曾有の出来事に対処していくのが精一杯の状況です。
ところが、その13日に、大阪府教育委員会はホームページで、大阪府公立中学統一テスト「中3チャレンジテスト」周知リーフレットを公表しました。そこには、6月17日に中3チャレンジテストを実施するとありました。
これには驚きを禁じ得ませんでした。多くの学校関係者は、3月から2ヶ月以上の休校が続いているため、6月17日の実施はできない、またやるべきではないと考えていました。その上、5月7日以降学校が再開できるかどうかの不安も抱えています。再開できたとしても、学校で何より優先したいことは、子どもたちの命と健康を守ることです。学習はもちろんのこと、心のケアと互いの信頼関係の回復が必要です。にもかかわらず、教育委員会は休校中であることを承知しながら一方的に実施をホームページに掲載しました。
「チャレンジテスト」は全国で唯一、その結果が高校入試の内申に影響します。大阪府教育委員会はホームページにおいてもテスト対策のための「中学生チャレンジテスト復習教材」を多量にアップしています。このような状況で実施を公表することは、休校中の学力補償を歪めてしまうことにもなりかねません。そしてなにより生徒を追いつめることになります。4月16日に予定されていた全国学力テスト(全国学力・学習状況調査)はすでに中止が表明されています。
新型コロナウイルス感染症の影響下、おとなも子どもも心身ともに疲弊しています。このような状況下での実施は、生徒はもちろん教員、保護者をも追いつめることになります。どうか、6月17日の中3チャレンジテストの実施は中止してください。
「子どもをテストで追いつめるな!市民の会」は6月17日実施中止を求めるネット署名を始めました。ご賛同いただければ幸いです。
◆ネット署名は、以下からお願いします。
http://chng.it/kxRzDZhgGg
大阪をはじめ全国のみなさまへ
大阪府中学生統一テスト「チャレンジテスト」をご存知でしょうか。
これは、大阪維新の会府政・市政において生み出された教育施策のなかでも、過度な競争主義と格差肯定施策の典型ともいえ、深刻な問題を含んでいます。
高校入試の際の内申(5段階絶対評価)を統一テストによって学校ごとの評定平均を予め行政が決め、各学校はそれに合わせて生徒の評定をつけるという制度です(尤も説明では粉飾していますが、実質はこうです。)
「子どもをテストで追いつめるな!市民の会」は、学校(教員)の評価権に対する行政の介入であり、何より学校格差を肯定し、拡大する不公平な制度であると、その問題性を広く市民に伝える活動を行なってきました。
さて、4月7日、安倍首相は新型コロナウイルス感染症対策本部で特別措置法に基づく緊急事態宣言を発令しました。東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県が対象、実施期間は7日から5月6日までです。それを受け、感染が拡大している大阪では、4月13日吉村知事によって休業要請がなされました。
現在、大阪の学校はすべて休校中です。児童・生徒をはじめ教職員も保護者も、感染の危険を抱えながらこの未曾有の出来事に対処していくのが精一杯の状況です。
ところが、その13日に、大阪府教育委員会はホームページで、大阪府公立中学統一テスト「中3チャレンジテスト」周知リーフレットを公表しました。そこには、6月17日に中3チャレンジテストを実施するとありました。
これには驚きを禁じ得ませんでした。多くの学校関係者は、3月から2ヶ月以上の休校が続いているため、6月17日の実施はできない、またやるべきではないと考えていました。その上、5月7日以降学校が再開できるかどうかの不安も抱えています。再開できたとしても、学校で何より優先したいことは、子どもたちの命と健康を守ることです。学習はもちろんのこと、心のケアと互いの信頼関係の回復が必要です。にもかかわらず、教育委員会は休校中であることを承知しながら一方的に実施をホームページに掲載しました。
「チャレンジテスト」は全国で唯一、その結果が高校入試の内申に影響します。大阪府教育委員会はホームページにおいてもテスト対策のための「中学生チャレンジテスト復習教材」を多量にアップしています。このような状況で実施を公表することは、休校中の学力補償を歪めてしまうことにもなりかねません。そしてなにより生徒を追いつめることになります。4月16日に予定されていた全国学力テスト(全国学力・学習状況調査)はすでに中止が表明されています。
新型コロナウイルス感染症の影響下、おとなも子どもも心身ともに疲弊しています。このような状況下での実施は、生徒はもちろん教員、保護者をも追いつめることになります。どうか、6月17日の中3チャレンジテストの実施は中止してください。
「子どもをテストで追いつめるな!市民の会」は6月17日実施中止を求めるネット署名を始めました。ご賛同いただければ幸いです。
◆ネット署名は、以下からお願いします。
http://chng.it/kxRzDZhgGg