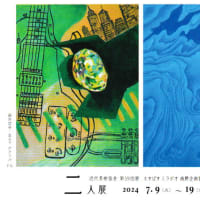今日の「田中利典師曰く」は、「蔵王権現信仰の伝播」(師のブログ 2015.2.28 付)、前年に開催された「吉野大峯世界遺産登録10周年記念連続講座 in 東京」の中の〈日本が日本のままで生きている世界遺産「吉野大峯」〉(2014.7.11)の話である。
※トップ写真は、吉野山の桜(2022.4.7 撮影)
スキー場としてよく知られている山形の「蔵王」、もとの名前は「刈田嶺(かったみね)」。ここにある刈田嶺神社の寺(神社寺、別当寺)に吉野山の蔵王権現を勧請した(招いた)。そこから山の名前も、「蔵王」と呼ばれるようになったそうだ。このように吉野山・金峯山寺の蔵王権現は全国に勧請され、伝播していった。では、全文を以下に紹介する。
「蔵王権現信仰の伝播」
吉野の権現信仰を中心とする修験信仰は、全国に伝播をいたします。蔵王権現の話をしましたが、蔵王って皆さん読めるでしょう。本当は「ぞうおう」として読みたいところなんです。ただ山形の蔵王が有名だから、みんな蔵王と読める。蔵王のスキー場のおかげなんですが、この蔵王は、山形の蔵王が本家ではなくて、吉野の蔵王が本家なんです。
吉野の蔵王権現さんを山形の刈田嶺(かったみね)神社の別当寺(神社を管理する寺)として勧請した、招いた。そこから山形、福島にまたがるあの地域に権現信仰が広がって、刈田嶺という山の名前さえ蔵王という名前に変わっていくほど広がっていった。大体物事は本家よりも分家のほうが有名になるんですが、この象徴が蔵王であります。
花笠音頭、あの祭に出てくる花の笠がありますね。あの花は何かわかりますか。あの花は山桜なんです。山桜が蔵王権現の御神木だから、花笠音頭の花は山桜なんです。行ったことはないんですが、花笠祭り、このときの山車の先頭は、蔵王権現が出てきます。写真で見ると確かにおられますね。つまり蔵王権現の祭りなんです。
明治に権現信仰が禁止されて、やはりこの山形からも権現信仰の形がなくなるんですけれども、元々は吉野の修験信仰、蔵王信仰が全国に広がった一つの典型的な証が、この山形の蔵王である。
あるいは中部には金峰山(きんぽうざん)という山が長野県と山梨県の両県にまたがり、日本百名山の一つに掲げられておりますが、この金峰山も金峯山(きんぷせん)から権現さんを持って行ってお祀りしてから、あれは金峰山と呼ぶようになったんです。
ほかにも全国にたくさんあります。熊本にやはり金峰山(きんぼうざん)がある。熊本市の人は皆知っています。熊本市を睥睨するようにある山なんですが、ここも元々は飽田山というところに蔵王権現をお迎えしてから金峰山という名前に変わった。
この山はこの3つの峯からなっているんですが、その3つの峯にある中央の土地は吉野という地名で、今もその名前は残っております。全国にこうして広がっていった。その中心は吉野大峯にあったというわけでございます。
※吉野大峯世界遺産登録10周年記念連続講座in東京 世界遺産『吉野大峯』の魅力:演題:日本が日本のままで生きている世界遺産「吉野大峯」(平成26年7月11日 東京SYDホール)講演録より
※トップ写真は、吉野山の桜(2022.4.7 撮影)
スキー場としてよく知られている山形の「蔵王」、もとの名前は「刈田嶺(かったみね)」。ここにある刈田嶺神社の寺(神社寺、別当寺)に吉野山の蔵王権現を勧請した(招いた)。そこから山の名前も、「蔵王」と呼ばれるようになったそうだ。このように吉野山・金峯山寺の蔵王権現は全国に勧請され、伝播していった。では、全文を以下に紹介する。
「蔵王権現信仰の伝播」
吉野の権現信仰を中心とする修験信仰は、全国に伝播をいたします。蔵王権現の話をしましたが、蔵王って皆さん読めるでしょう。本当は「ぞうおう」として読みたいところなんです。ただ山形の蔵王が有名だから、みんな蔵王と読める。蔵王のスキー場のおかげなんですが、この蔵王は、山形の蔵王が本家ではなくて、吉野の蔵王が本家なんです。
吉野の蔵王権現さんを山形の刈田嶺(かったみね)神社の別当寺(神社を管理する寺)として勧請した、招いた。そこから山形、福島にまたがるあの地域に権現信仰が広がって、刈田嶺という山の名前さえ蔵王という名前に変わっていくほど広がっていった。大体物事は本家よりも分家のほうが有名になるんですが、この象徴が蔵王であります。
花笠音頭、あの祭に出てくる花の笠がありますね。あの花は何かわかりますか。あの花は山桜なんです。山桜が蔵王権現の御神木だから、花笠音頭の花は山桜なんです。行ったことはないんですが、花笠祭り、このときの山車の先頭は、蔵王権現が出てきます。写真で見ると確かにおられますね。つまり蔵王権現の祭りなんです。
明治に権現信仰が禁止されて、やはりこの山形からも権現信仰の形がなくなるんですけれども、元々は吉野の修験信仰、蔵王信仰が全国に広がった一つの典型的な証が、この山形の蔵王である。
あるいは中部には金峰山(きんぽうざん)という山が長野県と山梨県の両県にまたがり、日本百名山の一つに掲げられておりますが、この金峰山も金峯山(きんぷせん)から権現さんを持って行ってお祀りしてから、あれは金峰山と呼ぶようになったんです。
ほかにも全国にたくさんあります。熊本にやはり金峰山(きんぼうざん)がある。熊本市の人は皆知っています。熊本市を睥睨するようにある山なんですが、ここも元々は飽田山というところに蔵王権現をお迎えしてから金峰山という名前に変わった。
この山はこの3つの峯からなっているんですが、その3つの峯にある中央の土地は吉野という地名で、今もその名前は残っております。全国にこうして広がっていった。その中心は吉野大峯にあったというわけでございます。
※吉野大峯世界遺産登録10周年記念連続講座in東京 世界遺産『吉野大峯』の魅力:演題:日本が日本のままで生きている世界遺産「吉野大峯」(平成26年7月11日 東京SYDホール)講演録より