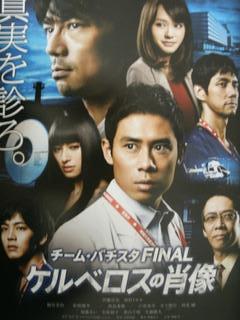国立新美術館において『中村一美展』が催されている。「絵画は何のために存するのか
絵画とは何なのか」という惹句がついているように、中村の作風は、「初期作品」の
「桑畑(櫛形町)」(1976年)や「自画像」(1977年)は正統派の作品として
描かれているものの、すぐにそのような正統派の絵画に疑問を投げかけるような抽象絵画
に転向している。
中村の作風をとりあえず大まかに理解する方法として、まず「開かれたC型」という
部屋に飾られている「宗達より - ダイアゴナル」(1986年)という茶色い描線で
描かれた小品を見て、その後に、その作品の横に据えつけられている「宗達より」
(1986年)と比べてみれば、「宗達より」は「ダイアゴナル」をベースに大胆に
色彩を施した作品であることが分かる。中村の作品は必ず「骨組」となるような
「斜行グリッド」のようなものがあり、そこに着色することで、絵画の「出自」を
暴く試みのように見える。
そのアプローチが比較的よく分かる作品は上の作品「存在の鳥 107(キジ)」
(2006年)に代表されるシリーズである。「存在の鳥」という言葉は英語で
「A Bird in its Existence」となり、正確に訳すと「その存在の中の鳥」となる。
つまり鳥が存在するのではなく、「存在」の中の鳥の在り様が描かれているのである。
とても分かりにくいが、上の作品をよく見ると、上で半分に見切れている円を鳥の目と
見なして向かって左側に大きく口を開いて右側に翼を開いている鳥の姿が見えてくる。
作品によっては左下に2、3羽の小鳥が後ろ姿で描かれている作品もあるのだが、
ようするに基本のストラクチャーは同じで、着色の仕方が違っているだけなのである。
意外なことかもしれないが、これはアンディ・ウォーホールのシルクスクリーンの
作品とアプローチとしては同じで、中村はベースとなる骨組を変えずに着色を変えることで、
絵画の成り立ちを探求しているというのが、あくまでも私の勝手な解釈である。

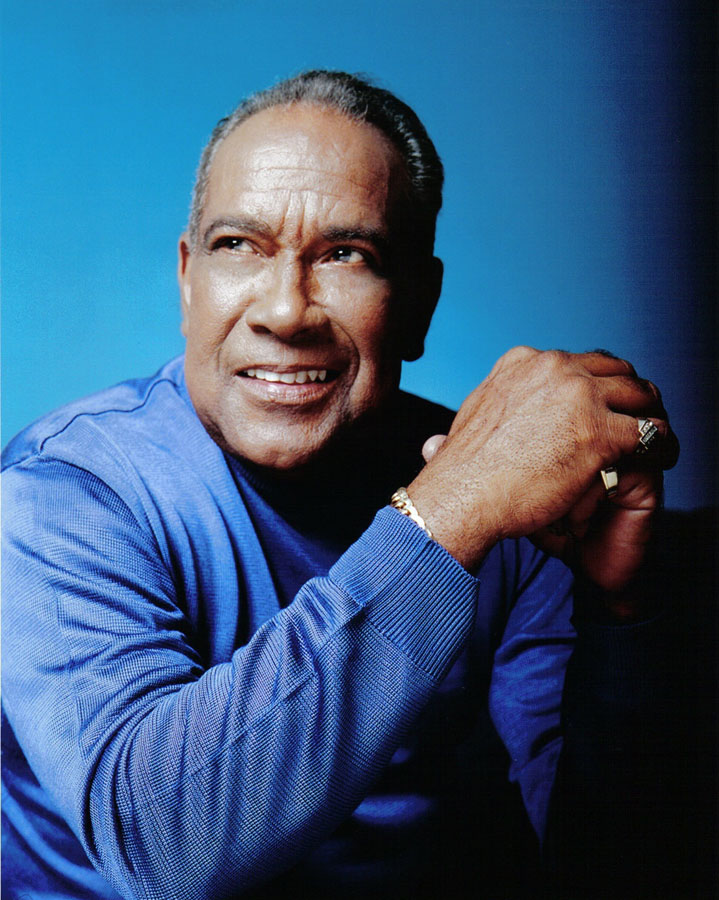
.jpg)
 普通は分からないのであるが、ホセは
普通は分からないのであるが、ホセは 普段ならばうっかりしていた
普段ならばうっかりしていた










 (Get A Horse
(Get A Horse )」と言われるのである。
)」と言われるのである。