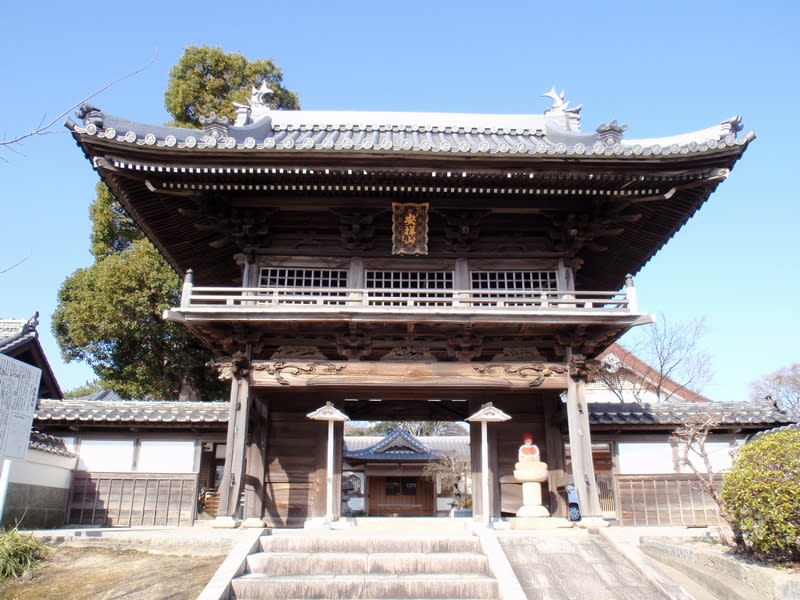こんばんわ。しょくです。
平城京遷都1300年祭に行ってきました。
花さんも奈良へ行くということで、予定より前倒しします。
下見の効果は大きかった。


 平城京遷都1300年祭を下見して来ました。
平城京遷都1300年祭を下見して来ました。

 下見で行ってきた平城京跡地。
下見で行ってきた平城京跡地。
いろいろしょく家の事情もありまして、雨の日を狙って行ってきました。
しかし、大雨すぎました。

雨が降ったおかげで、観光バス以外のお客さんは少なそうでした。
これは予定通りです。
以前行ったときは、この写真を撮り忘れたので、どうしても撮りたくて。
撮れて満足じゃ。 

雨にぬれた朱雀門(すざくもん)もまたいいですね。
ちょっと雨酷いかな?

下見時のblog

 平城京の正門 朱雀門
平城京の正門 朱雀門
今日からゆっくりと平城京遷都1300年祭を紹介していきます。

よろしくお願い致します。
P.S 花さん、東大寺の様子はこんな感じです。見てやって下さい。
締めは東大寺。
では。
BlogRankingに参加してます。







みんな応援(クリックで投票)してね。






































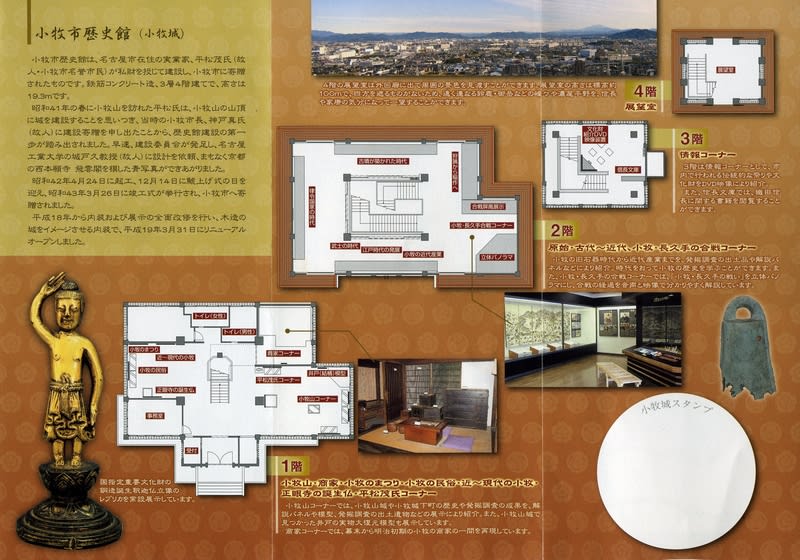















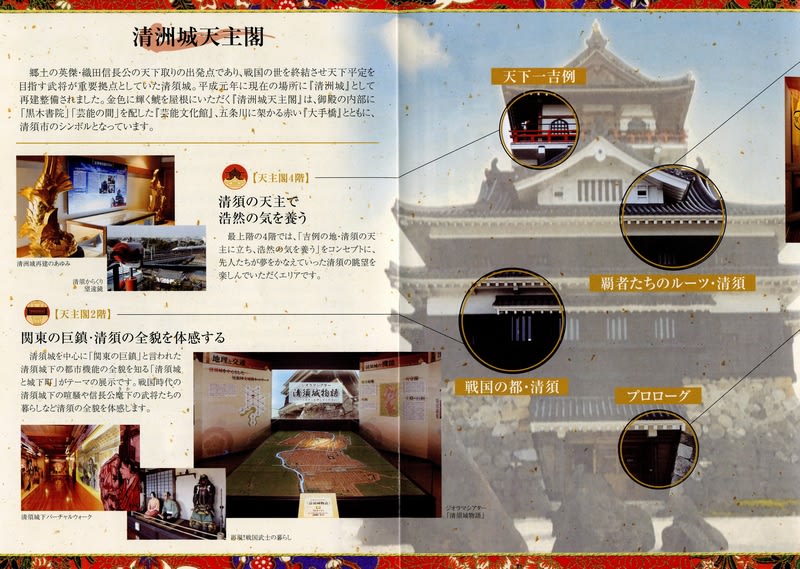



 公園の入り口です。
公園の入り口です。


































 の唐招提寺です。
の唐招提寺です。


























 しておりましたので
しておりましたので




 を撮った朱雀門。
を撮った朱雀門。


 をしようと
をしようと





 に乗ってますが、意味は分かりません。
に乗ってますが、意味は分かりません。

 に及んだが、
に及んだが、