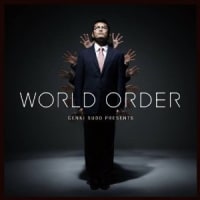>大名の墓から小判43枚、一分金117枚…愛知
>愛知県幸田町の本光寺にある深溝(ふこうず)松平家7代目当主、松平忠雄(1673~1736年)の墓所から、慶長小判を含む小判計43枚、享保・正徳などの一分金117枚、西洋製とみられるガラス製グラスなど多数の副葬品が出土したと、本光寺深溝松平家東御廟所(ひがしごびょうしょ)調査会が14日、発表した。
>大名の墓から副葬品の小判が確認された例としては、盛岡の南部家(12枚)、仙台の伊達家(10枚)などの大大名をしのぎ、過去最多とみられる。
>墓所は、地下約3.5メートルに掘られた石室(約1.5メートル四方、深さ1.3メートル)の中に六角形の木棺を納め、墓誌で蓋(ふた)をする構造。木棺の中には、遺体が座位で安置されていた。副葬品は木棺内に小判や太刀、木棺外にグラスや化粧道具、香道具、煙草(たばこ)道具、印籠(いんろう)、眼鏡などが納められていた。
>ほぼ完全な状態で出土したグラスは高さ約15センチで、製作年とみられる「1599」の文字が書かれていた。こうした西洋的な副葬品は、深溝松平家が島原藩主として長崎の監督を務めたことが関係している可能性が高いという。
・・・地方の小大名の副葬品が大大名より豪華だってのは皮肉です。徳川幕府は親藩以外の大名家には金を蓄えさせない政策をとっていたので、親戚の松平家に余裕があったのは当然かも知れませんね。
大判小判にも勿論惹かれますが(笑)、「1599」製のガラス製品なんて、その前年に秀吉死去、翌年は関ヶ原合戦の年代ですよ。ロマンが広がります。
まあ此処がエジプトじゃなくて良かった。こんなニュースが出た日には逆に日本にも墓泥棒が増殖するかな?
>愛知県幸田町の本光寺にある深溝(ふこうず)松平家7代目当主、松平忠雄(1673~1736年)の墓所から、慶長小判を含む小判計43枚、享保・正徳などの一分金117枚、西洋製とみられるガラス製グラスなど多数の副葬品が出土したと、本光寺深溝松平家東御廟所(ひがしごびょうしょ)調査会が14日、発表した。
>大名の墓から副葬品の小判が確認された例としては、盛岡の南部家(12枚)、仙台の伊達家(10枚)などの大大名をしのぎ、過去最多とみられる。
>墓所は、地下約3.5メートルに掘られた石室(約1.5メートル四方、深さ1.3メートル)の中に六角形の木棺を納め、墓誌で蓋(ふた)をする構造。木棺の中には、遺体が座位で安置されていた。副葬品は木棺内に小判や太刀、木棺外にグラスや化粧道具、香道具、煙草(たばこ)道具、印籠(いんろう)、眼鏡などが納められていた。
>ほぼ完全な状態で出土したグラスは高さ約15センチで、製作年とみられる「1599」の文字が書かれていた。こうした西洋的な副葬品は、深溝松平家が島原藩主として長崎の監督を務めたことが関係している可能性が高いという。
・・・地方の小大名の副葬品が大大名より豪華だってのは皮肉です。徳川幕府は親藩以外の大名家には金を蓄えさせない政策をとっていたので、親戚の松平家に余裕があったのは当然かも知れませんね。
大判小判にも勿論惹かれますが(笑)、「1599」製のガラス製品なんて、その前年に秀吉死去、翌年は関ヶ原合戦の年代ですよ。ロマンが広がります。
まあ此処がエジプトじゃなくて良かった。こんなニュースが出た日には逆に日本にも墓泥棒が増殖するかな?