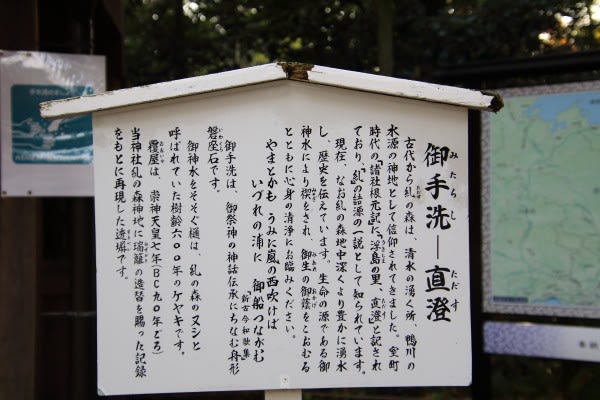7月30日「金戒光明寺(こんかいこうみょうじ)」に行ってきました。京都市左京区
黒谷町(くろだにちょう) 京阪電車「祇園四条駅」より京都市バスに乗りかえ
「岡崎道(おかざきみち)」バス停下車、歩いて10分かからんですかね。

バス停のある丸太町通りから岡崎通りにはいります。
しばらく歩くと道標がありました。右は「くろたに」。左は「ちおんいん」かな。
方角あってるかしら。 (^^♪
「高麗門(こうらいもん)」が見えてきました。09:05 参道のお店開いてるみたいです。
こちら昭和2年(1927年)創業「大前石材店」さん。キティちゃん (^^♪
はす向かい、享和元年(1801年)創業「花忠商店」さん。 きれい (^^♪
「高麗門(こうらいもん)」から入ります。
参道を歩いてと、緑がきれい。 (^^♪
「山門」が見えました。
桜と紅葉のイラスト。でも今は夏。 石段も多いみたい。 あかんがな。 (^^♪
りっぱな山門だ。 (^^)/ 山門の扁額「浄土真宗最初門」は第100代(北朝第6代)
後小松(ごこまつ)天皇の宸筆(しんぴつ)です。宸筆とは天皇が書いた文字です。
ありがたいのね。 (^^♪
「山門」応仁の乱で焼失 万延元年(1860年)再建。京都府指定有形文化財。
山門をくぐりました。 正面石段上は「御影堂(みえいどう)」本殿です。
「紫雲山(しうんさん)金戒光明寺」承安(しょうあん)5年(1175年)法然(ほう
ねん)上人が開山した浄土真宗の大本山。比叡山西塔の黒谷にならってこの地に庵を
むすんだのが始まりとされています。通称は「くろだにさん」です。 (^^♪
「勢至丸(せいしまる)」像 法然上人の幼名です。賢そうなお子さんですな。 (^^♪

では、ご本殿へ。
「鐘楼」

昭和9年(1934年)火災により焼失 昭和19年(1944年)再建。 戦争中に大変やった
ろうね。法然上人七十五歳時の座像が安置されています。
まずは身と清めてと。「花手水」 あら今日はお花ではないのね。(^^♪
あひるさんとカラフルボール。(^^♪ 中央あひるさんの頭のボツボツは仏像の「螺髪
らはつ)」をまねしてるのね。(^^)/
それではお参りを。 りっぱなご本殿です。 本殿内撮影禁止。
会津藩第9代藩主「松平容保(まつだいら かたもり)」(当時28歳)が、文久2年
(1862年)に幕府より「京都守護職」を命じられたとき、会津藩本陣となったお寺
さんです。会津藩おかかえの「新選組」の旗です。!(^^)!
では本殿廊下より撮影をと。中央のお堂は「阿弥陀堂」 右は「納骨堂」です。
京都タワーがみえます。 (^^♪

本殿横「直実鎧掛けの松」熊谷直実(くまがい なおざね)が鎧を洗いそれを掛けた
という松です。元の木は枯れてこれが三代目だとか。
〜人間五十年下天のうちをくらぶれば夢 幻のごとくなり〜 幸若舞「敦盛」のもと
になるエピソード、源平合戦「一の谷の戦い」で平清盛の甥、平敦盛(あつもり)と
の一騎打ちで知られる源氏方の武将です。その後出家して法然の弟子となり「法力
房蓮生(ほうりきぼう れんせい)」と称しました。熊谷一族の墓地もこのお寺さん
にあります。

こっちのほうが「螺髪」よく見える。 (^^♪
「極楽橋(ごくらくばし)」渡ると極楽浄土にいけるのかな。 (^^♪
ハスがきれいです。

「五劫思惟(ごこうしゆい)阿弥陀仏」さんへ。通称「アフロ阿弥陀」さんです (^^♪

「文殊塔」あそこまでいかなあかんのかな。
よかった途中にあった。
ほんにアフロだ。 螺髪もごりっぱ !(^^)!
阿弥陀仏が法蔵菩薩の時、もろもろの衆生を救わんと五劫の間ただひたすら思惟を
こらし修行され阿弥陀仏となられました。五劫思惟された時のお姿をあらわしたものだとか。
「劫」とは時の長さのことで、一劫とは約四十里立方(約160㎞)の大岩に天女が百年
に一度舞い降りて羽衣で撫でその岩がなくなるまでの長い時間です。五劫ですから
その5倍ですな。 落語「寿限無」の〜寿限無寿限無五劫の擦り切れ海砂利水魚の水行
末雲来末〜の五劫のことです。それで髪の毛そんなに伸びたのね。(^^♪
こらしんどそう。 檀家さんかな お掃除してはるし、邪魔になったらあかんし と、
登りたくない理由を探してウダウダ云いつつ おっちゃんやっぱりこれはあかん。
引き返そう (^^)/
本殿までもどってきました。
休憩処「快庵」さん。アイスでもと思いましたがまだ開いていないようで (^^♪
涼しげ アフロ阿弥陀さま (^^♪
来てみれば 森には森の 暑さかな 「加賀千代女(かがのちよじょ)」
来なくても 夏は夏です 暑いです 「麦藁帽子(ストローハット)」
(^^)/~~~