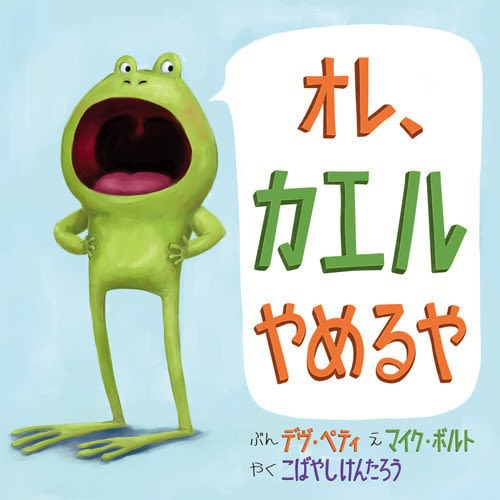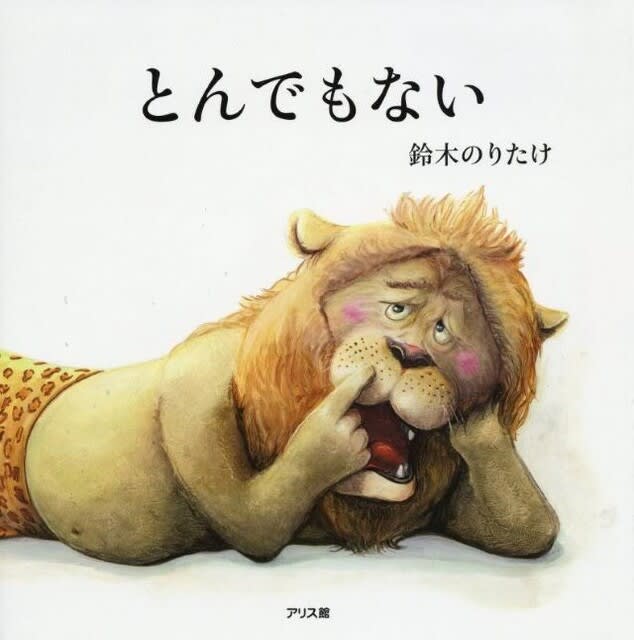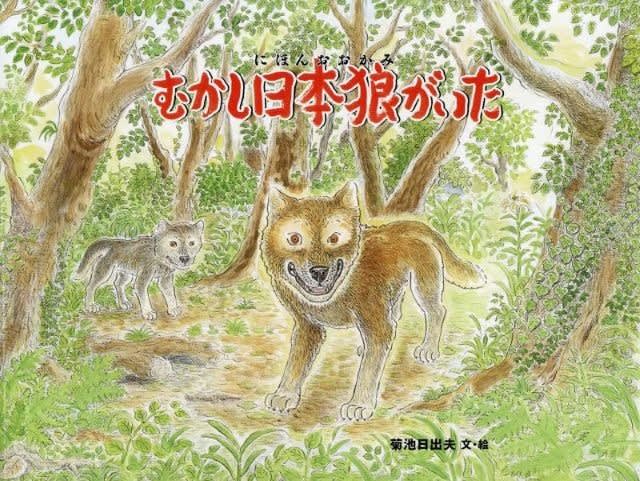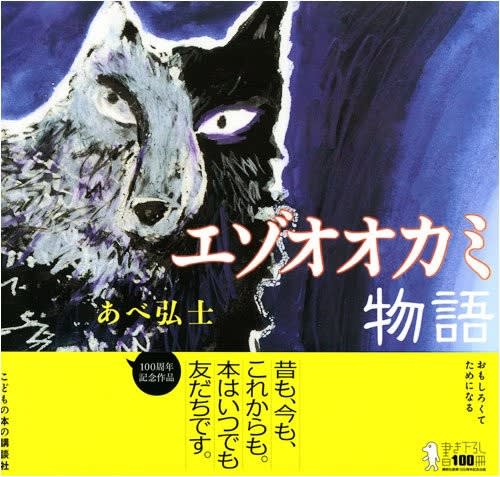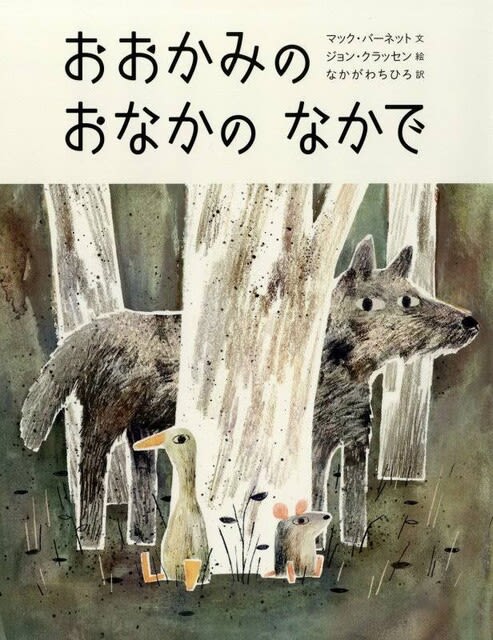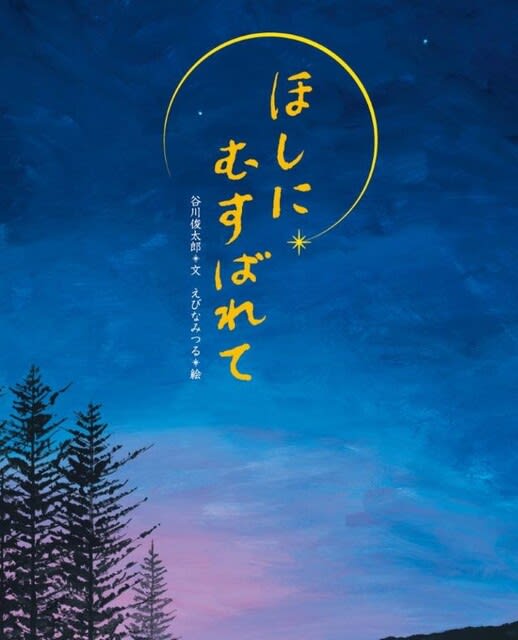「悪い」という語を広辞苑で調べる。10項目あり、「①みっともない。見た目が良くない」「②劣っている。上等でない」と続くのだが、絵本のタイトルとして『悪い本』とあれば、これはおそらく「③正しくない。好ましくない」か「⑥不吉」「⑨不快」だと思う。その「悪」さとは何か、題一つで想像をかき立てられる。
『悪い本』(宮部みゆき・作 吉田尚令・絵 岩崎書店)

出版社による「怪談えほん」シリーズの第一巻らしい。宮部みゆき以外にも文学畑の作家たちが名を連ねている。象徴性が高い文章が並んでいるイメージがある。この本の冒頭は、クマのぬいぐるみが椅子に座っている絵、そして見開きで「はじめまして わたしは 悪い本です」と記される。漢字にはルビがある。
部屋に並べられたぬいぐるみたちが、女の子を外の世界へ誘いながら、人間の「悪」の部分について語りかけてくる、といった展開。西洋画的なタッチやセピア系の色合いが、白昼夢のような雰囲気を漂わせている。読み進めると直接的な怖さが増していくというより、じわりじわりと沁みこんでくるように感じる。
どう読み語るか、考える。人形が語る形なので、極端な感情表現はないにしろ、抑揚・強弱をどの程度入れるか、無感情をねらった平坦な読みも考えられる。例えば狭い空間での少人数対象なら、それが効果的かもしれない。しかし大勢だと伝わりにくい気がする。そこで個性的な(癖のある)読み方が…と結論付けた。
『悪い本』(宮部みゆき・作 吉田尚令・絵 岩崎書店)

出版社による「怪談えほん」シリーズの第一巻らしい。宮部みゆき以外にも文学畑の作家たちが名を連ねている。象徴性が高い文章が並んでいるイメージがある。この本の冒頭は、クマのぬいぐるみが椅子に座っている絵、そして見開きで「はじめまして わたしは 悪い本です」と記される。漢字にはルビがある。
部屋に並べられたぬいぐるみたちが、女の子を外の世界へ誘いながら、人間の「悪」の部分について語りかけてくる、といった展開。西洋画的なタッチやセピア系の色合いが、白昼夢のような雰囲気を漂わせている。読み進めると直接的な怖さが増していくというより、じわりじわりと沁みこんでくるように感じる。
どう読み語るか、考える。人形が語る形なので、極端な感情表現はないにしろ、抑揚・強弱をどの程度入れるか、無感情をねらった平坦な読みも考えられる。例えば狭い空間での少人数対象なら、それが効果的かもしれない。しかし大勢だと伝わりにくい気がする。そこで個性的な(癖のある)読み方が…と結論付けた。