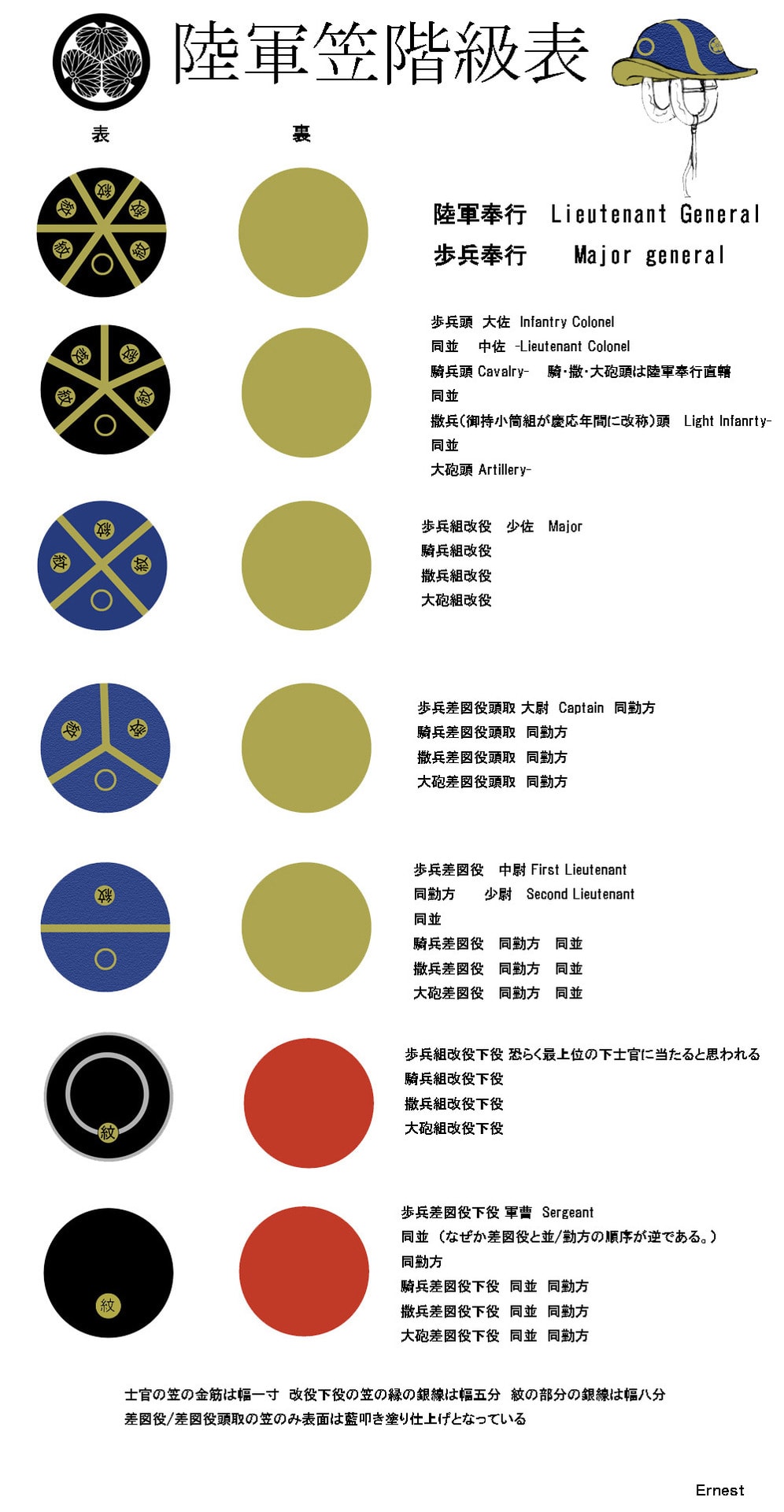そんなわけで長州藩奇兵隊隊長クラスです。ウィキにも載ってる有名な写真から軍装を再現してみました。
あれは明治二年に帰還した下関で撮影された記念写真のようで、合印の類は付いてませんでしたので、絵では付け足してみました。
スロウチハットに日本刀というのがなんともスキヤキウェスタンしてます。
チェック柄のシャツは彼らのみならず薩摩藩士の写真や土佐藩迅衝隊の肖像などにも残ってます。
けっこうカッコいいのに、映画やドラマでは必ずと言っていいほど白熊に陣羽織で登場するのがどうも…
(派手な陣羽織が狙撃の的になって危険なことは、四境戦争で奇兵隊や長州藩諸隊の活躍によって証明されました。)
同様の軍装が忍藩士の記念写真にも残っております。流行の最先端ですね。
気になるのが左の方の軍帽。円筒型の短い帽体に短い鍔、そしてバックルっぽいものがついた白っぽいバンド。謎です。せめて現存していれば。
両方とも服は体にフィットしているわけでなく、外国製の古着にありがちなサイズの大きなものを無理に着ているようです。
そういえば、箱館政府陸軍奉行の土方歳三の写真のコートもかなりでかそうです。
襟のスカーフは流行ですが、中には洋装でも首に和式の手拭いを巻いている武士などもおり、微妙なファッションセンスをうかがわせます。
刀は一本差しで腰ベルトに銃剣吊りのようなサックを付け、そこに差してるみたいです。
拳銃はスミス&ウェッソンモデル2アーミーを持っているようです。(絵のはオーバースケールぎみですが)
この拳銃は奇兵隊の生みの親である高杉晋作や彼からプレゼントされた亀山社中の坂本竜馬が所持していたことで有名です。新政府旧幕府問わず遺品や古写真に多くみられ、かなりの数が日本に入っていたようです。
足元は描きませんでしたが写真では靴ひもが見当たらず、サイドゴアの短いブーツを履いていたみたいです。
この写真の後、奇兵隊は脱退騒動を起こし、維新に貢献したはずなのに逆賊として処罰された方々も多かったようで、なんとも報われない…。