本来官僚組織は政治の決定を実現するための組織であるが、日本では政治
が官僚の決定を追認する逆転現象が生じている。
何故このような官僚主権制が出来上がってしまったのか。
明治維新で大久保利通を中心とする薩長藩閥政府が対外独立を図る為には
国家の近代化=富国強兵・殖産興業が必要であるとして「四民平等」を
唱えながら議会政治を無視し自由民権運動に対抗する天皇制専制支配を
行うための中枢的役割を担うシステムとして官僚政治を推し進めたのが
その発端である。
その後西南戦争で西郷軍が滅び大久保の没後、軍部・長州閥が伊藤、山縣
の元老政治をバックに勢力を拡大し、帝国主義、戦争への道を突き進む。
明治憲法では国家の主権は天皇にあったが、天皇は「神聖にして
侵すべからず」(3条)、即ち政治責任は負わない事になっているので天皇
の統治権は国務大臣(行政)が天皇を助言・補佐しその責任を負う(55条)
形をとっていたのである。
軍部と結びついた商工省官僚・岸伸介、運輸官僚・佐藤栄作はアメリカの
意向をくんで生き残り戦後の政治にまで大きな影響を及ぼした。
敗戦こそ国民主権・民主主義を手にする大きなチャンスで、日本を占領した
アメリカも最初は理想的な平和憲法を与え民主化の方向に舵を切っていたが
米ソ冷戦の激化、社会主義中国の出現、朝鮮戦争を背景に日本を反共の
砦とする為に、権力に対し反抗的でない生活保守の国民を造り上げる方向を
目指し日本の政治を後押しした。池田隼人の所得倍増計画など好例である。
そのような日米当局の方針により日本人は民主主義に不可欠な主権者の
理性的な意思決定能力を失い、政治への参画意識すら希薄な国民を
育ててしまった。
かくして日本は歴史的に見て一度も真の民主主義を経験しない国家になって
しまっていると言えるのではないだろうか。
日本の民主主義…(3)へ
が官僚の決定を追認する逆転現象が生じている。
何故このような官僚主権制が出来上がってしまったのか。
明治維新で大久保利通を中心とする薩長藩閥政府が対外独立を図る為には
国家の近代化=富国強兵・殖産興業が必要であるとして「四民平等」を
唱えながら議会政治を無視し自由民権運動に対抗する天皇制専制支配を
行うための中枢的役割を担うシステムとして官僚政治を推し進めたのが
その発端である。
その後西南戦争で西郷軍が滅び大久保の没後、軍部・長州閥が伊藤、山縣
の元老政治をバックに勢力を拡大し、帝国主義、戦争への道を突き進む。
明治憲法では国家の主権は天皇にあったが、天皇は「神聖にして
侵すべからず」(3条)、即ち政治責任は負わない事になっているので天皇
の統治権は国務大臣(行政)が天皇を助言・補佐しその責任を負う(55条)
形をとっていたのである。
軍部と結びついた商工省官僚・岸伸介、運輸官僚・佐藤栄作はアメリカの
意向をくんで生き残り戦後の政治にまで大きな影響を及ぼした。
敗戦こそ国民主権・民主主義を手にする大きなチャンスで、日本を占領した
アメリカも最初は理想的な平和憲法を与え民主化の方向に舵を切っていたが
米ソ冷戦の激化、社会主義中国の出現、朝鮮戦争を背景に日本を反共の
砦とする為に、権力に対し反抗的でない生活保守の国民を造り上げる方向を
目指し日本の政治を後押しした。池田隼人の所得倍増計画など好例である。
そのような日米当局の方針により日本人は民主主義に不可欠な主権者の
理性的な意思決定能力を失い、政治への参画意識すら希薄な国民を
育ててしまった。
かくして日本は歴史的に見て一度も真の民主主義を経験しない国家になって
しまっていると言えるのではないだろうか。
日本の民主主義…(3)へ




















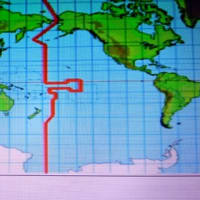





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます