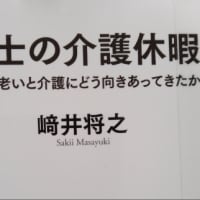塩野七生 著 「ローマ人の物語 27~28 すべての道はローマに通ず[上・下]」 新潮文庫
この巻では、古代ローマのインフラストラクチャーについて描かれています。
 古代のインフラと云えば、街道、水道、浴場にコロッセウムみたいな物を思い浮かべます。この本には、遺跡の写真が載せられていて、細々とした記事は読まなくっても、写真を見ていればいいか
古代のインフラと云えば、街道、水道、浴場にコロッセウムみたいな物を思い浮かべます。この本には、遺跡の写真が載せられていて、細々とした記事は読まなくっても、写真を見ていればいいか
紀元前312年、アッピウスが「アッピア街道」の建設を開始しています。東洋では、秦の始皇帝が「万里の長城」を作っていた時期だそうで、東洋では防御のため、ローマでは人や物の流通の為のインフラを作っていた。イタリアは三方を海に囲まれた半島だし、まだその時期、防御のための防壁よりも、軍隊がスムーズに動ける街道の方が必要だった! その時期、アッピウスは「水道」も作り始めたそうです。
原野も、人が歩けば道になる。そんな道はその頃でも、既に在ったであろうに。アッピウスは、なるべく真っ直ぐ、幅4mの車道、それを挟んで両側に幅3mの歩道を作ったそうです。石を平らに敷き詰めて、馬や馬車が疾走しても躓かないような高速道路
 排水なども考慮されていて、現在の道路に劣りません。
排水なども考慮されていて、現在の道路に劣りません。レスピーギが作った交響詩「ローマの松」の第四部に「アッピア街道の松 ♫🎶 」があります。
霧深い夜あけに、新しく昇る太陽の響きの中で、執政官の軍隊が前進していく様子を描いた曲だそうです。
これを聴くと、なんとなく「アッピア街道」が感じられます。
ローマは、こんな街道を帝国中に作ったそうです。
河にかかる橋は、太鼓橋でなく真っ直ぐの石の橋を作ったそうです。日本では江戸時代になっても木の橋だったと思うけど、西洋の石文化には驚きを感じます。
水道は、水源から基本的には土の中、それが出来ない場合は水道橋を作って引いてきたそうです。写真を見ていると、西洋のあちこちに、水道橋の遺跡が残っているのですね。
水道代は、街の中に作られた共同水槽の水を使う場合は無料、自宅まで引き込んだ場合は有料だったそうです。日本に水道が初めて引かれたのはいつだったっけ

ローマの人は、入浴が好きだったらしく、水道の先には大衆浴場を作ったそうです。美術館が内部に有ったりして、社交場だったのですね。以前、息子がイギリスに行った事があります。バースにローマ時代の浴場があったそうです。当時は、イギリスもローマ化されて、上下水道に街道、浴場に闘技場が出来ていたのですね。
この巻には、医療や教育の事も書かれています。ユリウス・カエサルは医療と教育の従事者にはローマ市民権を与え税制上の優遇をした。それにより、家庭医や家庭教師など、私的な医療・教育が発展したようです。防衛の前線には立派な軍病院があったが、ローマなど都市には、大病院はなかったとか。
ギリシャ人は、専門化した基礎科学、ローマ人は応用化学に熱心だったそうです。
医学も基礎的な研究はギリシャ人に任せて、ローマ人は家庭医とか、衛生面の充実、上下水道の充実、公衆浴場とかに力を注いだとか。
この小説のお気に入り度:★★★☆☆