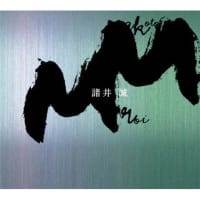「スーザン・ソンタグから始まる/ラジカルな意志の彼方へ」(光村推古書院)を読んでいて、興味深い箇所にぶち当たった。
この本は、2004年に世を去った作家/評論家、スーザン・ソンタグを追悼して、京都造形芸術大学RCES芸術編集研究センター(長いタイトル!)が開催したシンポジュウムの記録なのだが、その中にこういう件(くだり)があったのだ。これは知の連鎖に役立つ記述だった。
(浅田彰の発言)「ソンタグは旧ユーゴスラヴィア紛争の時に包囲下のサラエヴォに滞在し、本当は看護師かなにかで役に立ちたかったのを、お前は文化人だから文化をやれと言われて、サミュエル・ベケットの『ゴドーを待ちながら』の演出をした(中略)。その件で、フランスでフィリップ・ソレルスがちょっと嫌味なことを書いているんです。アメリカの高名な作家が、サラエヴォで『ゴドーを待ちながら』を演出したようだけれども、あそこではもう日常がベケット的なんだから、むしろマリヴォーの『愛の勝利』でもやったらよかったんだ、と。
この件を読んで、すぐにフィリップ・ソレルスの「神秘のモーツァルト」のことを思い出した。
「いまのところ、部屋の窓から、もし雨さえ許せば外へ食事に行こうと待機しながら、ぼくは動きのある平らな水を、ドナウ河の黄金に変えられた泥を見ている。ドナウ河、またはライン河を、モーツァルト対ワグナーの対戦と名づけることができるだろう。蛇行する動きか防波堤か、予測できない田舎か、伯爵夫人かワルキューレか、『ドン・ジョバンニ』か『パルジファル』か、『コジ・ファン・トゥッテ』か『トリスタンとイゾルデ』か、ザルツブルクかバイロイトか(中略)。ヒトラーはウィーンが好きでなかった。ヒステリックな人間たちは、ウィーンを警戒する。なぜなら、そういう人の存在が、ひとりの催眠術の専門家、おおいなる性の眠りから最初に目覚めた男によってとうとう明るみに出されてしまったのが、ほかならぬウィーンだからである。ああ、フロイトは音楽を好まなかった。レーニンもまた。ならばどうして、あのすばらしいモーツァルト演奏家であるダニエル・バレンボイムは、エルサレムでワグナーを演奏することにこだわってイスラエル人を困らせたのか?なぜ彼らにモーツァルトを、なおもモーツァルトを捧げなかったのだろう?」
この叙述は、東京1975→∞の7月16日付けコラム、バレンボイム/サイード「音楽と社会」の中のエピソードに行き着く。そこからまたサイードの「戦争とプロパガンダ(9.11を読む)の連想がはじまる。
その連想は、ついにまた、スーザン・ソンタグに戻るのである。それはこういうこと。9.11の後、私はこの出来事の「解釈」に苦しんで、(悪い癖ながら)書物の中に解答(回答)を見つけ出そうとした。サイードの「戦争とプロパガンダ」、ジャン・ボードリャールの「パワー・インフェルノ」(この本の中で語られる『あれは、ツィンタワーの自殺だ』という言葉には震えた)、ノーマン・メイラーの「なぜわれわれは戦争をしているのか」、ジャック・デリダの「フィシュ」。そして、9.11の後、パリにいながら、誰よりも早く発言したスーザン・ソンタグ。健在なり、“ラジカルな意志のスタイル”。そうなのだ!右顧左眄なしに、即座に自らの意見を提示したソンタグのスタイル。
学生時代、ソンタグの「ラジカルな意志のスタイル」にあこがれたのは、書かれている中身のことばかりではなく、ある意味、このタイトルのインパクトの強さだったように思う。
ラジカルな意志のスタイル、やっぱりいいなあ。
(写真はスーザン・ソンタグ)