[短歌味体 Ⅳ] ―吉本さんのおくりもの・戦争・敗戦期
19
人と人との関わり合う
背後には
いつも控える 影の 眼差し深く
20
硝煙漂う日差し
浴び もう
それではと一つ道に絞らるる
21
ふたたびの追い詰めらるる
首元に
ひんやり流れる死のイメージ
22
熱は氷にすぱんと
断ち切られ
真昼間に星の瞬く
23
自然のみ昨日と同じ
人はただ
取り払われた重力に浮遊す
24
あの暗雲の反復に
戦(おのの)きは
「生きた心地がしない」とさまよい歩く
註. 戦争・敗戦期 ①戦争・敗戦期の表情―柳田国男と大多数の普通の人々から 戦争や戦争期のことをいろいろと書き留められた言葉から判断すると、大多数の普通の人々は、敗戦をまず世界の崩壊感と虚脱感で受けとめたように見える。もちろん、その後にはもう戦争に関わらなくていいというような解放感が訪れたかもしれない。しかし、一方に主に知識層で、敗戦すなわち解放と捉えた人々もいた。彼らは戦後民主主義者に変身していった。これについてはここでは触れない。 柳田国男は、ほとんど全部と言っていいほどの戦争へののめり込みの状況下で、醒めて、ほんとうに大事なことは何かと黙々と思いを致し考えていたように見える。つまり、現実そのものの渦中への視線と深い歴史の大きな流れからの視線と二重化した視線を携えていたように見える。もちろん、戦時下において戦争による戦死という大多数の無名の人々の状況的な課題があれば、「先祖の話」などそれに答える文章も書いている。柳田国男の日記によると、 早朝長岡氏を訪う、不在。後向うから来て時局の迫れる話をきかせらる。夕方又電話あり、いよいよ働かねばならぬ世になりぬ。 (「炭焼日記」八月十一日『柳田國男全集32』ちくま文庫) 十二時大詔いづ、感激不止。 午後感冒、八度二分。 (「同上」八月十五日) 少し前から知り合いを通して、敗戦が近いことがわかっていたようだ。「いよいよ働かねばならぬ」というのは、当然民俗学的な研究のことだろう。敗戦を知っての思いは、簡潔に「感激不止」としかないが、辞書的な意味の「強く心に感じて、気持ちがたかぶること」と受け取るほかない。後の占領軍がもたらした民主主義を解放と捉え、それを謳歌するのとは違う。先に、柳田の視線を現実そのものの渦中への視線と深い歴史の大きな流れからの視線と二重化した視線と捉えた。戦時下でいろんな配慮や窮屈さを感じつつ研究し公表して来た柳田であるけれども、自身もまた敗戦によりその現実という片肺が崩壊した衝撃を茫然としたものとして感じたのだろうと思われる。しかし、二重の視線によって醒めていた分を考慮すると、以下のような大多数の普通の人々の感慨とは少し違っていただろうと思われる。 三月十日東京の本格的空襲初まつてから約五ヶ月の間に大中の都市殆ど灰燼に帰す。 数日前から心臓ひどく圧迫を感じて痛み、脈搏時々乱れるので、十五日は休養していた。高岡の西のおばあさんが来て、今日正午天皇陛下御自らの放送があるといふニュースがあつたと云った。門屋の廂のラヂオで拝聴する。ポツダム条約受諾のお言葉のやうに拝された。やうにといふのはラヂオ雑音多く、又お言葉が難解であつた。しかし「降伏」であることを知つた瞬間茫然自失、やがて後頭部から胸部にかけてしびれるやうな硬直、そして涙があふれた。近所の人々は充分意味汲取れぬながら、恐ろしい事実をきいたことを感知して黙つてつき立つてゐた。国民誰もが先日の露国参戦に対する御激励の御言葉をいただくものと信じてゐたのであつた。 十五日陛下の御放送を拝した直後。 太陽の光は少しもかはらず、透明に強く田と畑の面と木々とを照し、白い雲は静かに浮び、家々からは炊煙がのぼつてゐる。それなのに、戦は敗れたのだ。何の異変も自然におこらないのが信ぜられない。 (「日記」昭和二十年八月 註.旧漢字は少し直した) (『定本 伊東静雄全集』P327-P328人文書院) 柳田国男のように政府関連の知り合いもいない普通の庶民感覚としては、情報統制された大本営発表しかなく、アメリカ軍による広島・長崎に対する原爆投下、沖縄戦などの情報もうっすらとしか伝わってこなかっただろう、しかし、自らの都市の無差別爆撃を目の当たりにしていれば、なんかおかしいぞと思っていたかもしれない。敗戦という事実と目の前の自然との大きな乖離感が記されている。こうした感覚は、アジア的な社会に共通する感覚ではないだろうか。つまり、人々の感性や意識の中で人間社会も自然界も同一視するような歴史段階の感性や意識の水準のことである。若き吉本さんの場合もまた、そのようなものであった。 ②吉本さんにとっての戦争・敗戦 「アンドレイ(引用者註.トルストイ『戦争と平和』の登場人物)は仰向いて青く澄んだ空を、少し薄れた意識で見上げながら戦争も平和も人間の生死も自然に比べれば空しいと感じる。自然の変わらなさを、この場面で兵士たちの生死や将軍の野心や名誉欲とかかわりない救済として描いているトルストイ……中略……わたしもこの場面だけは『戦争と平和』のなかで鮮やかに覚えている唯一の個所だ。わたしは敗戦の日、動員先で、生きているのはおかしい、明日からどうしようと思い悩みはじめて、魚津港の海へ出て浮びながら、青い空を眺め、じぶんが生きた心地もなく悩み苦しんでいるのに今日も昨日とおなじように空が晴れているのが、不思議でならなかったのを記憶している。わたしにとってはその場面の自然の変らなさは、救済ではなく不都合に思えた。あれから半世紀ほどの年月を、このとき感じた自然への思いを解こうとして遠く戦後を旅してきたように思える。」 (「本多秋五さんの死」2001年、『吉本隆明資料集154』猫々堂) ロシアの作家トルストイの中にもこの列島と共通するアジア的な心性があるから上のような作品世界の言葉として滲み出してきたのだろう。吉本さんの「あれから半世紀ほどの年月を、このとき感じた自然への思いを解こうとして遠く戦後を旅してきたように思える」という言葉は、軽いものではない。これは一般化・抽象化すれば、戦争―敗戦が露わにした、わたしたちと共通するこの列島の住民の心性という大きな問題のことを指している。それは、自然を貪欲に開発・活用・制圧するというようなヨーロッパ的な感性や意識に対して、ヨーロッパ的なもの以前の段階の感性や意識である。それは、自然にまみれるような自然との交流という美点もあるだろうが、現実の危機的な状況に追いまくられ追い込まれたこの列島の人々の感性や意識の中で、人間社会も自然界も同一視される意識や感性がその古い層からまるで瀕死者の視線や感受のように湧き上がってくるということは、人間社会の諸課題をそのものとして直視し未来の方へ放つのではなく、その諸矛盾を自然の方に溶かし込むという時間的な退行と見なすほかないものであった。戦争期には、まるで近代そのものの総決算であるかのように、人々にそれらが湧き上がり、統合されていった。そして、このような心性の遺制は、社会関係や人間関係や思想の場面などで、今なお継続する負性を含めた課題であり続けている。 いろんな文章に吉本さん自身が書き記しているが、戦争体制に「軍国少年」として同化し死をも念頭に置いていた吉本さんにとって、この戦争・敗戦は自己の全存在を根底から揺さぶるものであった。「生きた心地もなく悩み苦しんでいる」ということは、そのことを指している。吉本さんの敗戦後の状況について、よくたどられている松崎之貞『吉本隆明はどうつくられたか』から借りてみる。 もし日本の敗戦がなかったとしたら、その後の「吉本隆明」はなかったといっていいだろう。吉本にとって敗戦の意味はそれほど重かった。 もしも、戦争、敗戦とつづく外的世界からくる強制が、わたしの「個」に断層をみち びかなかつたとしたら、わたしは、きわめて平均的な生活人のなかに全てを充たして間 然するところがなかつたであろう。(「過去についての自註) 弱年のころからきわめて精力的な読書家であり、すでに中学(府立化工)時代から詩や短文を書いていた吉本であるから、たとえ戦争・敗戦がなくとも、詩人ないし批評家として世に立ったであろうことは十分に考えられる。しかし戦争および敗戦を通過していない吉本の風貌・姿勢は、その後の実際の姿とは大きく異なったはずだ。みずから築いた思想を鋼のような文体で現実にびしびしと打ち込んでいくような立ち姿はやはり、「死ぬか生きるか」という心情をまるごと賭けて〈敗戦〉と格闘したあとでなければ出てこなかったであろう。吉本にとって昭和二十年八月十五日という日づけはそれほどの重みをもっていた。 敗戦は当時の日本人全員が体験したものではないかという、吉本固有の体験ではなかったはずだ―という論は当たらない。同じ体験をしても、それをどう受容したか、いかに超克したか、といった真の意味での〈経験〉は個々の人間によってまるで異なるからだ。 (『吉本隆明はどうつくられたか』「〈敗戦〉という落雷」松崎之貞 徳間書店 2013年) 人間の生涯において、あの時こうしていればという仮定自体は無意味のように思われるが、その仮定する行動によって人の置かれたある状況を照らし出してくれることは確かだ。吉本さん本人も仮定的に述べているが、〈敗戦〉という体験が吉本さんの生存をどれほどの衝撃で訪れ根底的に揺さぶったかということを照らし出していると見ることができる。 松崎之貞の『吉本隆明はどうつくられたか』から上に引用した部分の続きには、敗戦後の吉本さんにとっての大事な吉本さんの文章が引用されている。 わたしは、敗戦のとき、動員先からかえってくる列車のなかで、毛布や食糧を山のように背負いこんで復員してくる兵士たちと一緒になったときの気持を、いまでも忘れない。いったい、この兵士たちは何だろう?どういう心事でいるのだろう?この兵士たちは、天皇の命令一下、米軍にたいする抵抗もやめて武装を解除し、また、みずからの支配者にたいして銃をむけることもせず、嬉々として(?)食糧や衣料を山分けして故郷にかえってゆくのは何故だろう?そういうわたしにしても、動員先から虚脱して東京にかえってゆくのは何故だろう?日本人というのはいったい何という人種なんだろう。 兵士たちをさげすむことは、自分をさげすむことであった。知識人・文学者の豹変ぶりを嗤(わら)うことは、みずからが模倣した思想を嗤うことであった。どのように考えてもこの関係は循環して抜け道がなかった。このつきおとされた汚辱感のなかで、戦後が始まった。(「思想的不毛の子」『背景の記憶』所収) 「本多秋五さんの死」からの引用部分が、吉本さんの個としての内面を訪れた敗戦の衝撃の心的な情景だったすれば、ここの部分は、復員兵士や日本人という他者との関係が語られている。吉本さんは復員兵士という他者との関わり合いの中で、両者ともに逃れようもない絶対的な関係の前に立たされたように「関係は循環して抜け道がな」い、どうしようもない部分を共有する日本人だという「汚辱感」にまみれたやりきれなさが語られている。それは吉本さんの存在を根底から揺さぶるものであった。したがって、敗戦後の吉本さんの混迷する歩みはそのような場所から始まった。そうして、その後の「関係の絶対性」や「大衆の原像」、人間の生み出す幻想の三基軸(『共同幻想論』)や言葉の表現(『言語にとって美とはなにか』)、そしてそれらの後景にある心的現象(『心的現象論序説』など)というものの構造的な解明など、ものごとを根底から考え直し捉え論理化していくという吉本さんの戦後の歩みの動機は、くり返し本人によって語られてきているこれらの無惨な戦争・敗戦の体験にある。そして、その動機を支えるものとして、新たに生き直そうという強い意志と若い頃の文学の体験や実験化学者としての修練があった。 ここで、戦争・敗戦期の吉本さんにその誕生の方からの視線を加えてみると、「軍国少年」として入れ込み同化した自己の破局は、第一の不幸な誕生以後にそれを奥深く沈め周囲との関係に少しずつ馴れ馴染ませてきた表層的な意識や自己を、再び奈落に突き落とすように襲ってきた第二の根底的な不幸の体験であった。そのことに若い吉本さんがどれほど自覚的であったかはわからないとしても、若い吉本さんはその〈二重の根底的な不幸〉に「生きた心地もなく」見舞われたのである。 現在からの視線で見るならば、戦後の吉本さんの歩みは「今世紀最大の思想家」(註.1)と呼ばれるほどの、この世界のあらゆるものを根底的に問い捉えようとした人であった。しかも、論理を頭で追いかける学者と違って、自分の体験の核を何度も反芻しながら、手を動かすことによって考えながら、それにはっきりした像を与えるための論理や概念を呼び寄せるものであった。だから、『初期ノート』などに記された若い頃の考えが反芻され形を変えて何度も登場して来ることになる。 この吉本さんのような存在は、全てを情緒や印象批評に流して済ますようなこの列島社会の思想・芸術・文化などの伝統の中では、類のない存在であり貴重な存在である。そして、そのような吉本さんのその歩みと存在自体が、わたしたちへの貴重な〈おくりもの〉であるとわたしは思い感じている。そして、もうひとつ大切なことは、吉本さんの個としての内面の方に返してみれば、戦後の吉本さんの歩みは〈二重の根底的な不幸〉からの新たな〈生き直し〉の苦闘の過程に入り込んでいくことを意味していた。しかも、受けた衝撃が生存を根底から揺さぶるものであったから、吉本さんの問い・考え・捉えるという思想領域での新たな〈生き直し〉の苦闘の過程も根底的であるほかなかったのだと思われる。。 (註.1)吉本さんが、「今世紀最大の思想家」だという他者からの評価の言葉を聞いたらまず照れられたろう。そして、興味の無い勲章や叙勲のように見なし、終わられたのではないかと思う。なぜならば、吉本さんの思想は日々の細々した具体性にまで十分に及んでいるからであり、また、『カール・マルクス』の中のよく知られた言葉、つまりマルクスを偉大な思想家として引き合いに出して述べられたわたしたち人間存在についての認識の言葉がそれに対する答えになっているからである。 |













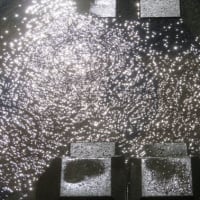






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます