短歌味体Ⅳ―吉本さんのおくりもの・おくりものということ 5-8
5
人はみな人知れず我知らず
受け継ぎ
渡すものあり無償のおくりもの
6
道端のふと拾い上げた
ひとつの石
溶けてみどりの滲み入ることあり
7
ことばに触れたどるとは
人の持つ
深さ広がり未知をも開く
8
死に急ぐ人は不幸のみか
半ば外
半ば自ら故の ああ日差し在り
(註は、ブログにて。)
註.
おくりもの
わたしたちは、ふだんおくりものをすることがある。中に立って何か口をきいてもらったなど利害の絡む場合もあれば、今ではもう薄れているのかもしれないが本家への中元や歳暮など慣習的な場合もある。現在、個人的な次元で考えれば、人類が築き上げてきた人と人とが関わり合う時の共同的な風習のひとつとして、今なお強力に、しかも靄のかかったようなあいまいさをともないつつ、― つまり、どうしてそういうことが始まり今に至っているかということはよくわからないとしても ―、おくりものは現在的な姿で生き残っている。
おくりものということを少し拡張してみる。人がこの世界のあるところに生まれ落ち、育っていくという始まりとその後の過程は、人が他者(ひと)からなんらかの「おくりもの」を物質的や精神的に受け取っていると見なすことができる。そして、人が生きて「おくりもの」を享受しながらこの世界と関わり合う中で、今度は自らが他者(ひと)や世界に対する「おくりもの」を生み出していくことになる。その「おくりもの」には、この列島では割と均質なものと見なせるかもしれないが、世界各地、地域毎の長年の慣習が色合いのように織り込まれているはずである。
このおくりものの現在の姿から、考えられるおくりものということの純粋な形態は、無償(見返りを求めない)のおくりものということである。そして、この無償ということの中には、この世界で人と人とが関わり合いながら生きていくあり方の理想形が込められている。ここで理想という意味は、その無償性は人に対して権力的や抑圧的に作用することなく、自由をもたらすからだ。それが可能な場は、現在のところ主には個と個とが関わり合う場と家族という場である。しかし、現実的には、その場には人を通して社会的な価値概念などその自由にヒビ入らせるような様々なものが混入してくる。
もちろん、今でもおくりものということには、返礼という意識がつきまとっている。しかし、親鸞の「順次生」という考え方が人の世代を継ぐ関わり方やつながりと見なすならば、人は誰でも、誰かから物心両面で何ものかを受け取り、この世界に育ち、また何ものかを次に渡していくことになる。そのことは、誰もがたどらざるを得ない普遍的な道筋であり、「わたしを生んでくれてありがとう」とか「自分のために親はこんなことしてくれた」などと取り立てて返礼の倫理を喚起される必要はないと思われる。
遠い昔、学生の頃、二段組みか三段組みの文学全集で、太宰治集の巻頭に太宰治の写真とたぶんその下に「反物をもらったから春まで生きていようと思った」というような言葉があった。これに似た言葉は、「葉」という掌編の出だしに「死のうと思っていた。ことしの正月、よそから着物を一反もらった。お年玉としてである。着物の布地は麻であった。鼠色のこまかい縞目しまめが織りこめられていた。これは夏に着る着物であろう。夏まで生きていようと思った。」と作品の言葉としてある。この言葉は、虚構性の言葉ではなく作者太宰治の思いと見てまちがいはないと思う。太宰治の日記を昔読んだことがあるが、いろんな人の世話になったり、おくりものをもらったことなどが記してあったと思う。先の巻頭の言葉にわたしは唐突な感じを持った覚えがある。普通そんな言葉を書かないだろうという感じである。しかし、太宰治にとっては真剣だったのかもしれない。人一倍落ちこみやすい心が、なにげない習慣のようなものの中に滲んでいるものに鋭敏に感応する。そしてそのおくりものに自分をこの世界につなぎとめるものを感じ取ったのかもしれない。これは言葉で言い表すのはむずかしい気がする。おそらく太宰治本人もよく意識していないような無意識的な部分が加わっているように見えるからである。大げさにいえば、生命という身体感覚レベルに近い言葉ではないか。傍目にはいい加減な人間に映るかもしれないが、さりげない言葉の中に、命を切り開こうと悪戦する太宰の一瞬が切り取られている。
でも、大人の私は自由がほしくて、パパが私のほうにぐっときてしまったらほんとうは困る。
だから、まるで恋愛を隠している男女みたいに、ふたりで暮らして行けたらいいとお互いがちょっとずつ思っていることを、ふたりともじっと黙っている。
こういう愛もあるんだな、と思う。
心配しあって、抱き合って、いっしょにいたがるだけではなくて、じっと抑えているからこそ絶対的に伝わってくるもの。ハムやお金に交換されてやってくるほんとうの気持ち。
読み取れる感受性だけが、宝なのだ。
(『みずうみ』P149 よしもと ばなな)
そして、もちろん小説というのは、作者の経験、幼年期からこれまでの人生、彼が考え、行ない、目撃し、読み、夢みてきたありとあらゆることから生れます。しかし、経験というのは、手に入れようとして入れられるものではありません-それは、贈り物です。そしてその贈り物をもらうための必要条件はただひとつ、それに対して心を開いていることです。
(『夜の言葉』「書くということ」P286 ル・グウィン 岩波現代文庫)
ここに物語の作者たちの言葉を二つ引用した。人が物語を作りそれを読者に提供するということは、現在ではもちろん経済社会のシステムを通してわたしたち読者の下に届くわけであるけれども、そのつながりの底流では作者と読者は純粋なおくりものを交わし合っているように見える。おくりものは無自覚的にも人を活かすけれども、おくりものということを十全に受け取り、渡すには、「読み取れる感受性」や「心を開いていること」が大切なことだ。
最新の画像[もっと見る]
-
 画像・詩シリーズ #15 田んぼの現在から
1週間前
画像・詩シリーズ #15 田んぼの現在から
1週間前
-
 水詩(みずし) #6
1週間前
水詩(みずし) #6
1週間前
-
 水詩(みずし) #5
1ヶ月前
水詩(みずし) #5
1ヶ月前
-
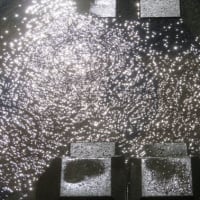 画像・詩シリーズ #14 はじまりの映像から
2ヶ月前
画像・詩シリーズ #14 はじまりの映像から
2ヶ月前
-
 農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26) 追記①、追記②
2ヶ月前
農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26) 追記①、追記②
2ヶ月前
-
 農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26) 追記①、追記②
2ヶ月前
農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26) 追記①、追記②
2ヶ月前
-
 農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26) 追記①、追記②
2ヶ月前
農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26) 追記①、追記②
2ヶ月前
-
 最近のツイートや覚書など2024年6月
2ヶ月前
最近のツイートや覚書など2024年6月
2ヶ月前
-
 最近のツイートや覚書など2024年6月
2ヶ月前
最近のツイートや覚書など2024年6月
2ヶ月前
-
 水詩(みずし) #4
3ヶ月前
水詩(みずし) #4
3ヶ月前










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます