今朝の地元紙のコラム“明窓”は、今年の雪は平年より3割多かったとの書き出し。
その中に「農業にも雪は味方する。水枯れの心配が減り、冷たい雪解け水が中国山地からゆっくり流れ出て、おいしいコメや農畜産物を育てる。水に恵まれた産地のイメージは地域ブランドの価値を高める。世界に打って出る農業を目指すには、かけがえのない地域資源となるはずだ」とも。
水とコメ、切っても切れない関係にあると思っていましたが、稲の歴史を紐解いてみると、最初はなんと!原初的な稲は焼畑で雑穀と混播され栽培されていたと。
そして、焼畑は2~3年で肥料分を消費し尽くし、新しい森が開かれ、10年程度休耕するのだとか。
その焼畑、日本ではもうないだろうと思っていましたが、まだやっているところがあるんですね~、ビックリ~!
さて、照葉樹林文化論でその稲栽培の歴史を読んでいる中で、「火耕水耨(かこうすいどう)」という聞きなれない言葉が出てきました。
中国の古い歴史書に、稲を栽培して2,3年経つと、田んぼで雑草や木の枝などを燃やし、肥料分としたことが書かれていいるのだとか。
えっつ!!おコメって、連作できるものだとばかり思っていましたが、、、
またある本には、農薬・化学肥料を使わない田んぼは、微生物や生き物の生態系が豊かになり、実りも豊かになると書かれていましたし。
???、で、外から全く何も入れない、こだわり自然栽培農家の反田さんに電話を入れて、火耕水耨では数年おきに肥料分として草や雑木を燃やすと書かれているけど、反田さんの自然栽培は何も入れないんだよね?と聞くと、、、
川の水を掛け流しているから、ミネラル分が補給されているんでしょうね、って。
弥生時代、古墳時代、奈良時代も、開墾された田んぼでも休耕田や耕作放棄田が多くあったと書かれており、そうか!今のように青々とした稲が一面に広がる光景って、昔はあり得なかったんだ!
水漏れしない畦畔を作る技術や、灌漑の技術が確立して初めて連作ができるようになったんだ!
だから、江戸時代でも、お正月でさえお米が食べられない水吞百姓が多くいた。
今朝の“明窓”ではありませんが、豊かな水を育む我が国の森、守り続けたいものです。
最新の画像[もっと見る]
-
 アニミズムの世界観
3ヶ月前
アニミズムの世界観
3ヶ月前
-
 米離れなのにコメがキロ1000円で買えない
4ヶ月前
米離れなのにコメがキロ1000円で買えない
4ヶ月前
-
 焼畑で稲を作る
4ヶ月前
焼畑で稲を作る
4ヶ月前
-
 焼畑で稲を作る
4ヶ月前
焼畑で稲を作る
4ヶ月前
-
 「菊と刀」~「恥の文化」とは?
4ヶ月前
「菊と刀」~「恥の文化」とは?
4ヶ月前
-
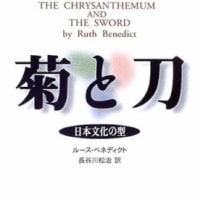 「菊と刀」~「恥の文化」とは?
4ヶ月前
「菊と刀」~「恥の文化」とは?
4ヶ月前
-
 照葉樹林文化論
4ヶ月前
照葉樹林文化論
4ヶ月前
-
 照葉樹林文化論
4ヶ月前
照葉樹林文化論
4ヶ月前
-
 ヒラリ、ハラリと
4ヶ月前
ヒラリ、ハラリと
4ヶ月前
-
 ヒラリ、ハラリと
4ヶ月前
ヒラリ、ハラリと
4ヶ月前










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます