環境省は現在、生物多様性国家戦略の改訂を進めていて、8月5日(必着)まで
パブリックコメントを募集しています。
パブリックコメントは、一般人が国に対して直接ものを言えるほぼ唯一の機会。この機会に、ちょっと関心をもってみませんか。
 生物多様性国家戦略って、そもそも何?
生物多様性国家戦略って、そもそも何?
私たち人間の社会は自然の恩恵なしには成立しません。その自然の健全さはたくさんの生物のつながりによって支えられていますが、人間活動の拡大によって地球上では平均すると1日に数種~十数種という凄まじいスピードで生物が絶滅しています。もし世界中の国々がそれぞれ、これまでどおりの開発行為を野放図に続けていけば、遠からず後戻りできない地点(ティッピング・ポイント)を過ぎて地球の生態系は加速度的に崩壊を始めてしまいます。人間がみずからの存続を危うくするほど地球環境を損なってしまう前に、何とかしなければならないと開かれたのがいわゆる「地球サミット」(1992年リオデジャネイロ)で、それを契機に環境に関する国際条約や会議などが開催されてきました。
このあたりの流れはWWFのサイトにコンパクトにまとめられているので関心のある方はこちらをご一読下さい。
生物多様性条約
生物多様性条約と日本
条約締結国として、日本も、条文に書かれている「生物多様性国家戦略」を作成しなければなりません。
生物多様性国家戦略とは、日本という国が生物多様性という分野に関して今後どのような国づくりをし、国としてどう行動していくのかをあらわしたもの。「人と自然の関わり方を見直し将来像を示すものとして作られる指針(環境省の説明会より)」です。
例えていうなら企業の社屋の正面玄関や社長室に額縁に入れて掲げられる「社是」のようなもの。「お手本」であり「作りました」と対外的にアピールするためのもので、書かれているから実現すると約束されたわけではないし、実現できなくても誰かが責任を問われるとかいうものでもありません。さらに、ここに書かれないからといってそれが否定されたということを意味するわけでもありません。
では何の意味も無いかといえばそうではなく、社是が【社風(企業風土)】を作りその会社の【独自の存在価値の源】となり、従業員の行動や思考も既定して、将来的には【会社そのものの存続をも左右する】ように、国家戦略も今の時点での【国を挙げての行動指針】(こう行動しましょう、という声がけ)なので、国民のひとりひとりが「これで良いか?」と考えてみるべきものです。
刻々と変わる国際的および国内的な情勢も反映するよう書かれているため、何だかとりとめのない感じの文書なのですが、これを読むことで、現時点で「国」が自国の自然をどう見て、将来像をどう考えようとしているかをうかがい知ることができます。
今回の改訂の目玉は2010年に開催されたCOP10名古屋(第10回の条約締約国会議)で決められた世界の新たな目標である「愛知目標」を内容に含めること、そして、国の将来像を考えるうえでの大きな衝撃となった東日本大震災の経験をふまえての内容とすることです。これに加えて、確実に訪れる人口減少も考慮に入れた国土全体の将来像の考え方を示す必要があります。
 積み残しのオオカミ問題
積み残しのオオカミ問題
ところで日本はいま、増えすぎたシカによる自然環境の改変が進み、農林業被害だけでなく、各地で植生の変化や表土の流出による生物多様性の急激な低下が進行しています。これは
日本の自然に本来備わっていた健全な頂点捕食者機能がオオカミの絶滅により失われたことに原因の一端があります。オオカミの絶滅後にその機能を補完していた狩猟者も、社会状況の変化によりその力を失ってきています。
わが国の生物多様性を将来にわたって維持回復してゆくためにはこの「自然の中に欠かせない頂点捕食者機能」を「
いったいどういう手段で存続させていくのか」を真剣に考える必要があります。
米国でイエローストーン国立公園にオオカミを再導入により復活させたのはこの機能の回復のためであり、その結果、地域の生態系の健全さが回復した実例があります。ですから日本でも、社会構造の将来予測を勘案すれば、
人の手の届きにくい奥山地域の頂点捕食者機能は再導入によりオオカミを野生復帰させて自然の遷移にゆだね、人間による狩猟やカリング(間引き)の労力は里地里山に集中させるというビジョンが、合理的かつ環境倫理上も齟齬のない将来像であると言えます。
しかし、生物多様性国家戦略には、改定案ではもちろん、従来のものにも、絶滅したオオカミのことをどう考えるかは何も触れられていません。
シカ激増による生物多様性の低下は人間の社会が変化したことに起因する
第2の危機と位置づけられており、それは今回の改訂でも残念ながら変わることはありませんでした。
実は今回の改訂にあたり、NGO・NPOの意見も聞こうという会が2011年秋から催されていて、私たちはシカ激増の根底には人間がオオカミを絶滅させた「第1の危機」があり、それがめぐりめぐっていま現われているのだという点も併記するべき、と提言しました。環境省の担当者もその点には心を動かされた様子に思えましたが結局それらしい文章がもりこまれることはありませんでした。
その理由は、改定案の33ページ、第4節「わが国の生物多様性の現状」の冒頭を見るとわかります。
国家戦略を作る際の前提となる「生物多様性評価」の検討委員会および協力した208名の専門家が評価期間と設定したのは1950年代後半から2010年まで。
そのあいだに起きた変化だけをみて、物事を考え、決めているため、それ以前に絶滅していたオオカミは最初から思考の外にある、というわけです。
でも私たちの国土の自然は、当然のことながら、1950年代に始まったものではありません。
国家戦略の中では、わが国の基本姿勢として「100年計画」と銘打ち、「過去100年の間に破壊してきた国土の生態系を、次なる100年をかけて回復する」(55ページ第3章の第2節)「自然の質を着実に向上させることを目指す」と明記しています。
明治期の野生鳥獣大乱獲時代からオオカミの絶滅を経て、戦争や山林乱開発などで荒廃していた時代。そこをスタート地点として環境の変化を評価し、そこから未来を描くことははたして妥当なのでしょうか。
日本の生態学はオオカミの絶滅後に始まったものです。生態学は【目の前の現象をそのまま記述する学問】。
わが国の生態学には、自然の調節機能としての頂点捕食者の存在への視点が欠けているとの自覚は、専門家たちにあるでしょうか。
 シカが国を動かした
シカが国を動かした
もっとも、さすがの環境省も、自然の中から中・大型哺乳類をめぐる自然調節能力が失われている現状は認めざるを得なくなったようで、今回の改訂では、2010年版には無かった記述が入りました。58ページ、国土のグランドデザインで「奥山自然地域」に関する部分です。
従来の書き方は、人の影響さえ遠ざけておけば自然は維持され何の問題もおこらないかのようなもので、いったい国は現実に起きているシカ問題をどれだけ深刻に受け止めているのかと機会あるごとにその点をパブリックコメント等で指摘してきました。
今回の改訂案では《現状》にシカ問題の深刻さが記述され、《目指す方向》にも森林生態系への影響を抑制するためにシカの保護管理を進める、とあります。そして《望ましい地域のイメージ》には「ニホンジカが生態系に悪影響を与えない生息数に維持されている。」の一文が入りました。
「奥山は、人の活動は制限するけどあとはほっておけばよい」という感覚から「維持しなければ危うい」と明言するようになった「国の認識の変化」はとても意味のあるものだと思います。
捕食者オオカミを失って自然の中で悪者扱いされねばならなくなったシカや、シカの影響で地域絶滅していく動植物の命たちが、ようやく国を動かしたというわけです。
あとは、この維持管理を将来にわたって
現実的にどう担っていくべきか、
担っていけるのか、という議論になります。その先の「生態系の健全な機能を維持回復させるための事業」であるオオカミ復活へとつながる、ほんのわずかな前進といえます。
 これからの課題
これからの課題
生物多様性の保全と持続可能な利用に向けた今後の課題(51ページ)が5つあげられていますが、その中の「科学的知見の充実」というところには「自然科学と社会科学の総合的な分析や、対策のオプションと効果などに関する研究が十分に進んでいないため、将来の選択肢を提示できていない」と書かれています。オオカミ復活の問題はまさにこれにあてはまります。今回の改訂で、
奥山で起こっている問題の深刻さをようやくみとめた国が、
それではいつ「その修復にとりかかるかどうか」という選択肢を国民に提示することができるでしょうか。
シカはたった数年でその地の生物相を変化させてしまいます。事態は全国規模で拡大・進行しており、場所によっては(大台ケ原がその典型)明らかにティッピング・ポイントを過ぎてしまい回復不能な生態系も出始めています。時間の猶予はありません。
また「いのちのつながり」の重要性をうたいながら、具体的な行動内容をよく読むと「つながり=場の形成」のみで、森林生態系の中大型哺乳類をめぐる物質循環とエネルギーフローは頂点捕食者オオカミの絶滅により途切れている、という事実についての考え方は何も示されていません。これは、「生態系サービスでつながる自然共生圏の認識」などと言って奥山で捕獲されたシカをどう人間領域に持ち出して消費・有効利用を促進するかを考えるだけでは十分な理解とはいえません。これは
自然領域での腐食連鎖という重大な科学的知見が欠けていることからくるもので、そこについての研究の推進もぜひもりこむべきではないかと思います。
この国家戦略は適宜改訂されていくものという位置づけですが、次の改訂にはさらなる進展を期待したいと思います。













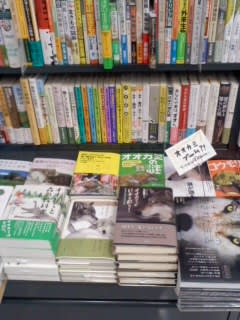

 新たに刊行されました。(正確には、児童文学を入れると7冊ですが)
新たに刊行されました。(正確には、児童文学を入れると7冊ですが)






 積み残しのオオカミ問題
積み残しのオオカミ問題 シカが国を動かした
シカが国を動かした これからの課題
これからの課題