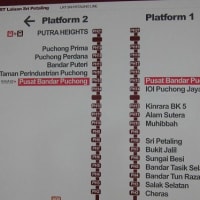海外にロングステイなさりたい方、現在すでにされている方にとって、ロングステイの一番の動機は何でしょうかね?
この種の調査はどこかの団体や一部のマスコミなどがそれぞれ何回も行って発表されてきたことでしょう。ここではそういった調査結果を基にした細かい数字を論じることはしません。
そこで今回のブログでは人々が海外ロングステイを目指す動機やきっかけ、それらの背景などを考察してみたいと思います
【自身の背景を少し語りましょう】
ことの性格上、まずイントラアジアのケースをちょっと例にしてみます。
イントラアジア (Intraasia)はその名前が示唆するように、東南アジアとりわけマレーシアを生活と滞在の基盤にしながら東南アジアに打ち込んでいます。東南アジアに打ち込むようになったのは1990年ごろからですが、それ以前の1980年代中ごろからすでに東南アジアをしばしば訪れており、かなり興味を持っていました。東南アジア言語の学習は1980年代前半にすでに手がけています。
ただ1980年代は私自身の中に中欧と東欧への強い興味と憧れがありましたので(これは1970年代後半から続いていたもの)、ヨーロッパをしばしば訪れ且つ短中期の滞在を繰り返していました。1980年代後期は中欧への移住を真剣に考え且つ現地でも試みていました。その後ある個人的理由から急遽取りやめて、日本に戻りました(1990年春)。ところがその半年後新たに雇われた会社の仕事で海外駐在の道を選び、これが以後マレーシアに住むようになるきっかけとなったわけです。
私の35年間に及ぶ長い海外旅行・滞在歴の中で、他にも北米、北部と南部のアフリカ、南太平洋諸国、南アジアなどを数多く訪れていますが、住む地つまり移住地としては考慮対象になりませんでした。
人がある地に自分から好んで住む・滞在する以上、それなりの動機が必要です。つまりイントラアジアにとってアフリカ、南太平洋諸国、北米などは中東欧と東南アジアに比べて移住したい十分な動機が足らないか”十分なる”興味がわかなかった、ということです。といっても興味がわかなかったとか嫌いだということではありませんよ、どの国や地域であれ、興味がまったくわかないなんてことはイントラアジアにはありません。例えばアフリカと南太平洋諸国は今でもまた訪れたい地です。
このようにイントラアジアがこれまでに移住地の対象に選んだのは中東欧と東南アジアの2つの地域です。この2つの地域にはそれぞれかなりの数の国がありますが、やはりどの国でもいいということにはなりません。
中東欧と東南アジアの両地域でそれぞれ多くの国々を訪れたことで、この国なら住んでみたいなあと思うようになる場合が、イントラアジアの場合は主たる動機になります。本や雑誌で読んだこことから ある Xという国に興味を持つようになることもあります。ただその場合でもやはり実際に訪れて自分で見てみることが、決定打になりますね。
20代前半から海外へ行き始めたイントラアジアですから、それ以来ある地域やある国に興味を持ったらできるだけ訪れるようにしてきました。といっても経済的と時間的制約がありますから、多少でも興味を持った国々の全てを訪れることはできませんでしたが、ざっと言って 3分の2ぐらいは訪れたでしょう。書物の上では大して興味を持たなかったまたはその国を詳しく紹介した書物を当時読んでいなかったけど、旅ルートの中で訪れたことでその国にかなり魅せられた、という場合もあります。
【非自発的選択だが多年の居住地になることもある】
イントラアジアにとってマレーシアはいわば非自発的選択の最たる例です。というのは、1990年当時東南アジアの中でイントラアジアの興味対象が大きかったのは、タイとインドネシアでした。当時イントラアジアは海外勤務の可能性を探して求職しており、そのとき就職した日本企業の海外初進出先がマレーシアであったことから、イントラアジアはまもなくマレーシアに赴任となりました。
このように、人間何がきっかけである国に住み始めるかわからないものですね。1990年ごろといえば、インターネットはまだ一般市民にはまったく普及していない頃であり、海外情報はほぼすべて活字で書かれた書籍類で探した時代です。言うまでもなく現地事情を知る人に尋ねるという直接手段と映画など撮られた映像で見るという手段はいつの時代でもありますね。
【情報が作るイメージと像が拡大しやすい現代】
時代は変わり21世紀の現在、海外情報はまさにありあふれており、且つ手間暇かけて探す気さえあれば、かなり詳細な情報も以前とは比べものにならないほど容易く入手できるようになりました。世界がインターネットで結ばれ、そのことで世界の情報とコミュニケーションに一大革命をもたらしたからです。
そんな便利社会の現代ですから、むしろ情報に振り回される人たち、情報の質に惑わされる人たち、情報選択を誤っている人たち、の多さをイントラアジアは感じます。
人々の口コミ情報を含めてマスコミが植えつける地域や国々の像、日本人一般が以前から持っている捉え方、この2つがインターネット全盛である21世紀の現代社会でも、かなり、いや依然として最大級のイメージ作りに貢献していると感じます。
例えば、昨年2010年はタイのバンコクでは反政府騒乱が発生しましたよね。まるでタイ全土が危険地帯であるかのように、マスコミは報道し、ごく一般的なニュースしか見ない人はそんな印象を持たせられていました。
あれはバンコクの中心街で起きた出来事ですが(たまたま伝統的に少なからずの日本人が居住している、働いている地区に近かった)、広大なバンコクの全ての場所や町内で不穏状況が発生していたわけではありません。南部とか東北部といったバンコクから何百キロも離れた地方の県では、市民はごく普通に生活していたのに(極めてごく一部の場所だけで小さな事件が起きたのみ)、そういうことをマスコミは強調しないし、且つ日本人を含めた他国の民は知ろうとしないのです。隣国であるマレーシアでさえ、一般市民の反応は(日本の一般市民と)同様なのです。
これはマスコミが報道する海外ニュースの常であり、マスコミ界はある国で起きた問題をその国に全体化、一般化させる体質を持っていること、一方ある国のことをよく知らない、ある国とはあまり関係ない他国の人たちは報道される中で耳目を引くこと”だけ”に捉われて、そのイメージを全体化させてしまう傾向が強いからです。
【あるべきロングステイ先像から多少乖離していても候補に入れますか?】
世界200カ国あまりもある中で、全ての国をよく調べ、自分で訪れて、そうして比較するなんてことは誰もできません。ですから海外ロングステイされる方もその選択候補を考える際に、思考の基底にはこのようなネット情報を含めた広義のマスコミが伝えるある国の像、ある地域の像、及び日本人一般が抱いているイメージが相当程度付いて回ることになります(それだけとは言いませんよ)。
海外ロングステイを選ぶ、考えるとっかかりはまずここから出発するわけです。そこで、この思考の基底にある像とイメージだけを手がかりに候補を考えていく方たちと、その像やイメージが自分の求めるそれとは多少外れているけど(まったく外れている場合は別)、とりあえず候補にも入れてみるかと思う人たち、の2種類に分かれるでしょう。
わかりやすい例で言いましょう。イスラム教とムスリムに関する像とイメージは、日本人の間で非常にステレオタイプ化しています。これは多分に、伝統的に西欧思想が日本に大きな影響を与えてきた歴史と現代でも続く漠然とした西欧志向の強さが原因ですが(二言目には、先進国ではどうのこうのと言いたがる、何々の専門家やマスコミ登場者などが溢れてますね)、加えて日本人独自の思想と文化から見てもイスラム教とムスリムは異質であることは否定できないでしょう(この面では違和感を感じても仕方がないともいえる)。
しかし現実にイスラム世界に住み、ムスリムと日常的に接すれば、埋め込まれた像とイメージに合わない面が結構あることに気がつくはずです。気がつかないとすれば、それは真摯に日常的に接していないからです。さらに一口にイスラム教とムスリムといっても、その世界はサウジアラビアからインドネシアまで、イランの堅固なシーア派教徒から中国社会で代々生きるゆるやかなムスリム民族まで、かなり多様で幅広いのです。
ですから、読者の方がロングステイ先を考える際に、その国の像やイメージが自分の求めるそれとは多少外れているけど(まったく外れている場合は別)、とりあえず候補に入れてみるかと思う人たちのグループに属されておれば、多少正確性を欠くが卑近な形容である”いわゆる穏健なイスラム国やイスラム地域”も考慮先に入れてみるのもいいのではないでしょうか。具体的にいえば、東南アジアならマレーシア、インドネシアということになりますね。
【粗探しより、興味あること、良い面に目を向けてみる】
ここから上記で述べたことにつながっていきます。
ロングステイを考慮されている、ロングステイに憧れていらっしゃる方々には、多すぎる情報に振り回される、情報の質に惑わされる、情報選択を誤らないようにしていただきたいなと、イントラアジアは願っています。
あまりにも細かな情報や各国事情の比較にこだわれば、どんな国だって粗は出てきます。好ましくない点や気に食わない面が気になることは仕方ありませんが、それに気を取られ過ぎない、むしろ良い面や自分に興味ある面にもっと目をむけてみることが、海外暮らしで楽しく過ごし、長続きさせるには大いに必要なことです。
【小さな失敗をいくつも経験しないと実際の姿が見えてきません】
イントラアジアがこのブログで時々主張していることを再度書いておきます。いくらか情報収集されたら、まずご自分の目で見て、自分の足で歩き回ってください。そうすると、いわば耳学問で得た情報との違いが感じられるはずです。読者の方にとって 数十年とはいいませんが、5年、10年と住むことになる国です。ロングステイ先を決める前に、数ヶ月程度の実滞在はすべきだと言えます。そしてその体験は最終的な選択に大いに役立つのです。
当ブログをご覧になる方の大多数は、イントラアジアと違って、20歳以降の人生の大部分を海外で過ごされた経験のない方たちのはずです。あの国、この地域というように幅広く体験されてないため、どうしてもインターネット上の口コミを含めたマス情報に頼りがちになられることはわかります。
でもせっかくイントラアジアのブログをご覧になられたのではありませんか、多すぎる情報に振り回されないために、情報の質に惑わされないために、ご自分がとりあえず興味をお持ちになった国々をまず訪れて、例え短期でも滞在してみましょう。そうすれば小さな失敗もいくつか経験することになります。小さな失敗はその後の成功につながる大事な体験ですよ。
A国での家賃はいくらで、b国での食料費はいくらといった細かな微に入る比較本などあまり意味がありません。国情が違い、条件が違うことを前提にした単なる参考にしかならないでしょう。ビジネスとしてロングステイ先の美辞麗句を並べているような代理業者や団体など後回しにしましょう。
それよりも自分の目と感性を信じ、歩いて肌で感じてみましょう。
これはイントラアジアが長年実行してきたスタイルであり、専門書の多読はその後に来ます(感性だけでは不十分ですから、きちんとした書物からの知識も必要です)。ロングステイされたい方々に、20歳以降の人生の3分の2を複数地域で多国からなる外国で過ごしてきたイントラアジア的スタイルを押し付けたいのではなく(それは不可能です)、このブログからヒントを読み取っていただけたらなあ、という私の思いを込めています。
【ロングステイ層は経済基盤があり、多様な人々からなっている】
海外ロングステイが現実にできる方たちというのは、この格差社会の中で少なくとも路頭に迷わない経済基盤をお持ちの層であるはずです。受け取っているまたは受け取ることになる年金が主たる財源であれ、ご自身の蓄えが主体であれ、少なくとも月10万円ぐらいの可処分所得を、日本で働くことなく得られるまたはそれが十分に見込める方たちです。
イントラアジアは今回日本に滞在して、つくづく現代日本の格差社会を見聞することができ、同時に自分自身が直面しています。月10数万円程度の非正規雇用手取り賃金では、とても海外ロングステイ用の資金はたまりませんね。
ですから、実際にするしないは別にして、ロングステイをまじめに考慮されている方たちは、経済基盤があるわけです。つまり数千万円のコンドミニアムを現地でぽんと購入される方から、多少程度の落ちるコンドミニアムを賃貸するのが精一杯だという方まで違いはあろうとも、ロングステイ可能層という範疇に入りますね。
この経済基盤面の違いは当然として、その他の面でも海外ロングステイされたい、憧れていらっしゃる方は一様ではないはずですよね。南欧が好きな方もあれば、東南アジアに住みたいと思われている方もいらっしゃいます。そう、まず自分の好みを第一に、しかし多少柔軟な思考で広く検討もしてください、そして実体験を経てお決めください。その結果が、スペインであろうと、オーストラリアであろうと、タイであろうと、イントラアジアは感知しないことです。
その中で東南アジアに対象国を絞りたい方々に対しては、そうであればマレーシアも考慮に入れてみませんか、マレーシアは暮らしやすい国ですよ、とお勧めの言葉をかけてみます。でも選択はあくまでもあなた自身がなさるのです。イントラアジアはマレーシアだけが絶対にお勧めとか、是非マレーシアにすべきだなどと説得したいがためにこのブログを運営しているのではありません。
イントラアジア (Intraasia)は、マレーシアはロングステイになかなか向いている国ですよと宣伝、解説する一方、日本人の海外ロングステイの多様な発展にも微力ながら貢献したいと願っています。
おしまい。
2011年年頭のブログとして、読者の皆さんにとって良い年でありますようとの願いをここに記しておきます。
今回は今年最初のブログですので、反対に年初のブログなのにという感想もあることでしょうが(笑)、いささか理屈っぽく長目の文章を載せました、全5800字。実践を理論的に整理しまたは裏付けていくことはイントラアジアが標榜しているところなので、馴染みのない読者の方は悪しからずご了承くださいね。
【ひとことご挨拶】
当ブログは昨年(2010年)大晦日に、日々の実訪問者数を累計した訪問者総数で2万人に達しました。そして今年3月でブログ開設2周年を迎えます。ごく特化したテーマを論ずる当ブログは、あちこちに登録するようなこともせず、とりたてて宣伝しているわけではないにも関わらず、Google などで検索されることで、さらに口コミ紹介もあるでしょう、当ブログを訪問される方が結構いらっしゃることをいつもうれしく思っています。主催者として多くの方に読んでいただくことは励みにもなります。
この種の調査はどこかの団体や一部のマスコミなどがそれぞれ何回も行って発表されてきたことでしょう。ここではそういった調査結果を基にした細かい数字を論じることはしません。
そこで今回のブログでは人々が海外ロングステイを目指す動機やきっかけ、それらの背景などを考察してみたいと思います
【自身の背景を少し語りましょう】
ことの性格上、まずイントラアジアのケースをちょっと例にしてみます。
イントラアジア (Intraasia)はその名前が示唆するように、東南アジアとりわけマレーシアを生活と滞在の基盤にしながら東南アジアに打ち込んでいます。東南アジアに打ち込むようになったのは1990年ごろからですが、それ以前の1980年代中ごろからすでに東南アジアをしばしば訪れており、かなり興味を持っていました。東南アジア言語の学習は1980年代前半にすでに手がけています。
ただ1980年代は私自身の中に中欧と東欧への強い興味と憧れがありましたので(これは1970年代後半から続いていたもの)、ヨーロッパをしばしば訪れ且つ短中期の滞在を繰り返していました。1980年代後期は中欧への移住を真剣に考え且つ現地でも試みていました。その後ある個人的理由から急遽取りやめて、日本に戻りました(1990年春)。ところがその半年後新たに雇われた会社の仕事で海外駐在の道を選び、これが以後マレーシアに住むようになるきっかけとなったわけです。
私の35年間に及ぶ長い海外旅行・滞在歴の中で、他にも北米、北部と南部のアフリカ、南太平洋諸国、南アジアなどを数多く訪れていますが、住む地つまり移住地としては考慮対象になりませんでした。
人がある地に自分から好んで住む・滞在する以上、それなりの動機が必要です。つまりイントラアジアにとってアフリカ、南太平洋諸国、北米などは中東欧と東南アジアに比べて移住したい十分な動機が足らないか”十分なる”興味がわかなかった、ということです。といっても興味がわかなかったとか嫌いだということではありませんよ、どの国や地域であれ、興味がまったくわかないなんてことはイントラアジアにはありません。例えばアフリカと南太平洋諸国は今でもまた訪れたい地です。
このようにイントラアジアがこれまでに移住地の対象に選んだのは中東欧と東南アジアの2つの地域です。この2つの地域にはそれぞれかなりの数の国がありますが、やはりどの国でもいいということにはなりません。
中東欧と東南アジアの両地域でそれぞれ多くの国々を訪れたことで、この国なら住んでみたいなあと思うようになる場合が、イントラアジアの場合は主たる動機になります。本や雑誌で読んだこことから ある Xという国に興味を持つようになることもあります。ただその場合でもやはり実際に訪れて自分で見てみることが、決定打になりますね。
20代前半から海外へ行き始めたイントラアジアですから、それ以来ある地域やある国に興味を持ったらできるだけ訪れるようにしてきました。といっても経済的と時間的制約がありますから、多少でも興味を持った国々の全てを訪れることはできませんでしたが、ざっと言って 3分の2ぐらいは訪れたでしょう。書物の上では大して興味を持たなかったまたはその国を詳しく紹介した書物を当時読んでいなかったけど、旅ルートの中で訪れたことでその国にかなり魅せられた、という場合もあります。
【非自発的選択だが多年の居住地になることもある】
イントラアジアにとってマレーシアはいわば非自発的選択の最たる例です。というのは、1990年当時東南アジアの中でイントラアジアの興味対象が大きかったのは、タイとインドネシアでした。当時イントラアジアは海外勤務の可能性を探して求職しており、そのとき就職した日本企業の海外初進出先がマレーシアであったことから、イントラアジアはまもなくマレーシアに赴任となりました。
このように、人間何がきっかけである国に住み始めるかわからないものですね。1990年ごろといえば、インターネットはまだ一般市民にはまったく普及していない頃であり、海外情報はほぼすべて活字で書かれた書籍類で探した時代です。言うまでもなく現地事情を知る人に尋ねるという直接手段と映画など撮られた映像で見るという手段はいつの時代でもありますね。
【情報が作るイメージと像が拡大しやすい現代】
時代は変わり21世紀の現在、海外情報はまさにありあふれており、且つ手間暇かけて探す気さえあれば、かなり詳細な情報も以前とは比べものにならないほど容易く入手できるようになりました。世界がインターネットで結ばれ、そのことで世界の情報とコミュニケーションに一大革命をもたらしたからです。
そんな便利社会の現代ですから、むしろ情報に振り回される人たち、情報の質に惑わされる人たち、情報選択を誤っている人たち、の多さをイントラアジアは感じます。
人々の口コミ情報を含めてマスコミが植えつける地域や国々の像、日本人一般が以前から持っている捉え方、この2つがインターネット全盛である21世紀の現代社会でも、かなり、いや依然として最大級のイメージ作りに貢献していると感じます。
例えば、昨年2010年はタイのバンコクでは反政府騒乱が発生しましたよね。まるでタイ全土が危険地帯であるかのように、マスコミは報道し、ごく一般的なニュースしか見ない人はそんな印象を持たせられていました。
あれはバンコクの中心街で起きた出来事ですが(たまたま伝統的に少なからずの日本人が居住している、働いている地区に近かった)、広大なバンコクの全ての場所や町内で不穏状況が発生していたわけではありません。南部とか東北部といったバンコクから何百キロも離れた地方の県では、市民はごく普通に生活していたのに(極めてごく一部の場所だけで小さな事件が起きたのみ)、そういうことをマスコミは強調しないし、且つ日本人を含めた他国の民は知ろうとしないのです。隣国であるマレーシアでさえ、一般市民の反応は(日本の一般市民と)同様なのです。
これはマスコミが報道する海外ニュースの常であり、マスコミ界はある国で起きた問題をその国に全体化、一般化させる体質を持っていること、一方ある国のことをよく知らない、ある国とはあまり関係ない他国の人たちは報道される中で耳目を引くこと”だけ”に捉われて、そのイメージを全体化させてしまう傾向が強いからです。
【あるべきロングステイ先像から多少乖離していても候補に入れますか?】
世界200カ国あまりもある中で、全ての国をよく調べ、自分で訪れて、そうして比較するなんてことは誰もできません。ですから海外ロングステイされる方もその選択候補を考える際に、思考の基底にはこのようなネット情報を含めた広義のマスコミが伝えるある国の像、ある地域の像、及び日本人一般が抱いているイメージが相当程度付いて回ることになります(それだけとは言いませんよ)。
海外ロングステイを選ぶ、考えるとっかかりはまずここから出発するわけです。そこで、この思考の基底にある像とイメージだけを手がかりに候補を考えていく方たちと、その像やイメージが自分の求めるそれとは多少外れているけど(まったく外れている場合は別)、とりあえず候補にも入れてみるかと思う人たち、の2種類に分かれるでしょう。
わかりやすい例で言いましょう。イスラム教とムスリムに関する像とイメージは、日本人の間で非常にステレオタイプ化しています。これは多分に、伝統的に西欧思想が日本に大きな影響を与えてきた歴史と現代でも続く漠然とした西欧志向の強さが原因ですが(二言目には、先進国ではどうのこうのと言いたがる、何々の専門家やマスコミ登場者などが溢れてますね)、加えて日本人独自の思想と文化から見てもイスラム教とムスリムは異質であることは否定できないでしょう(この面では違和感を感じても仕方がないともいえる)。
しかし現実にイスラム世界に住み、ムスリムと日常的に接すれば、埋め込まれた像とイメージに合わない面が結構あることに気がつくはずです。気がつかないとすれば、それは真摯に日常的に接していないからです。さらに一口にイスラム教とムスリムといっても、その世界はサウジアラビアからインドネシアまで、イランの堅固なシーア派教徒から中国社会で代々生きるゆるやかなムスリム民族まで、かなり多様で幅広いのです。
ですから、読者の方がロングステイ先を考える際に、その国の像やイメージが自分の求めるそれとは多少外れているけど(まったく外れている場合は別)、とりあえず候補に入れてみるかと思う人たちのグループに属されておれば、多少正確性を欠くが卑近な形容である”いわゆる穏健なイスラム国やイスラム地域”も考慮先に入れてみるのもいいのではないでしょうか。具体的にいえば、東南アジアならマレーシア、インドネシアということになりますね。
【粗探しより、興味あること、良い面に目を向けてみる】
ここから上記で述べたことにつながっていきます。
ロングステイを考慮されている、ロングステイに憧れていらっしゃる方々には、多すぎる情報に振り回される、情報の質に惑わされる、情報選択を誤らないようにしていただきたいなと、イントラアジアは願っています。
あまりにも細かな情報や各国事情の比較にこだわれば、どんな国だって粗は出てきます。好ましくない点や気に食わない面が気になることは仕方ありませんが、それに気を取られ過ぎない、むしろ良い面や自分に興味ある面にもっと目をむけてみることが、海外暮らしで楽しく過ごし、長続きさせるには大いに必要なことです。
【小さな失敗をいくつも経験しないと実際の姿が見えてきません】
イントラアジアがこのブログで時々主張していることを再度書いておきます。いくらか情報収集されたら、まずご自分の目で見て、自分の足で歩き回ってください。そうすると、いわば耳学問で得た情報との違いが感じられるはずです。読者の方にとって 数十年とはいいませんが、5年、10年と住むことになる国です。ロングステイ先を決める前に、数ヶ月程度の実滞在はすべきだと言えます。そしてその体験は最終的な選択に大いに役立つのです。
当ブログをご覧になる方の大多数は、イントラアジアと違って、20歳以降の人生の大部分を海外で過ごされた経験のない方たちのはずです。あの国、この地域というように幅広く体験されてないため、どうしてもインターネット上の口コミを含めたマス情報に頼りがちになられることはわかります。
でもせっかくイントラアジアのブログをご覧になられたのではありませんか、多すぎる情報に振り回されないために、情報の質に惑わされないために、ご自分がとりあえず興味をお持ちになった国々をまず訪れて、例え短期でも滞在してみましょう。そうすれば小さな失敗もいくつか経験することになります。小さな失敗はその後の成功につながる大事な体験ですよ。
A国での家賃はいくらで、b国での食料費はいくらといった細かな微に入る比較本などあまり意味がありません。国情が違い、条件が違うことを前提にした単なる参考にしかならないでしょう。ビジネスとしてロングステイ先の美辞麗句を並べているような代理業者や団体など後回しにしましょう。
それよりも自分の目と感性を信じ、歩いて肌で感じてみましょう。
これはイントラアジアが長年実行してきたスタイルであり、専門書の多読はその後に来ます(感性だけでは不十分ですから、きちんとした書物からの知識も必要です)。ロングステイされたい方々に、20歳以降の人生の3分の2を複数地域で多国からなる外国で過ごしてきたイントラアジア的スタイルを押し付けたいのではなく(それは不可能です)、このブログからヒントを読み取っていただけたらなあ、という私の思いを込めています。
【ロングステイ層は経済基盤があり、多様な人々からなっている】
海外ロングステイが現実にできる方たちというのは、この格差社会の中で少なくとも路頭に迷わない経済基盤をお持ちの層であるはずです。受け取っているまたは受け取ることになる年金が主たる財源であれ、ご自身の蓄えが主体であれ、少なくとも月10万円ぐらいの可処分所得を、日本で働くことなく得られるまたはそれが十分に見込める方たちです。
イントラアジアは今回日本に滞在して、つくづく現代日本の格差社会を見聞することができ、同時に自分自身が直面しています。月10数万円程度の非正規雇用手取り賃金では、とても海外ロングステイ用の資金はたまりませんね。
ですから、実際にするしないは別にして、ロングステイをまじめに考慮されている方たちは、経済基盤があるわけです。つまり数千万円のコンドミニアムを現地でぽんと購入される方から、多少程度の落ちるコンドミニアムを賃貸するのが精一杯だという方まで違いはあろうとも、ロングステイ可能層という範疇に入りますね。
この経済基盤面の違いは当然として、その他の面でも海外ロングステイされたい、憧れていらっしゃる方は一様ではないはずですよね。南欧が好きな方もあれば、東南アジアに住みたいと思われている方もいらっしゃいます。そう、まず自分の好みを第一に、しかし多少柔軟な思考で広く検討もしてください、そして実体験を経てお決めください。その結果が、スペインであろうと、オーストラリアであろうと、タイであろうと、イントラアジアは感知しないことです。
その中で東南アジアに対象国を絞りたい方々に対しては、そうであればマレーシアも考慮に入れてみませんか、マレーシアは暮らしやすい国ですよ、とお勧めの言葉をかけてみます。でも選択はあくまでもあなた自身がなさるのです。イントラアジアはマレーシアだけが絶対にお勧めとか、是非マレーシアにすべきだなどと説得したいがためにこのブログを運営しているのではありません。
イントラアジア (Intraasia)は、マレーシアはロングステイになかなか向いている国ですよと宣伝、解説する一方、日本人の海外ロングステイの多様な発展にも微力ながら貢献したいと願っています。
おしまい。
2011年年頭のブログとして、読者の皆さんにとって良い年でありますようとの願いをここに記しておきます。
今回は今年最初のブログですので、反対に年初のブログなのにという感想もあることでしょうが(笑)、いささか理屈っぽく長目の文章を載せました、全5800字。実践を理論的に整理しまたは裏付けていくことはイントラアジアが標榜しているところなので、馴染みのない読者の方は悪しからずご了承くださいね。
【ひとことご挨拶】
当ブログは昨年(2010年)大晦日に、日々の実訪問者数を累計した訪問者総数で2万人に達しました。そして今年3月でブログ開設2周年を迎えます。ごく特化したテーマを論ずる当ブログは、あちこちに登録するようなこともせず、とりたてて宣伝しているわけではないにも関わらず、Google などで検索されることで、さらに口コミ紹介もあるでしょう、当ブログを訪問される方が結構いらっしゃることをいつもうれしく思っています。主催者として多くの方に読んでいただくことは励みにもなります。