最近このブログでは、忌野清志郎のことをたびたび書いています。
私はRCサクセションをリアルタイムで聴いていた世代ではありませんが、そうであっても、清志郎の歌声は普通に生活していれば耳に入ってきますし、一度耳にすれば忘れないわけです。私が清志郎を本格的に聴くようになったのはソロアーティストとしてで、そこからRCやその後に彼が作ったいくつかのバンドにいきました。
今回は、清志郎ヘビーローテーションの延長として、そうしたバンドの一つである、ザ・タイマーズについて書こうと思います。
一応、覆面バンドということになっているのですが、清志郎であることは誰でもわかりますし、タイマーズでカバーした「デイドリーム・ビリーバー」をソロのライブでやったりもしているので、覆面バンドというのは有名無実です。
タイマーズにいたるまでには、アルバム『COVERS』発表をめぐる騒動があり、また、「FM東京事件」など、とにかくタイマーズの活動には清志郎のロックなところが炸裂しています。清志郎は、日本では実に稀有な、リアルをみせてくれるロックンローラーだったのです。しかも、こんなことをやっておいて、清志郎は業界から消えることもなく、その後NHKの番組にもふつうに出てますし、「デイドリーム・ビリーバー」は今でもコンビニのCMソングとして使われています。まさに、日本ロック界のレジェンド、GODとしかいいようがありません。
そんな清志郎がタイマーズとしてリリースした3枚目のアルバム『不死身のタイマーズ』に収録されているのが、「あこがれの北朝鮮」です。
発表は、1995年。
94年の朝鮮半島危機も記憶に新しいころに出されたこの歌で、Zerryこと忌野清志郎はこう歌っています。
北朝鮮で遊ぼう
楽しい北朝鮮
北朝鮮は、いい国
みんなの北朝鮮
キム・イルソン
キム・ジョンイル
キム・キム・キム・ヒョンヒ
おーい! キムって呼べば
皆が振り向く
北朝鮮で遊ぼう
あこがれの北朝鮮
楽しい北朝鮮
北朝鮮は、いい国
みんなの北朝鮮
キム・イルソン
キム・ジョンイル
キム・キム・キム・ヒョンヒ
おーい! キムって呼べば
皆が振り向く
北朝鮮で遊ぼう
あこがれの北朝鮮
ふざけたような歌と思われるかもしれませんが、ふざけているだけではありません。
また、北朝鮮が拉致を認めた後にはさらに不穏当な歌詞に変えて歌ったりもしていましたが、北朝鮮をコケにするだけの歌でもありません。
実はこの歌は、ラブ&ピース的な価値観に根差しているのです。
もともと清志郎は、若いころにはピーター、ポール&マリーなんかを聴いていて、60年代ラブ&ピース的なフォークを一つのルーツとして持っています。RCサクセションも、当初は3人組のフォークグループでした。それが、70年代半ばごろから、KISSをイメージしたような5人編成のハードロックバンドに生まれ変わったのです。
しかし、RCで『COVERS』を出したころぐらいから、清志郎はラブ&ピース的な傾向をみせはじめます。
もっとも、PPMのような感じではなく、パンクの体験を経てアナーキズムの色で染められたものではありますが……
そして、そんなアナーキーなラブ&ピースをもっとも端的に見て取れるのが、「あこがれの北朝鮮」なのです。
ふざけたような歌でありながらも、最後はこんなふうにしめくくられます。
いつかきっと皆
仲良くなれる
いつかきっとそんな
世界が来るさ
差別も偏見も
国境も無くなるさ
仲良くなれる
いつかきっとそんな
世界が来るさ
差別も偏見も
国境も無くなるさ
これが、清志郎ふうの、ひねりのあるラブ&ピースなんです。
あまり正面から愛や平和を口にするのは抵抗があるので、こんな表現にならざるをえないということでしょう。
この歌が発表されたのは今からもう20年以上も前ですが、残念ながら、清志郎のいうような世界はやってきていません。
この手の歌について書く時にはいつも同じようなことをいってますが……
北朝鮮をめぐる情勢も、先が見通せません。こんなときだからこそ、ただ強硬姿勢をエスカレートさせていくばかりでなく、ユーモアも交えたしなやかな姿勢が必要なんじゃないかと思いました。












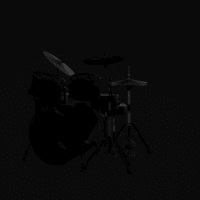








たしかに「悲惨な戦争」や「500マイル」なんか、彼の声で歌ってもサマになる感じですね。
人は「単なる理想主義、希望的観測」だろ、とかケチをつけるけど、やっぱり理想を先にかかげないといけないよね。
「坊ちゃん」と呼ばれようが、青二才扱いされようが愛や誠実さを訴え続けることは必要ですね。
理想を先にかかげるというのは重要なことだと思います。
世界史は、「理想」「夢想」とされたことが実現してきた過程であり、「現実はこうだから」といって理想を放棄すると、結局は時代に取り残されることになります。
「現実」路線をとった結果、むしろ時代に取り残される……それは、近代日本が繰り返してきた過ちであり、今もそうなりつつあるような気がしてなりません。