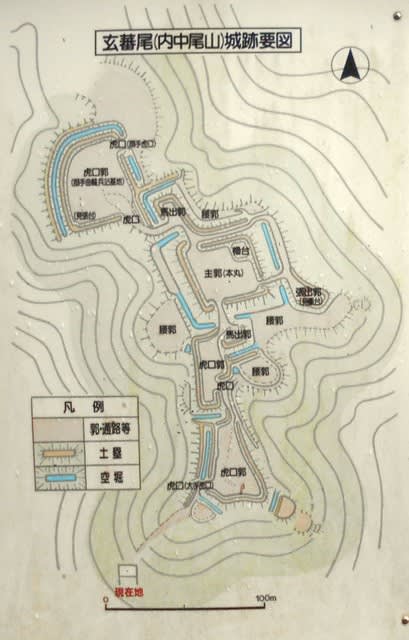先日、福井県の白山平泉寺を訪れました。
というのは、私の所属する「若越城の会」の学習会でこの「白山平泉寺」をテーマに学習会がもたれ、関心を持ったからです。
白山平泉寺はお寺か神社か
はじめ平泉寺というくらいなので、ここにはお寺があると思っていました。しかし、学習会でよくよく聞いてみると、ここには白山神社という神社があるということでした。では、平泉寺とはどういうことか、戦国時代までここに平泉寺というお寺があり、そのお寺は京都の比叡山延暦寺につながるお寺として絶大な勢力を誇っていたそうです。パンフレットには、「一帯は、最盛期の戦国時代には8000人もの僧兵がいたと伝えられ、当時の日本では最大規模の宗教都市となり繁栄します。しかし、天正2年(1574)に越前一向一揆勢に攻められ、全山焼失しました。」と書かれています。

中宮白山平泉寺境内図(江戸時代に描かれた中世の白山平泉寺の境内図)
戦国時代の宗教都市といえば、大坂(石山)本願寺が思い浮かびますが、福井県にもそういった宗教都市があったというのは驚きでした。
さて平泉寺は、現在発掘調査が行われており、特に南谷の方で僧房の跡が発見され石畳の道や坊舎の跡の調査が行われています。それを見ることを目的にして見学をしました。

平泉寺案内図(青色は、私が追加しました)
「まほろば館」の近くの駐車場に車を停め、一の鳥居から順に見学しました。
続く
というのは、私の所属する「若越城の会」の学習会でこの「白山平泉寺」をテーマに学習会がもたれ、関心を持ったからです。
白山平泉寺はお寺か神社か
はじめ平泉寺というくらいなので、ここにはお寺があると思っていました。しかし、学習会でよくよく聞いてみると、ここには白山神社という神社があるということでした。では、平泉寺とはどういうことか、戦国時代までここに平泉寺というお寺があり、そのお寺は京都の比叡山延暦寺につながるお寺として絶大な勢力を誇っていたそうです。パンフレットには、「一帯は、最盛期の戦国時代には8000人もの僧兵がいたと伝えられ、当時の日本では最大規模の宗教都市となり繁栄します。しかし、天正2年(1574)に越前一向一揆勢に攻められ、全山焼失しました。」と書かれています。

中宮白山平泉寺境内図(江戸時代に描かれた中世の白山平泉寺の境内図)
戦国時代の宗教都市といえば、大坂(石山)本願寺が思い浮かびますが、福井県にもそういった宗教都市があったというのは驚きでした。
さて平泉寺は、現在発掘調査が行われており、特に南谷の方で僧房の跡が発見され石畳の道や坊舎の跡の調査が行われています。それを見ることを目的にして見学をしました。

平泉寺案内図(青色は、私が追加しました)
「まほろば館」の近くの駐車場に車を停め、一の鳥居から順に見学しました。
続く