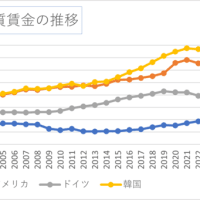【はじめに】
小泉進次郎大臣は、米の店頭価格を下げる為に奔走している様ですが、近年の法律の改正で「米の価格を下げるのは政府の役割では無い」事になっています。 この基本方針には全く触れないで、「当面の価格を下げれば良い」と言うスタンスです。 稲作の喫緊の課題は、「農家の収入が少なく→→息子/娘が跡を継がないケースが増え→→親父さんが高齢化して→→政府が、対策を講じないと→→日本の農業は壊滅的な状況になる!」ことです。
備蓄米を安値で放出し→→5kgで2,000円台の米が→→店頭に並ぶと→→直ぐに売り切れるそうです。 「現在、主食米が不足している」とは思えません。 流通経路に、「5kgで2,000円台」では赤字になる米が沢山残っていると想像します。 小泉大臣は、米屋を倒産させようとしているのか?
「令和の米騒動を経験したので、食品の安定供給の重要性について、国民の多くの方が認識された」と私は思っています。 私が、このシリーズのブログを書いているのは、『食の安全保障』と『永続可能な農林水産業』に関する、私の持論を近い将来書きたいと考えており、「私の主張を御理解頂く為には農業についの知識を広げて頂く必要が有る」と思うからです。
【農地の面積の単位】
日本では、農地や山林の面積には公式には、メートル法の『平方メートル(m2)』や『アール(a)』が使用されますが、一般に『町・反・畝・歩』も使用されています。 宅地や家屋の場合、尺貫法の単位は『坪・合・勺』ですが、『合・勺』は殆ど使用されません。
アメリカとイギリスは今でも、ヤードポンド法の面積単位が採用されていますが、その他の国ではメートル法に切り替わっています。
(注記) 『合』と『勺』は、本来は体積の単位です。 面積の単位の合と勺は、凄く小さな面積なので、一般には殆ど使用されていません。
・・・ 尺貫法の面積 ・・・
① 町(ちょう)=10反 ≒ 9,917平方メートル(m2)
② 反(たん)=10畝 ≒992平方メートル≒10a
③ 畝(せ) =30坪 ≒99平方メートル
④ 坪(つぼ)=10合 ≒3.3平方メートル
⑤ 合(ごう)=10勺 ≒0.33平方メートル
⑥ 勺(しゃく)=0.1合 ≒0.033平方メートル
⑦ 歩(ほ)=6尺✕6尺=1坪≒3.3平方メートル
(注記) 『歩』は条里制で使用された単位で、現在は『坪』が使用されています。
・・・ メートル法の面積 ・・・
❶ 平方キロメートル(km2)=100ha≒100町
❷ ヘクタール(ha)=100a≒1町
❸ アール(a)=100m2≒1畝
❹ 平方メートル(m2)
(注記 :国際単位系) 国際的な条約で決めた単位系を『国際単位系(SI)』と呼びます。 面積に関するSI単位は、現在、平方キロメートルと平方メートルだけです。 日本は、1959年に制定された旧計量法でメートル法が正式単位になりました。 アメリカでもSI単位が使用されていますが、今でも『ヤードポンド法』が主流になっています。 イギリスには複雑極まる『帝国単位』が長い間使用されて来たので→→今でも、一部の帝国単位系の使用が認められていますが→→基本的にはSI単位に移行しています。
・・・ ヤードポンド法の面積 ・・・
★ エーカー(ac)= 43,560 平方フィート≒40.469a≒4反
★ 平方ヤード =9平方フィート≒ 0.836 平方メートル
【水田の条里制】
平地に有る水田は、正方形や長方形(三角形も有る)に整備され→→整然と並んでいます。 (私は、山村で生まれ育ったので棚田しか見た事が有りませんでした。 私の一番上の姉が、田辺市郊外の高台に家を建てました。姉の家から眺めると→→田圃が長方形に整備されていて、ビックリしました。 義兄が、「大昔の条里制で、整備されたのだ」と教えてくれました。
飛鳥時代(592年~710年)から『班田収授法』が有って、平安時代の中頃まで、平地の水田を整備したのだそうです。 人力の土木工事ですから、国を挙げての大事業だったと思われます。
今でも、条里制で整備された状態が、全国にそのまま残っています。 私は、現役時代に全国を飛び回ったので、水田を見る機会が沢山有りました。 畔(あぜ)が不自然に曲がっている個所を時々見掛けました。 「地震で断層がズレてた痕跡なのか?」などと思いを巡らせて楽しみました。
尺貫法では、『町(ちょう』が”長さの単位”と”面積の単位”として使用されます。 面積の単位として使用するケースでは『町歩(ちょうぶ)』が使用される場合が多いい様です。 私の故郷では、面積の単位『反(たん)』も『反歩』と呼んでいました。『歩(ほ)』も長さと面積の単位として使用されました。 1歩=6尺≒1.82mです。
条里制の『条』とは南北に引かれた線、『里』は東西に引かれた線をさします。
平地の水田地帯の条里制は、1町(約109m)間隔で→→『条』と『里』の線を引いて→→正方形の地割をして→→畔(あぜ)巡らせるのが基本でした。 『1町』掛ける『1町』の正方形の面積を『1町(=1町歩)』としたのです。
大昔は人力で水田を耕し、草引きをして、刈り取っていました。 (私の意見ですが、)「一枚が1町歩も有る田圃を人力で管理するのは難しい為に→→1町歩を正方形や長方形に細分化したのだ」と思います。 その地割が、現在でも各地に残っています。
・・・ 尺貫法の長さの単位 ・・・
★ 里(り)=36町≒3.93km
★ 町(ちょう)=60間≒109.1m
★ 間(けん)=6尺≒1.82m
★ 尺(しゃく)=10寸≒30.3cm
★ 寸(すん)=10分≒3.03cm
★ 分(ぶ)≒3.03mm
◎ 歩(ほ)=6尺≒1.82m
【水田の面積】
水田の面積は、1968年に最大『341万ha』になりましたが、その後は毎年減少してきました。 2018年に減反政策は廃止されましたが、今でも休耕田が非常に多いいです。 2024年の水田面積は『235万ha』でしたが、作付面積は『136万ha』しか有りませんでした。 ・・・『58%』にしか稲は植えられていないのです。
・・・ 農耕面積の推移 ・・・
★ 2024年 :水田≒235万ha、畑≒194万ha、合計≒429万ha
★ 2020年 :水田≒241万ha、畑≒200万ha、合計≒441万ha
★ 2000年 :水田≒270万ha、畑≒214万ha、合計≒484万ha
★ 1980年 :水田≒308万ha、畑≒237万ha、合計≒545万ha
★ 1960年 :水田≒336万ha、畑≒271万ha、合計≒607万ha
出典 :農林水産省が公表しているグラフ『国内の農地面積の推移』を、私が数値化しました。
【一戸当たりの水田面積】
現在の日本の農業の最大の問題点は、一戸当たりの耕作面積が非常に少ない事です。
農林水産省が公表している、一戸当たりの水田面積は『1.5ha』と『1.8ha』の2種類有りますが、何れにしても、アメリカの『320ha』と比べると二桁以上の違いが有ります。
★ 日本≒1.8ha
★ アメリカ≒320ha
【田圃の種類】
私の父は、山林の売買をしていたので『5 万分1の地図』を沢山所有していました。 田圃には軍事目的で、①乾田、②水田、③沼田の3種類の記号が書いてありました。 (現在の地図では、記号は1種類になっています。)
乾田(かんでん)は、兵士や軍用車両が何時でも移動できる田圃です。 一般に、乾田の収穫量は多いいです。
① 乾田(かんでん) : 水はけが良く、水を入れない時に地面が乾いた状態になる田圃
② 水田 :①と③の中間
③ 沼田 :冬場でもぬかるむ田圃
④ 湿田 :年間を通して地面が湿った状態にある田圃
★ 棚田(たなだ) :一塊の棚田には、乾田~湿田まで混在します。
・・・ 収穫量による水田の区分 ・・・
豊臣秀吉が1582年から始めた『太閤検地』で、1反あたりの石高(収穫量)で水田のランク付けをしました。江戸時代も、太閤検地の基準が使用されました。 田畑一反当たりの高(土地の価値)を決める事を『石盛(こくもり)』と呼びました。
❶ 上田 :1石5斗(15の盛)
❷ 中田 :1石3斗(13の盛) ・・・収穫量が平均
❸ 下田 :1石1斗(11の盛)
❹ 下々田 : 9斗(9の盛)
出典 :レファレンス共同データベース :『石盛(こくもり)』
1石=10斗≒180リットル
【水稲の収穫量】
農業は自然が相手ですから、天候によって収穫量が変動します。 各都道府県毎に、平年の収穫量を『100』とします。 平年より『3%』収穫量が多ければ→→作況指数が「103」だと公表され→→「やや良」の年だったとされます。
・・・ 作況指数の区分 ・・・
★ 良 :106以上
★ やや良 :102~105
★ 平年並み :99~101 ・・・2023年の作況指数は『101』ほどだった様です。
★ やや不良 :95~98
★ 不良 :91~94
★ 著しい不良 :90以下 ・・・1993年の『平成の米騒動』の時は、冷夏の為に作況指数が『74』になり、米が『200万トン』も不足しました。
《御参考 :平成と令和の米騒動》
1991年にフィリピンのピナトゥボ火山が大噴火し→→1993年、日本が冷夏に見舞われ→→米が大不作になり→→『平成の米騒動』が発生したのです。『平成の米騒動』は天災が原因でした。
2023年に日本は軽微な天候不順に襲われました。 然し、米の作況指数は『101』程度だった様です。 主食米の生産量が『661万トン』、需要が『705万トン』だったので→→『44万トン』不足しました。 備蓄米が『100万トン』有りましたから、直ぐに対策したら、何も問題は発生しなかったと思われます。 令和の米騒動は人災です!
2023年の総理大臣は岸田文雄氏で農林水産大臣は坂本哲志氏でした。 2024年10月に石破政権が発足し、11月に江藤拓氏が農林水産大臣に就任しました。 この4人は、全く何も対策し無い、無知/無能な人間でした。 こんな人間を国会議員にした責任は国民に有ります。 無能な人間に投票したら→→時として、国民が苦しむ事になるのです。
① 全国の米の平均収量は、10a(1反)当たり『540kg』です。
② 2024年の米の生産量は735万トンで、需要は702万トンでした。
③ 2024年の水田の面積は235万haで、作付け面積は136万ha ・・・『58%』にしか利用されていません。
・・・ 都道府県の10a(1反)当たりの米収穫量 ・・・ 2024年 農林水産省
★ 1位 :長野と青森≒614kg
★ 3位 :山形≒589kg
★ 47位 :沖縄≒321kg
・・・ 都道府県の米収穫量 ・・・ 2024年 農林水産省
★ 1位 :新潟=59万トン
★ 2位 :北海道≒54万トン
★ 47位 :東京≒465トン
【三菱総研の稲作農家の分析】
私は現役時代に大手シンクタンク『(株)三菱総合研究所(三菱総研)』に、何回か、お世話になりました。 私の相談に乗って頂いた方は全て、幅広い知識を持った素晴らしい人達でした。 石破茂氏や小泉進次郎氏は、農業についての知識が不足していますから、三菱総研のアドバイスを受けるべきです。
三菱総研が、2023年7月12日に『コメ農家が赤字でもコメを作り続ける理由』のタイトルで、分かり安い分析結果を公表しています。 但し、以下の❶~❸の条件をベースにしています。 こめ農家の95%は、農家としては『赤字』ですが、休日の時間で農作業をしている兼業農家です。
❶ 作付けの割合=100% ・・・実際は『58%』程度です。
❷ 米の販売価格=2,000円/10kg
❸ 耕作に要する作業時間 :タイプ1=160時間(≒46時間/10a)、タイプ2=420時間(≒25時間/10a)、タイプ3=2,500時間(15≒時間/10a)
・・・ 三菱総研の分析の概要 ・・・
タイプ1 :所有水田『35a』 ・・・兼業農家→→農業の収支は赤字
タイプ2 :所有水田『170a』 ・・・日本の平均的稲作農家→→農業の収支は赤字
タイプ3 :所有水田『1,700a』 ・・・専業農家→→兼業しないで生活出来る。
タイプ4 :所有水田『6,300a』 ・・・大規模農家→→『1,853万円』程の所得が期待出来る。
他の参考になる資料 :YUIME Japan 2023年6月12日 『米作りにかかる費用の目安を教えてほしい』
小泉進次郎大臣は、米の店頭価格を下げる為に奔走している様ですが、近年の法律の改正で「米の価格を下げるのは政府の役割では無い」事になっています。 この基本方針には全く触れないで、「当面の価格を下げれば良い」と言うスタンスです。 稲作の喫緊の課題は、「農家の収入が少なく→→息子/娘が跡を継がないケースが増え→→親父さんが高齢化して→→政府が、対策を講じないと→→日本の農業は壊滅的な状況になる!」ことです。
備蓄米を安値で放出し→→5kgで2,000円台の米が→→店頭に並ぶと→→直ぐに売り切れるそうです。 「現在、主食米が不足している」とは思えません。 流通経路に、「5kgで2,000円台」では赤字になる米が沢山残っていると想像します。 小泉大臣は、米屋を倒産させようとしているのか?
「令和の米騒動を経験したので、食品の安定供給の重要性について、国民の多くの方が認識された」と私は思っています。 私が、このシリーズのブログを書いているのは、『食の安全保障』と『永続可能な農林水産業』に関する、私の持論を近い将来書きたいと考えており、「私の主張を御理解頂く為には農業についの知識を広げて頂く必要が有る」と思うからです。
【農地の面積の単位】
日本では、農地や山林の面積には公式には、メートル法の『平方メートル(m2)』や『アール(a)』が使用されますが、一般に『町・反・畝・歩』も使用されています。 宅地や家屋の場合、尺貫法の単位は『坪・合・勺』ですが、『合・勺』は殆ど使用されません。
アメリカとイギリスは今でも、ヤードポンド法の面積単位が採用されていますが、その他の国ではメートル法に切り替わっています。
(注記) 『合』と『勺』は、本来は体積の単位です。 面積の単位の合と勺は、凄く小さな面積なので、一般には殆ど使用されていません。
・・・ 尺貫法の面積 ・・・
① 町(ちょう)=10反 ≒ 9,917平方メートル(m2)
② 反(たん)=10畝 ≒992平方メートル≒10a
③ 畝(せ) =30坪 ≒99平方メートル
④ 坪(つぼ)=10合 ≒3.3平方メートル
⑤ 合(ごう)=10勺 ≒0.33平方メートル
⑥ 勺(しゃく)=0.1合 ≒0.033平方メートル
⑦ 歩(ほ)=6尺✕6尺=1坪≒3.3平方メートル
(注記) 『歩』は条里制で使用された単位で、現在は『坪』が使用されています。
・・・ メートル法の面積 ・・・
❶ 平方キロメートル(km2)=100ha≒100町
❷ ヘクタール(ha)=100a≒1町
❸ アール(a)=100m2≒1畝
❹ 平方メートル(m2)
(注記 :国際単位系) 国際的な条約で決めた単位系を『国際単位系(SI)』と呼びます。 面積に関するSI単位は、現在、平方キロメートルと平方メートルだけです。 日本は、1959年に制定された旧計量法でメートル法が正式単位になりました。 アメリカでもSI単位が使用されていますが、今でも『ヤードポンド法』が主流になっています。 イギリスには複雑極まる『帝国単位』が長い間使用されて来たので→→今でも、一部の帝国単位系の使用が認められていますが→→基本的にはSI単位に移行しています。
・・・ ヤードポンド法の面積 ・・・
★ エーカー(ac)= 43,560 平方フィート≒40.469a≒4反
★ 平方ヤード =9平方フィート≒ 0.836 平方メートル
【水田の条里制】
平地に有る水田は、正方形や長方形(三角形も有る)に整備され→→整然と並んでいます。 (私は、山村で生まれ育ったので棚田しか見た事が有りませんでした。 私の一番上の姉が、田辺市郊外の高台に家を建てました。姉の家から眺めると→→田圃が長方形に整備されていて、ビックリしました。 義兄が、「大昔の条里制で、整備されたのだ」と教えてくれました。
飛鳥時代(592年~710年)から『班田収授法』が有って、平安時代の中頃まで、平地の水田を整備したのだそうです。 人力の土木工事ですから、国を挙げての大事業だったと思われます。
今でも、条里制で整備された状態が、全国にそのまま残っています。 私は、現役時代に全国を飛び回ったので、水田を見る機会が沢山有りました。 畔(あぜ)が不自然に曲がっている個所を時々見掛けました。 「地震で断層がズレてた痕跡なのか?」などと思いを巡らせて楽しみました。
尺貫法では、『町(ちょう』が”長さの単位”と”面積の単位”として使用されます。 面積の単位として使用するケースでは『町歩(ちょうぶ)』が使用される場合が多いい様です。 私の故郷では、面積の単位『反(たん)』も『反歩』と呼んでいました。『歩(ほ)』も長さと面積の単位として使用されました。 1歩=6尺≒1.82mです。
条里制の『条』とは南北に引かれた線、『里』は東西に引かれた線をさします。
平地の水田地帯の条里制は、1町(約109m)間隔で→→『条』と『里』の線を引いて→→正方形の地割をして→→畔(あぜ)巡らせるのが基本でした。 『1町』掛ける『1町』の正方形の面積を『1町(=1町歩)』としたのです。
大昔は人力で水田を耕し、草引きをして、刈り取っていました。 (私の意見ですが、)「一枚が1町歩も有る田圃を人力で管理するのは難しい為に→→1町歩を正方形や長方形に細分化したのだ」と思います。 その地割が、現在でも各地に残っています。
・・・ 尺貫法の長さの単位 ・・・
★ 里(り)=36町≒3.93km
★ 町(ちょう)=60間≒109.1m
★ 間(けん)=6尺≒1.82m
★ 尺(しゃく)=10寸≒30.3cm
★ 寸(すん)=10分≒3.03cm
★ 分(ぶ)≒3.03mm
◎ 歩(ほ)=6尺≒1.82m
【水田の面積】
水田の面積は、1968年に最大『341万ha』になりましたが、その後は毎年減少してきました。 2018年に減反政策は廃止されましたが、今でも休耕田が非常に多いいです。 2024年の水田面積は『235万ha』でしたが、作付面積は『136万ha』しか有りませんでした。 ・・・『58%』にしか稲は植えられていないのです。
・・・ 農耕面積の推移 ・・・
★ 2024年 :水田≒235万ha、畑≒194万ha、合計≒429万ha
★ 2020年 :水田≒241万ha、畑≒200万ha、合計≒441万ha
★ 2000年 :水田≒270万ha、畑≒214万ha、合計≒484万ha
★ 1980年 :水田≒308万ha、畑≒237万ha、合計≒545万ha
★ 1960年 :水田≒336万ha、畑≒271万ha、合計≒607万ha
出典 :農林水産省が公表しているグラフ『国内の農地面積の推移』を、私が数値化しました。
【一戸当たりの水田面積】
現在の日本の農業の最大の問題点は、一戸当たりの耕作面積が非常に少ない事です。
農林水産省が公表している、一戸当たりの水田面積は『1.5ha』と『1.8ha』の2種類有りますが、何れにしても、アメリカの『320ha』と比べると二桁以上の違いが有ります。
★ 日本≒1.8ha
★ アメリカ≒320ha
【田圃の種類】
私の父は、山林の売買をしていたので『5 万分1の地図』を沢山所有していました。 田圃には軍事目的で、①乾田、②水田、③沼田の3種類の記号が書いてありました。 (現在の地図では、記号は1種類になっています。)
乾田(かんでん)は、兵士や軍用車両が何時でも移動できる田圃です。 一般に、乾田の収穫量は多いいです。
① 乾田(かんでん) : 水はけが良く、水を入れない時に地面が乾いた状態になる田圃
② 水田 :①と③の中間
③ 沼田 :冬場でもぬかるむ田圃
④ 湿田 :年間を通して地面が湿った状態にある田圃
★ 棚田(たなだ) :一塊の棚田には、乾田~湿田まで混在します。
・・・ 収穫量による水田の区分 ・・・
豊臣秀吉が1582年から始めた『太閤検地』で、1反あたりの石高(収穫量)で水田のランク付けをしました。江戸時代も、太閤検地の基準が使用されました。 田畑一反当たりの高(土地の価値)を決める事を『石盛(こくもり)』と呼びました。
❶ 上田 :1石5斗(15の盛)
❷ 中田 :1石3斗(13の盛) ・・・収穫量が平均
❸ 下田 :1石1斗(11の盛)
❹ 下々田 : 9斗(9の盛)
出典 :レファレンス共同データベース :『石盛(こくもり)』
1石=10斗≒180リットル
【水稲の収穫量】
農業は自然が相手ですから、天候によって収穫量が変動します。 各都道府県毎に、平年の収穫量を『100』とします。 平年より『3%』収穫量が多ければ→→作況指数が「103」だと公表され→→「やや良」の年だったとされます。
・・・ 作況指数の区分 ・・・
★ 良 :106以上
★ やや良 :102~105
★ 平年並み :99~101 ・・・2023年の作況指数は『101』ほどだった様です。
★ やや不良 :95~98
★ 不良 :91~94
★ 著しい不良 :90以下 ・・・1993年の『平成の米騒動』の時は、冷夏の為に作況指数が『74』になり、米が『200万トン』も不足しました。
《御参考 :平成と令和の米騒動》
1991年にフィリピンのピナトゥボ火山が大噴火し→→1993年、日本が冷夏に見舞われ→→米が大不作になり→→『平成の米騒動』が発生したのです。『平成の米騒動』は天災が原因でした。
2023年に日本は軽微な天候不順に襲われました。 然し、米の作況指数は『101』程度だった様です。 主食米の生産量が『661万トン』、需要が『705万トン』だったので→→『44万トン』不足しました。 備蓄米が『100万トン』有りましたから、直ぐに対策したら、何も問題は発生しなかったと思われます。 令和の米騒動は人災です!
2023年の総理大臣は岸田文雄氏で農林水産大臣は坂本哲志氏でした。 2024年10月に石破政権が発足し、11月に江藤拓氏が農林水産大臣に就任しました。 この4人は、全く何も対策し無い、無知/無能な人間でした。 こんな人間を国会議員にした責任は国民に有ります。 無能な人間に投票したら→→時として、国民が苦しむ事になるのです。
① 全国の米の平均収量は、10a(1反)当たり『540kg』です。
② 2024年の米の生産量は735万トンで、需要は702万トンでした。
③ 2024年の水田の面積は235万haで、作付け面積は136万ha ・・・『58%』にしか利用されていません。
・・・ 都道府県の10a(1反)当たりの米収穫量 ・・・ 2024年 農林水産省
★ 1位 :長野と青森≒614kg
★ 3位 :山形≒589kg
★ 47位 :沖縄≒321kg
・・・ 都道府県の米収穫量 ・・・ 2024年 農林水産省
★ 1位 :新潟=59万トン
★ 2位 :北海道≒54万トン
★ 47位 :東京≒465トン
【三菱総研の稲作農家の分析】
私は現役時代に大手シンクタンク『(株)三菱総合研究所(三菱総研)』に、何回か、お世話になりました。 私の相談に乗って頂いた方は全て、幅広い知識を持った素晴らしい人達でした。 石破茂氏や小泉進次郎氏は、農業についての知識が不足していますから、三菱総研のアドバイスを受けるべきです。
三菱総研が、2023年7月12日に『コメ農家が赤字でもコメを作り続ける理由』のタイトルで、分かり安い分析結果を公表しています。 但し、以下の❶~❸の条件をベースにしています。 こめ農家の95%は、農家としては『赤字』ですが、休日の時間で農作業をしている兼業農家です。
❶ 作付けの割合=100% ・・・実際は『58%』程度です。
❷ 米の販売価格=2,000円/10kg
❸ 耕作に要する作業時間 :タイプ1=160時間(≒46時間/10a)、タイプ2=420時間(≒25時間/10a)、タイプ3=2,500時間(15≒時間/10a)
・・・ 三菱総研の分析の概要 ・・・
タイプ1 :所有水田『35a』 ・・・兼業農家→→農業の収支は赤字
タイプ2 :所有水田『170a』 ・・・日本の平均的稲作農家→→農業の収支は赤字
タイプ3 :所有水田『1,700a』 ・・・専業農家→→兼業しないで生活出来る。
タイプ4 :所有水田『6,300a』 ・・・大規模農家→→『1,853万円』程の所得が期待出来る。
他の参考になる資料 :YUIME Japan 2023年6月12日 『米作りにかかる費用の目安を教えてほしい』