[映画紹介]

1858年、イタリアのボローニャの
ユダヤ人街に住むモルターラ家に
教皇から派遣された兵士たちが訪れ、
6歳になる息子エドガルドを連れ去ってしまう。
両親は息子を取り戻すために奔走するが、
神学校に入れられたエドガルドに会うことは出来ても、
家に連れ帰ることは叶わない。
教皇側の言い分は、こうだ。
エドガルドはある人物から洗礼を受けており、
キリスト教徒であるから、
ユダヤ人の家庭では育てることは出来ず、
敬虔なクリスチャンになるための教育をする
というのだ。

事件はおおやけとなり、
世論と国際的なユダヤ人社会に支えられて、
モルターラ夫妻の闘いは急速に政治的な局面を迎える。
当時は、イタリアの独立闘争の真っ只中であり、
自由主義運動が勃興し、
保守反動的なローマ・カトリック教会と
民衆が対立していた時代。
31年間という、歴代最長在位期間を誇る
時のローマ教皇ピウス9世は、
弱体化著しかった教会の権威回復と、
権力を強化するために、
かたくなになってしまう・・・

というわけで、一人の子供を巡っての
カトリック教会とユダヤ教との争奪戦を描く。
つくづく宗教はやっかいだと思う。
宗教の特性は、
自らの正当性と無謬性だから、
妥協することがない。
大の大人が寄ってたかって、
幼い子供の脳みそに手を突っ込み、
自分の側に引き寄せようとする。
親子の情愛など、歯牙にもかけない。
途中で「洗礼」の真相が明らかになるが、
幼いエドガルドが病気の時に、
出入りしていた家政婦が救いを与えようと、
容器に入った水を頭に垂らしただけだと分かる。
本来、洗礼は聖職者がしなければ無効だが、
瀕死の瀬戸際には、聖職者以外の者が施すことが出来るのだという。
しかし、何も分からない赤子にほどこした
「洗礼もどき」のもの根拠に、
教皇庁が拉致するのだから、あきれる。
元々洗礼は、水の中に頭まで浸かって(浸礼)、
一度死んで蘇る、という意味があるのであって、
頭に水を垂らしてするのは、「滴礼」と言って簡易型のもの。
今でも、教派によっては、
浸礼しか認めないと、
礼拝堂の床に水槽を備えているところもある。
いずれにせよ、
キリストの時代とは、やり方が違う。
成人したエドガルドの「粗相」を
ピウス9世がとがめて、
ある反省の行為をさせるが、
もしキリストが蘇ってその様を見たら、
「私はそんなことをしろとは言っていない」
と否定するだろう。
ついでに言うと、
今の日本の仏教がしている戒名や法事を
ブッダが見たら、
「こんな事を誰が定めたんだ」
と拒絶するだろう。
驚くような描写もある。
エドガルドが祭壇にある磔刑のキリスト像によじ登り、
手足に打たれた釘を抜いてやると、
キリストが解放されて、自由に歩み去るところ。
エドガルドの夢なのだが、
子供の純粋な目だとそう見えるのだ。
もう一か所、一緒に教育を受けていた子供が病死した際、
その葬儀の場で、子供同士が
「祈ったけど無駄だったね」
と言うところ。
これも子供の視点から真理を突いている。
約150年前の事件を描くが、
現代にも通じる多くの課題を突きつける。
宗教に根ざした戦争は今も続いている。
取り戻そうとする両親を拒む教会の姿に、
カルト教団に子供を奪われて闘う父母の姿や
北朝鮮に拉致された被害者を取り戻そうとする肉親の姿が重なる。

ローマの歴史的宗教建造物が沢山出て来るが、
カソリックの暗黒史に加えられそうな事件の内容で、
よく撮影許可が出たものだ。
二つ宗教に挟まれて呻吟する
子供の姿を描いて胸が痛かった。
近代史の出来事を積極的に描こうとする
スティーヴン・スピルバーグ(ユダヤ系)が映画化を目論み、
書籍の原作権を押さえたのだが、

結局、映画化を実現したのは
イタリアの巨匠マルコ・ベロッキオだった。
原題の「Rapito」は「誘拐」の意。
5 段階評価の「4」。
ヒューマントラストシネマ有楽町他で上映中。










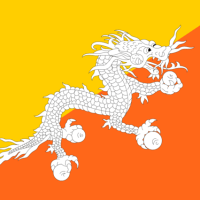









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます