(2022年9月18日投稿)
【はじめに】
前回のブログでは、小林公夫氏の『論理思考の鍛え方』(講談社現代新書、2004年)をもとに、人間の能力因子、論理力について述べた。
今回は、同じ小林公夫氏の次の著作を取り上げ、引き続き、論理力について考えてみたい。
〇小林公夫『法曹への論理学 適性試験で問われる論理力の基礎トレーニング<第3版>』早稲田経営出版、2004年[2006年第3版]
この書の「プロローグ」(5頁)においても、小林氏の前著『論理思考の鍛え方』(講談社現代新書、2004年)のことが言及されている。
『論理思考の鍛え方』では、人間の能力因子について解明を試みたという。
人間の能力因子で最も最重要なものは、推理能力因子、比較能力因子、更に抽象化能力因子であるとする。
第一の推理能力は、個別に存在しているものの中に共通項(同一性)を識別して、物事の在りようのルール、法則性を発見していく能力、さらにその逆で、統一的な法則性を他のケースに当てはめ、未知のものを導き出す能力である。
第二の比較能力は、まず二つのもののどちらが長いか、重いかといった単純な段階を経て、三者関係、四者関係と複雑な関係性の理解が要求されてくるものである。また、何と何を比較するのかを把握する能力も比較能力の一つである。
第三の抽象化能力は、二つの側面を持っている。一つは、宗教や哲学、芸術といった人間の精神性との関係で語られる場合である。もう一つの側面は、事物を「量」「重さ」「長さ」といった特定の観点から捉え、そこに一元化して考える能力、さらに数や式などの記号と結びつけて考える能力と位置づけられる。
このような人間の基本的な重要能力因子に加え、法曹の仕事には、法的思考力(リーガルマインド)が求められる。「法的解決」ないし「法的処理」という目的に向けて、目の前にある法的問題の中心的命題が何であるか、つまり法律的観点から見て解決されるべき問題の主眼がどこにあるかを認知して、処理にとりかかるかという能力、論理力のことであるようだ。
それでは、「論理的判断力」「長文読解力」「表現力」が身につくよう、本書の収められた問題をみてみよう。
【小林公夫氏のプロフィール】
・1956年生まれ、東京出身。
・横浜市立大学卒業、2000年に一橋大学大学院法学研究科修士課程に社会人入学、2007年に同博士後期課程を修了。
・一橋大学博士(法学)。博士論文は「医療行為の正当化原理」
【小林公夫『法曹への論理学』(早稲田経営出版)はこちらから】
小林公夫『法曹への論理学』(早稲田経営出版)
〇小林公夫『法曹への論理学 適性試験で問われる論理力の基礎トレーニング<第3版>』早稲田経営出版、2004年[2006年第3版]
【目次】
第3版の改訂に際して
プロローグ
第1章 論理学の基礎マスター編
第1部・論理構造に関する基本的仕組みと考え方
・命題の問題に関する基本的仕組みと考え方
第2部・「批判」トレーニング26題
第2章 基礎トレーニング編
第1問 前提
第2問 前提
第3問 前提
第4問 前提
第5問 前提
第6問 支持
第7問 論理の飛躍
第8問 論理的反論
第9問 論理的反論
第10問 仮説形成
第11問 仮説形成
第12問 発言の相関関係
第13問 批判
第14問 批判
第15問 利益衡量
第16問 利益衡量
第17問 利益衡量
第3章 応用力養成編
第1問 命題
第2問 命題
第3問 命題
第4問 命題
第5問 命題
第6問 命題・ド・モルガンの法則
第7問 必要十分条件
第8問 必要条件・十分条件
第9問 必要条件・十分条件
第10問 逆≠真
第11問 逆・裏・対偶
第12問 命題
第13問 ド・モルガンの法則
第14問 循環論法
第15問 前提
第16問 支持
第17問 論理の飛躍
第18問 批判
第19問 批判
第20問 批判
第21問 批判
第22問 批判
第23問 反論
第24問 反論方法
第25問 反論
第26問 反論
第27問 反論
第28問 反論
第29問 反論
第30問 異論
第31問 2者の発言の相関関係
第32問 2者の発言の相関関係
第33問 2者の発言の相関関係・支持
第34問 2者の発言の相関関係・支持
第35問 2者の発言の相関関係・批判
第36問 主なる論点
第37問 共通の認識
第38問 推理
第39問 推理
第40問 推理
第41問 論理構成
第42問 論理構成
第43問 推論方法
第44問 対立する利益の調整①携帯電話使用の是非
第45問 対立する利益の調整②監視カメラ設置とプライバシー
第46問 対立する利益の調整③AID児に、出自を知る権利はあるか?
第4章 論理的長文問題トレーニング編
第1問 権利の行使と権利の喪失
第2問 体の大きさと進化
第3問 裁判員制度の是非
第4問 世界劇場論
第5問 翻訳のあるべき姿
第6問 情報化時代と「人格」の不存在
第7問 「ウチ」と「ソト」
第8問 労働の意義
さて、今回の執筆項目は次のようになる。
・命題の問題に関する基本的仕組みと考え方
・第3章 応用力養成編の命題問題
・命題とド・モルガンの法則~第3章より
・2者の発言の相関関係・支持~第3章より
・翻訳のあるべき姿~第4章 論理的長文問題トレーニング編より
・【補足】日本人の配慮
命題の問題に関する基本的仕組みと考え方
【命題の問題に関する基本的仕組みと考え方】
≪問題を解く際の基本的手法≫
①論理記号で表してみる。
②関係図を作ってみる(対偶、三段論法、ド・モルガンの法則などに注意)。
③各選択肢を検討する。
④ベン図を描いてみる。
≪基本的な注意事項≫
・命題:真偽(〇×)が判定できる文、またはその内容。
以下特に断りがないときには、すべての命題を真(〇)とする。
・論理の問題を解く際には、自分の常識や価値観で勝手に真偽を判断してはいけない。
☆命題には様々な種類があるが、もっとも簡単なものからその表現方法などを考えてみよう。
①肯定形の表現方法
<日本語> AならばBである
<論理記号> A→B
<ベン図> (省略)
[例]
<日本語> バラは植物である
<論理記号> バラ→植物
<ベン図> (省略)
②否定形の表現方法
<日本語> AはBではない
<論理記号> A→B
<ベン図> (省略)
※【お断り】
論理記号を表す場合、本来、オーバーライン ̄で記すが、今回のブログでは、入力の都合上、
アンダーバー(B)でしるす。(以下、同様)
③A→Bのその他の表現方法
AがBに含まれている
④「AならばBである」と「BならばAである」の成立
A→BかつB→A ⇒双方向なケースの構造
この場合、AとBはお互いに必要十分条件であるという(同値)
<重要マスター事項>
・A→B
AはBが成立するための十分条件
BはAが成立するための必要条件
[例]
バラは植物である バラであることは植物であるための十分条件
(バラ→植物) 植物であることはバラであることの必要条件
⑥三段論法の構造
<日本語> AならばBである かつBならばCである AならばCである
<論理記号> A→B かつB→C A→B→C
<ベン図> (省略)
⑦逆、裏、対偶の関係
P:A→B ――逆―― Q:B→A
裏 対偶 裏
R:A→B ――逆―― S:B→A
※対偶の関係同士にある命題は真偽が一致する。
否定形が多い命題を考えるとき、対偶の命題を考えることにより肯定形として考えることが可能となる。
⑦’ド・モルガンの法則
<ド・モルガンの法則ポイント1 P∨Qの意味は?>
P∨Q=P∧Q
<ド・モルガンの法則ポイント2 P∧Qの意味は?>
P∧Q=P∨Q
⑧∧「かつ」と∨「または」
<日本語> AかつB AまたはB
<論理記号> A∧B A∨B
<ベン図> (省略)
⑨A∨B→C、A→B∧Cの分解
「また先にして、後でかつ」と覚えること
⑩A→B∧Cが正しいとき、なぜA→B∨Cも成立するか?
<ベン図> (省略)
(小林公夫『法曹への論理学<第3版>』早稲田経営出版、2004年[2006年第3版]、7頁~17頁)
第3章 応用力養成編の命題問題
〇第2章では、論理力の基礎固めをした。第3章では、いよいよ実戦形式で“論理”の応用力を養成するという。
本章では、次のような演習問題が載っている。
①命題の分野で頻出のA→B∨C、A→B∧Cの相互の関係
②ド・モルガンの法則の複雑な処理
③発言者が2者いる場合の相関関係
「第3章 応用力養成編」から、ベン図を使う「第2問 命題」と「第3問 命題」を紹介しておこう。
【第2問 命題】
次のAとBの相互の論理的関係として正しいものを、下の①~⑤のうちから選べ。
A 図画工作が不得意な人は、手先が器用ではない。
B 手先が器用で美的センスのある人は、図画工作が得意である。
①Aが正しいとき、必ずBも正しい。また、Bが正しいとき、必ずAも正しい。
②Aが正しいとき、必ずBも正しい。しかし、Bが正しいときに必ずAも正しいとは限らない。
③Bが正しいとき、必ずAも正しい。しかし、Aが正しいときに必ずBも正しいとは限らない。
④Aの正しさとBの正しさは、論理的に無関係である。
⑤Aの正しさとBの正しさは、論理的に成立しない。
【解答・解説】
<解説>
A 図画工作が不得意な人は、手先が器用ではない。
B 手先が器用で美的センスのある人は、図画工作が得意である。
A:図→器(対偶をとる) 器→図
B:器∧美→図
器のはみだしというケースがありうる
※反証例が挙げられる図の作成がポイントとなる

A、Bのベン図から分かるように、
A→Bは成立するが、
B→Aは、上図のように器のはみ出しがあるCのようなケースでは必ずしも成立しない。
よって、Aが正しいとき、必ずBも正しい。
しかし、Bが正しいときに必ずAも正しいとは限らない。
<正解>②
(小林公夫『法曹への論理学<第3版>』早稲田経営出版、2004年[2006年第3版]、71頁~76頁)
【第3問 命題】
次のAとBの相互の論理関係として正しいものを、下の①~⑤のうちから選べ。
A 忍耐力があり、集中力もあるような生徒は、勉強熱心である。
B 勉強熱心でない生徒は、忍耐力がない。
①Aが正しいとき、必ずBも正しい。また、Bが正しいとき、必ずAも正しい。
②Aが正しいとき、必ずBも正しい。しかし、Bが正しいときに必ずAも正しいとは限らない。
③Bが正しいとき、必ずAも正しい。しかし、Aが正しいときに必ずBも正しいとは限らない。
④Aの正しさとBの正しさは、論理的に無関係である。
⑤Aの正しさとBの正しさは、論理的に成立しない。
【解答・解説】
<解説>
A 忍耐力があり、集中力もあるような生徒は、勉強熱心である。
B 勉強熱心でない生徒は、忍耐力がない。
A:忍∧集→勉 ※忍のはみだしというケースがありうる
B:勉→忍(対偶をとる)忍→勉
A、Bのベン図から分かるように、
A→Bは成立しないケースがある。
例えば、上図のように忍のはみ出しがあるCのようなケースでは、A→Bは不成立。
逆に、B→Aは成立する。
よって、Bが正しいとき、必ずAも正しい。
しかし、Aが正しいときに必ずBも正しいとは限らない。
<正解>③
(小林公夫『法曹への論理学<第3版>』早稲田経営出版、2004年[2006年第3版]、77頁~78頁)
命題とド・モルガンの法則~第3章より
「第3章 応用力養成編」から、ベン図を使う「第6問 命題・ド・モルガンの法則」と「第13問 ド・モルガンの法則」を紹介しておこう。
〇第6問 命題・ド・モルガンの法則
次の文章を読み、下の問いに答えよ。
ある大学で入学試験を行った日に雪が降った。その地方ではめったに雪が降ることはなかったので、交通機関に遅れが生じ、多くの遅刻者が出ることとなった。このことについて、次のA~Cの3つの主張が3人から出された。
A 遅刻した人は電車とバスを両方利用していた。
B 電車もバスも利用しなかった人は遅刻しなかった。
C 電車を利用しなかった人は遅刻しなかった。
問 A~Cの主張相互の論理的関係として正しいものを、次の①~⑥のうちから選べ。
① Aが正しいとき、必ずBも正しい。また、Bが正しいとき、必ずCも正しい。
② Aが正しいとき、必ずCも正しい。また、Cが正しいとき、必ずBも正しい。
③ Bが正しいとき、必ずAも正しい。また、Aが正しいとき、必ずCも正しい。
④ Bが正しいとき、必ずCも正しい。また、Cが正しいとき、必ずAも正しい。
⑤ Cが正しいとき、必ずAも正しい。また、Aが正しいとき、必ずBも正しい。
⑥ Cが正しいとき、必ずBも正しい。また、Bが正しいとき、必ずAも正しい。
(平成15年8月実施、法科大学院適性試験(大学入試センター)第5問)
【解答・解説】
<解説>
・基本事項の確認。ただし、Aの否定をAと表記する。
〇対偶
A→Bが成り立つとき、B→Aも成り立つ
〇∧「かつ」と∨「または」~ド・モルガンの法則
「A∧B」の否定は「A∨B」
「A∨B」の否定は「A∧B」
・今、「遅刻した」をT、「電車を利用した」をD、「バスを利用した」をSとする。
まず、対偶を利用して、主語を「遅刻した人は」に揃えてみる。
A 遅刻した人は電車とバスを両方利用していた。 T→D∧S
B 電車もバスも利用しなかった人は遅刻しなかった。 D∧S→T ⇒T→D∨S
C 電車を利用しなかった人は遅刻しなかった。 D→T ⇒T→D
D∧S、D∨S、Dをベン図に表現すると、A→B、A→C、C→Bは正しい。
よって、選択肢としてふさわしいものは、②であることが分かる。
(小林公夫『法曹への論理学<第3版>』早稲田経営出版、2004年[2006年第3版]、84頁~85頁)
〇第13問 ド・モルガンの法則
ある人が家の購入に際して次のような条件を考えているとき、条件を満たす家をすべてあげている選択肢を下の①~⑧のうちから1つ選べ。
条件:「間取りに関しては『3LDK以下で、または居間が10畳以下』であり、かつ、立地に関しては『駅から徒歩3分以上かかり、かつスーパーが遠い家』以外の家。
ア 2LDKで居間は7畳、駅から徒歩3分より近くスーパーの近い家。
イ 5LDKで居間は8畳、駅から徒歩1分でスーパーの遠い家。
ウ 2LDKで居間は12畳、駅から徒歩20分でスーパーの近い家。
エ 7LDKで居間は14畳、駅から徒歩5分でスーパーの遠い家。
① ア、イ
② イ、ウ
③ ウ、エ
④ ア、エ
⑤ ア、イ、ウ
⑥ イ、ウ、エ
⑦ ア、イ、エ
⑧ ア、イ、ウ、エ
【解答・解説】
<解説>
・条件である文章が少し長いので、すべて記号化して考えてみる。
ポイントは、ド・モルガンの法則の有効活用。
「3LDK以下で、または居間が10畳以下」=A かつ「徒歩3分以上かつスーパーが遠い」=Bではない。
A∧B=A∨B
ここでA=(3LDK以下=Pで、または居間が10畳以下=Q)ではない
P∨Q=P∧Q=3LDKより広く居間が10畳より広い。
またB=(徒歩3分以上=Rかつスーパーが遠い=S)ではない。
R∧S=R∨S=徒歩3分より近いか、またはスーパーが近い
∴A∨Bより結論として、
●「3LDKより広く、居間が10畳より広いか、または徒歩3分より近いかまたはスーパーが近い」ということになる。
よって、ア、イ、ウ、エすべて正しいことになる。正解は⑧
(小林公夫『法曹への論理学<第3版>』早稲田経営出版、2004年[2006年第3版]、44頁~45頁)
第34問 2者の発言の相関関係・支持~第3章より
「第3章 応用力養成編」から、英語学習に関する議論である「第34問 2者の発言の相関関係・支持」を紹介しておこう。
A「英語を学ぶには、まず何が大切か。私は会話であると思う。確かに、文法重視の読み・書きも大切ではあるが、コミュニケーションとしての言語という観点からみれば会話の重要度は明らかであろう」
B「確かに会話は大切であるが、文法の基礎があっての会話でなくてはならない。国際人の養成を目的とする英語教育であれば、ただ話せればよいだけではだめであり、基礎力に基づくある程度格調のある英語が話せなくては意味がない。したがって、文法・会話をあわせて教育していくべきであるし、どの時期から学ぶのかということについても議論すべきである」
【No.1】両者の発言の関係を最も適切に記述したものを次の①~⑤のうちから1つ選べ。
① Aの発言に対して、Bは内容を修正しつつ、新たな方針を打ち出している。
② Aの発言に対して、Bは内容を検討しつつ、疑問を呈している。
③ Aの発言に対して、Bは内容を否定しつつ、新たな方針を打ち出している。
④ Aの発言に対して、Bは内容を賛同しつつ、疑問を呈している。
⑤ Aの発言に対して、Bは内容を修正しつつ、疑問を呈している。
【No.2】 Bの発言に対する支持として、最も強いものを次の①~⑤のうちから1つ選べ。
① 英会話中心の教育であれば、英語として偏りができてしまう。
② 英語は世界共通語となりつつあり、総合的な教育が必要である。
③ ある調査によれば、会話中心の教育を受けた生徒は基本的な英単語のスペルを書けなかった。
④ 英語も大切であるが、まず日本語の教育を充実すべきである。
⑤ 社会人となり、日常英語を使わない人は英語を学ぶ必要はない。
【解答・解説】
<解説>
A「英語を学ぶには、まず何が大切か。私は会話であると思う。確かに、文法重視の読み・書きも大切ではあるが、コミュニケーションとしての言語という観点からみれば会話の重要度は明らかであろう」
B「確かに会話は大切であるが、文法の基礎があっての会話でなくてはならない。国際人の養成を目的とする英語教育であれば、ただ話せればよいだけではだめであり、基礎力に基づくある程度格調のある英語が話せなくては意味がない。したがって、文法・会話をあわせて教育していくべきであるし、どの時期から学ぶのかということについても議論すべきである」
Aの発言のポイント
・まず何が大切か。
・私は会話であると思う。
・確かに、文法重視の読み・書きも大切ではある
・会話の重要度は明らか
Bの発言のポイント
・確かに会話は大切であるが、
・文法の基礎があっての会話で
・ただ話せればよいだけではだめ
・文法・会話をあわせて教育していくべき
・どの時期から学ぶのか
【No.1】
Aの発言⇒文法重視の読み書きも大切だが、英語学習で大切なのは、まず会話である。
Bの発言⇒英語学習において会話が大切なのは分かるが、それは、文法の基礎が前提となる。
国際人養成目的の英語教育であれば、格調の高い英語を話すことに意味がある。文法・会話教育の併存や学習開始時期についても議論すべきである。
<選択肢の検討>
① Aの発言に対して、Bは内容を修正しつつ、新たな方針を打ち出している。
② Aの発言に対して、Bは内容を検討しつつ、疑問を呈している(×)。
③ Aの発言に対して、Bは内容を否定しつつ(×)、新たな方針を打ち出している。
④ Aの発言に対して、Bは内容を賛同しつつ、疑問を呈している(×)。
⑤ Aの発言に対して、Bは内容を修正しつつ、疑問を呈している(×)。
⇒BはAの発言内容を全面否定していないし、最終的に疑問を呈しているわけではない。
BはAの発言内容を修正しつつ、新たな方針を打ち出しているの①が正解。
【No.2】
●Bの発言内容をもう一度論証構造で分析してみよう。
英語学習において会話は大切⇒しかし、文法の基礎が前提⇒国際人養成目的の英語教育⇒格調高い英語を話すことに意味あり⇒文法・会話教育の併存や学習時期についても議論すべきである
<選択肢の検討>
① 英会話中心の教育であれば、英語として偏りができてしまう。
➡英語として偏りができてしまうだけでなく、格調高い英語の意味に触れるべき。
② 英語は世界共通語となりつつあり、総合的な教育が必要である。
➡前半はよいが、後半は格調高い英語の意味に触れるべき。
③ ある調査によれば、会話中心の教育を受けた生徒は基本的な英単語のスペルを書けなかった。
➡会話中心であると、文法力が欠如することの指摘がなされており、Bの支持となりうる。
④ 英語も大切であるが、まず日本語の教育を充実すべきである。
➡弱い批判になっている。
⑤ 社会人となり、日常英語を使わない人は英語を学ぶ必要はない。
➡論点がずれている。
以上より、正確は③であるとする。
(小林公夫『法曹への論理学<第3版>』早稲田経営出版、2004年[2006年第3版]、150頁~152頁)
第5問 翻訳のあるべき姿~第4章 論理的長文問題トレーニング編より
「第3版の改訂に際して」(3頁)にも記してあるように、第4章の「論理的長文問題トレーニング編」は、大学入試センター実施の長文と論理の融合問題にも対処できるように配慮した問題である。
目次を見てもわかるが、次の問題が注目される。
≪第4章 論理的長文問題トレーニング編≫
第3問 裁判員制度の是非
第5問 翻訳のあるべき姿
第6問 情報化時代と「人格」の不存在
第7問 「ウチ」と「ソト」
上記のうち、「第5問 翻訳のあるべき姿」といった英語に関連した問題を紹介しておこう。
【第5問 翻訳のあるべき姿】
原文と訳語の一対一対応や英文和訳式の構文など、「原文の表面に忠実な翻訳」
を特徴づける要素は、漢文以来の日本文化の伝統に深く根ざしている。そして、
「汝いかになしなすか」にみられるように、日本の英語教育に深く浸透している。
翻訳者はこれらの影響から逃れることはできない。
とくに英語教育の影響は大きい。翻訳者のかなりの部分、そして翻訳学習者の大
部分は、「得意な英語を活かせる仕事」として翻訳に興味をもつようになったのだ
という。なぜ、英語が得意だと考えているかというと、たいていは学校で英語の成
績が良かったからだ。なぜ、英語の成績が良かったかというと、よほどすぐれた英
語教育に出会ったのでないかぎり、原語と訳語の一対一対応を素直に受け入れたか
らであり、英文和訳式の構文に疑問をもたなかったからだ。したがって、翻訳者の
かなりの部分、翻訳学習者の大部分にとって、英文和訳調こそが自然なのである。
意識して英文和訳調を拒否して「原文の意味を伝える翻訳」を目指さないかぎり、
英文和訳調の方向に流れていく。
このような傾向を示すものに片仮名の言葉の多用がある。片仮名の言葉が多用さ
れる理由はさまざまであり、翻訳とは関係のない要因も数多い。だが翻訳にあたっ
ても、さまざまな「理由」をつけて、片仮名の訳語が使われることが多い。確定し
た訳語がないからという「理由」をよく聞く。既成の訳語では意味がずれるからと
いわれることも多い。英語の言葉を片仮名言葉で覚えておく方が国際コミュニケー
ションの場で便利だからという人もいる。こうして原語にカタカナの訳語を一対一
であてはめていく方法が頻繁に使われている。
もちろん、片仮名の言葉に対しては抵抗感も強い。そして、片仮名言葉にもっと
も強い拒否反応を示すのは、翻訳者(少なくとも翻訳者の一部)だと思える状況も
ある。まともな翻訳者なら、訳語を考え、必要なら訳語を作るのが自分の役割だと
みている。片仮名の言葉に原語とズレがあることにも気づいている。そして片仮名
言葉の多用がむしろ、国際コミュニケーションの場で障害になることを知っている。
たとえば、情報内容を意味する「コンテンツ」という片仮名言葉がある。この言葉
がなぜもてはやされているのかはわからないが、この言葉を国際コミュニケーショ
ンの場で使っても情報発信に役立たないことはたしかだ。英語で情報内容を意味す
るときにcontentが使われることはあるが、contentsと複数形になることはまずな
いからだ(情報内容を意味するときのcontentはいわゆる不可算名詞である。ただ
しこの語は可算名詞として使われ、contentsと複数形になったときの用例でもっ
とも多いのはおそらく、書籍などの「目次」の意味で使われるものだろう)。また、
「グローバルスタンダード」という言葉は、「逆らっても仕方のない時代の流れ」と
いった意味で使われることが多いが、英語のglobal standardsにこのような意味が
あるようには思えない。片仮名の言葉には、それのもとになった英語の言葉との間
に微妙だが無視できない違いがあるのが普通であり、違いが微妙なだけにきわめて
厄介なのだ。
それでも、片仮名語が翻訳で頻繁に使われるのは、片仮名にしておけば安全だと
いう感覚があるからだ。片仮名にしておけば楽でもある。原文の語のニュアンスを
考える必要もなく、訳語をあれこれ考える必要もなく、すぐに訳文が作れる。言い
換えれば、原文の意味を考えなくても、機械的に翻訳できる。これでは「原文の意
味を伝える翻訳」になるはずがない。
このような感覚は片仮名の訳語に限ったことではない。学校英語で一対一対応で
教えられる訳語についてもおなじことがいえる。いちばん簡単な例をあげておくな
ら、heは「彼」と訳し、sheは「彼女」と訳す。そう訳しておけば安全だと感じて
いるのだろう。たしかに、英文和訳の試験ならこれが安全な方法だが、翻訳ではき
わめて危険な方法である。原文のheを「彼」と訳すとき、heと「彼」には微妙だ
が決定的な違いがあることを認識しているのだろうか。そういう認識もなく、こう
訳しておけば安全だと考えるのであれば、それは英文和訳であって、翻訳ではない。
学校で英語の成績が良かったのであれば、英文和訳の回路が頭のなかにできあが
っているはずである。原語と訳語を一対一で対応させ、英文和訳に特有の文体で訳
す回路が作られているはずである。この回路を使えば、原文の意味を考える必要も
なく、機械的に訳文が書ける。英文和訳では、原文の意味を考えるのは時間の無駄
であり、そんなことに時間を使っていては、試験で良い点はとれない。
たとえば、heは「彼」とは訳さず、片仮名の訳語は必要最小限のもの以外は使
わない。こう決めると、英文和訳の回路は使えなくなる。するととたんに、原文の
意味が気になるようになる。原文の意味を理解しなければ、訳文が書けない。だか
ら、必死になって読み、必死になって考える。英文和訳の回路から翻訳の回路に頭
が切り替わるのだ。
このようにして英文和訳調を意識して拒否しないかぎり、翻訳のつもりがいつの
間にか英文和訳に堕していく。それでは「文脈が続かなく」なり、「文が日本語と
して体をなさなくなる」との自覚もなく、もちろん、大量の訳注をつける必要を感
じることもなく、訳文の形だけは金子流(※1)に近づいていく。
翻訳者にとって英文和訳の回路は甘い罠である。だから、「原文の表面に忠実な
翻訳」は時代後れだと切り捨てるわけにはいかない。注意していなければ、裏口か
らそっと忍び込んでくる。
森鷗外は原著者が日本語で書くとしたらこう書くだろうと思える訳文を書くと語
った。「原文の表面に忠実な翻訳」を成り立たせる条件がほとんどの場合になくな
っているいま、この方法を目指す以外に道はないように思える。だがその際には、
漢文以来の伝統と学校英語でたたき込まれた考え方によって、「原文の表面に忠実
な翻訳」の亜流に、英文和訳調に流される傾向があることをしっかりと認識してお
くべきだろう。
(山岡洋一『翻訳とは何か―職業としての翻訳』)
(※1)金子流 ヘーゲル著「精神の現象学」(岩波書店・1971年刊行)を翻訳した金子武蔵氏がとった方法。本文は直訳に近く、それを多量の訳者注によって補う。
問1 本文中に「英文和訳式の構文に疑問をもたなかったからだ」とあるが、その理由を説明したものとして最も適当なものを次の中から選べ。
(A) 英文の構造には曖昧さがなく、文章を論理的にするためには英文の構造を変えない方がいいから。
(B) 英文の主語、述語、補語、目的語などを文法的に理解し、それに各々の日本語をあてがえば正確に訳せるから。
(C) 前後の文脈に関係なく一文ごとに独立した文章と考え、それを特定の構文にあてはまるのがてっとりばやい方法だから。
(D) 代名詞を見つけ、その代名詞を主語とした日本文を作成すれば、英語の文意に近づけるから。
(E) 単数・複数などの区別に厳密な英文を、理論的な文章を書くために不可欠だと考えたから。
問2 本文中に「違いが微妙なだけにきわめて厄介なのだ」とあるが、その理由を説明したものとして最も適当なものを次の中から選べ。
(A) 片仮名言葉は原語とほぼ同じ意味ではあるが、新たな日本語を増やすことになって学習者に苦労させることになるから。
(B) 片仮名言葉は原語の意味と完全には一致せず、ときには誤解を生じさせることになるから。
(C) 片仮名言葉は原文を正確に翻訳する1つの方法だが、日本語の構文の中に置くと別の意味が付け加わってしまうから。
(D) 片仮名言葉はすぐに外来語という日本語として定着し、将来にわたって独自の意味変化を遂げるから。
(E) 片仮名言葉は発音だけが先行して、日本語における厳密な意味を考える努力を捨てさせるから。
問3 本文中に「片仮名にしておけば安全だ」とあるが、その理由を説明したものとして最も適当なものを次の中から選べ。
(A) 英語についての知識を持っている人が多いから。
(B) 片仮名言葉でも日本語に訳したことにはかわりがないから。
(C) 片仮名言葉にしておけば、英語に知識のない人は文句をつけてこないから。
(D) 少なくとも誤訳ではない、と言い訳できるから。
(E) 変化の激しい日本語にすると、また別の訳語を見つける必要が出てくるから。
問4 本文中に「翻訳者にとって英文和訳の回路は甘い罠である」とあるが、このことを説明したものとして最も適当なものを次の中から選べ。
(A) いつのまにか英文和訳調に堕していても、それを批判する人はいない。
(B) 英文和訳調なら、単語の意味を考える苦労もなく簡単に訳文が書ける。
(C) 英文和訳調は楽なので、自覚していなければついつい使ってしまう。
(D) 学校英語で学んだ原文と訳語の一対一対応がいちばんいい方法だと信じている。
(E) 変な訳文でも国際コミュニケーションの場で有効だという利点がある。
問5 この文章の内容を説明したものとして、適当でないものを次の中から選べ。
(A) 一語一訳に従うことは、翻訳としては、安全でもなく、正しくもない。
(B) 学校で英語の成績が良かった者が、翻訳者に向いているとは限らない。
(C) 原文の意味を通すためには、かならずしも一語一訳の対応にこだわって訳さなくてもよい。
(D) 原文に逐語的な翻訳は、実際の日本語としてはかならずしも正しくない。
(E) 翻訳においては、意味が通るならば、どのように訳してもかまわない。
【解答・解説】
≪解説≫
<論点整理>
①日本の翻訳者、翻訳学習者の大部分は、原文と訳語の一対一対応や英文和訳式の構文を自然なものとして考えている。
②これには漢文訓読や日本の英語教育の影響がある。
③翻訳のあるべき姿は、「原文の表面に忠実な翻訳」ではなく、「原文の意味を伝える翻訳」である。
④そのためには英文和訳の頭の回路を翻訳の回路に切り替えなくてはならない。
⑤森鴎外の「原著者が日本語で書くとしたらこう書くだろうと思える訳文を書く」という方法を目指す以外に道はない。
問1 正解(C)
英文和訳式の構文に疑問をもたなかった。
=(同様)原語と訳語の一対一対応を素直に受け入れた
ということなので、最も適切なのは、(C)
(A) ⇒「英文の構造には曖昧さがない」という内容は本文中にはなく、「文章を論理的にする」必要性も訴えていないため誤り。
(B) ⇒本文は正確に訳すことの難しさを述べているため、「正確に訳せるから」が誤り。
(C) ⇒正解
(D) ⇒代名詞を主語とした日本文の話題は述べられていないため誤り。
(E) ⇒単数・複数に関しては言及されていないため誤り。
問2 正解(B)
本文中で片仮名言葉について述べられている部分を見てみる。
・原語とズレがある。
・国際コミュニケーションの場で障害になる。
・情報発信に役立たない。
これらの特徴から考えると、正解は(B)
問3 正解(D)
(A) 本文中に「片仮名の言葉に原語とズレがある」とあり、片仮名言葉の使用理由に英語の知識の有無は無関係であるとわかるため、誤り。
(B) 「片仮名言葉にしておけば安全だ」という問の答えにはなっていないため、誤り。
(C) 本文中に「片仮名の言葉に原語とズレがある」とあり、むしろ英語に知識のある人の方が片仮名言葉に違和感を覚えると考えられるため、誤り。
(D) 片仮名言葉を使う利点は、「原文の意味を考えなくても、機械的に翻訳できる」点にあることが本文中から読み取れる。それは、一語一対応の言葉を使用する利点と同じである。よって正解。
(E) 本文中に日本語の変化の厳しさは言及されていないため誤り。
問4 正解(C)
本文の流れを見てみる。
・英文和訳調を意識して拒否しないかぎり、翻訳のつもりがいつの間にか英文和訳に堕していく
⇒・翻訳者にとって英文和訳の回路は甘い罠である
※「いつの間にか英文和訳に堕していく」こと、それが「甘い罠」であるのだから、選択肢と照らし合わせると、英文和訳調は楽なので、自覚していなければついつい使ってしまう、が最もその意味を的確に捉えている。したがって正解は(C)
問5 正解(E)
本文中最終段落に、次のようにある。
「原文の表面に忠実な翻訳」を成り立たせる条件がほとんどの場合になくなっているいま、この方法を目指す以外に道はないように思える
また、本文中の別の箇所に、次のような表現がある。
・それは英文和訳であって、翻訳ではない
・英文和訳の回路から翻訳の回路に頭が切り替わる
・翻訳のつもりがいつの間にか英文和訳に堕していく
⇒「翻訳と英文和訳は別ものである」という流れがわかる。
したがって、筆者の中心的主張は翻訳の難しさにあることが明らかとなる。
よって、適切ではない選択肢は、(E)
(小林公夫『法曹への論理学<第3版>』早稲田経営出版、2004年[2006年第3版]、219頁~226頁)
【補足】日本人の配慮
現在の日本人は他人に対して配慮することに高い価値を置くという理想を持っているが、その理想と現実にはギャップがあるという。
イギリスの文芸評論家 William Hazlitの『Table talk』から、次のような言葉を引用している。
Man is the only animal that laughs and weeps, for he is the only animal
that is struck with the difference between what things are, and
what they ought to be.
「人間は唯一、笑いと涙を所有する動物である。それは人間が物事のありのままの姿と、そのあるべき姿との違いを受け止める唯一の動物であるからだ」
(小林公夫『法曹への論理学<第3版>』早稲田経営出版、2004年[2006年第3版]、44頁~45頁)












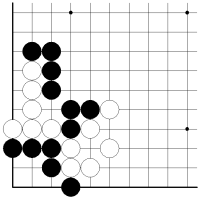







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます