(2024年2月7日投稿)
【はじめに】
今回のブログでは、次の参考書をもとに、古文の入試問題を見ておこう。
〇山村由美子『図解古文読解 講義の実況中継』語学春秋社、2013年[2019年版]
前回のブログでは、古文読解のためのワザ85個の一部を紹介したが、今回の入試問題は、そのワザを使って、解いてゆくことになる。
出典としては、『平家物語』『大鏡』『更級日記』『十訓抄』である。
興味のある人は、問題に挑戦してもらいたい。
【山村由美子『図解古文読解 講義の実況中継』(語学春秋社)はこちらから】
山村由美子『図解古文読解 講義の実況中継』語学春秋社
山村由美子『図解古文読解 講義の実況中継』語学春秋社、2013年[2019年版]
【目次】
山村由美子『図解古文読解 講義の実況中継』
【目次】
はじめに
本書の特徴と使い方
第一章 主語発見法
テーマ1 「は・が・を・に」は補ってよし!
テーマ2 本文にある「は・が・の」に騙されないで!
テーマ3 主語にあたる部分が丸ごとない場合
テーマ4 敬語もヒントに使おう!
テーマ5 男の子ワードと女の子ワード
テーマ6 お役立ち! 天皇ご一家専用ワード
第二章 人物整理法
テーマ1 埋もれた人物の発見法
テーマ2 主人公発見法
テーマ3 人間関係を整理する
第三章 状況把握法
テーマ1 舞台を意識せよ!
テーマ2 位置関係を意識せよ!
テーマ3 異空間を意識せよ!
テーマ4 場面の変わり目をつかもう!
第四章 具体化の方法
テーマ1 まずは正確に訳すこと
テーマ2 場面に応じた意味把握①~曖昧ワード編~
テーマ3 場面に応じた意味把握②~恋愛ワード編~
テーマ4 古文特有の比喩表現
テーマ5 指示内容の具体化
テーマ6 省略内容の補い
テーマ7 発想パターンと行動パターン
第五章 本文整理法
テーマ1 カギカッコ「 」をつけよ!
テーマ2 挿入句にまどわされないで!
テーマ3 内容を整理する
テーマ4 主題発見法
第六章 和歌読解法
テーマ1 5/7/5/7/7で区切って直訳!
テーマ2 和歌修辞
テーマ3 和歌の構造
テーマ4 和歌に情報をつけ足す
テーマ5 和歌の贈答
テーマ6 引き歌の処理法
第七章 入試問題ヒント発見法
テーマ1 出題者が示すヒントのありか
テーマ2 本文が示すヒントのありか
巻末付録
読解のワザ・チェックリスト
用言活用表
助動詞一覧表
助詞一覧表
主な敬語動詞一覧表
主な文法識別一覧表
さて、今回の執筆項目は次のようになる。
・古文の入試問題に挑戦~『平家物語』より<立教大[改]>
・古文の入試問題に挑戦~『大鏡』より<東京女子大[改] >
・古文の入試問題に挑戦~『更級日記』より<中央大[改]>
・古文の入試問題に挑戦~『十訓抄』より<日大[改] >
古文の入試問題に挑戦! 『平家物語』より
入試問題に挑戦! 『平家物語』より<立教大[改]>
次の文章は、天皇(君・主上)が大事にしていた紅葉の落ち葉を、下役人が掃除の際にかき集めて酒をあたためるためのたき火にしてしまった後の場面です。
(天皇専用ワード満載である。特に主語に注意しながら、読んでみよう)
これを読んで、後の問いに答えなさい。
奉行の蔵人、(ア)行幸より先にと急ぎ往いて見るに、跡かたなし。「いかに」と問へば、しかしかといふ。蔵人大いに驚き、「あなあさまし。君のさしも執し思しめされつる紅葉を、かやうにしけるあさましさよ。知らず、汝らただ今禁獄流罪にも及び、わが身も(イ)いかなる逆鱗にかあづからんずらん」と嘆くところに、主上いとどしく夜の御殿を出でさせ給ひもあへず、かしこへ行幸なつて紅葉を(A)叡覧なるに、なかりければ、「いかに」と御たづねあるに、蔵人奏すべき方はなし。ありのままに(B)奏聞す。(ウ)天気ことに御心よげにうち笑ませ給ひて、「林間煖酒焼紅葉といふ詩の心をば、それらには誰が教へけるぞや。やさしうも仕りけるものかな」とて、かへつて御感にあづかつし上は、あへて勅勘なかりけり。 (平家物語)
(注)
奉行の――係の
勅勘――天子からのとがめ。
問一 傍線の部分の(ア) 「行幸」、(ウ)「天気」の意味を、十字以内で記しなさい。
問二 傍線の部分の(イ)「いかなる逆鱗にかあづからんずらん」を、二十字以内で現代語訳しなさい。
問三 傍線(A)「叡覧なる」、(B)「奏聞す」の主語を記しなさい。
<立教大[改]>
【解答】
問一 (ア)天皇のお出まし(天皇のお出かけ)(7字)
(ウ)天皇のご機嫌(6字)
問二
(イ)どのような天皇のお怒りをこうむるだろうか(20字)
問三
(A)天皇(主上)
(B)(奉行の)蔵人
【解説】
問一 ワザ12 専用ワードで主語を見抜くワザ
天皇ご一家専用ワードを覚えて、天皇がらみの行動を把握!
問二
・「いかなる」は、「どのような」
「あづかる」は、「こうむる・受ける」
「逆鱗にあづかる」で、「天皇のお怒りをこうむる(受ける)」という意味。
「んず(=むず)」は推量、「らん(=らむ)」は現在推量の助動詞。
⇒「んずらん」と続けて用いられる場合は、「~だろう」と訳せばよい。
※「か……らん」で成立している係り結びを見逃さないように。
(「か」は疑問の係助詞)
問三
(A)「叡覧」は「天皇・もと天皇が御覧になること」
この文章には「もと天皇」は登場していないので、主語は「天皇」
(B)「奏聞す」は「奏す」と同義語。
「天皇に申しあげる」と訳す「言ふ」の謙譲語。
誰が「天皇に申しあげる」のかは、本文に書いてないが、前文と同じ主語の「蔵人」が主語と判断すること。
【現代語訳】
係の蔵人が、天皇のお出ましより先にと急いで行って見ると、(紅葉は)跡形もない。(蔵人が)「どうした」と尋ねると、(下役人が)これこれこういうことですと答える。蔵人はたいそう驚き、「あああきれた。天皇があれほどまでにご執心になっていた紅葉をこんなふうにしたとはあきれたことよ。知らないぞ、おまえたち(=下役人)は即刻禁獄流罪にもなり、この私自身もどのような天皇のお怒りをこうむるだろうか」と嘆くところに、天皇がいつも以上に早く夜の御殿(=寝室)をお出になるのももどかしそうに、その場所(=紅葉の所)へお出ましになって紅葉を御覧になると、(紅葉はすっかり)なかったので、(天皇は)「どうした」と尋ねなさるが、蔵人は天皇に申しあげようがない。(しかたなく蔵人は)ありのままに天皇に申しあげる。(すると天皇は)ご機嫌が特別よさそうにほほえみなさって、「『林間に酒をあたためて紅葉を焼く』という漢詩の心を、その者たち(=下役人)にいったい誰が教えたのか。(下役人は)風流にも振る舞い申しあげたなあ」と言って、逆に天皇のおほめの言葉をいただいた以上は、いっこうにおとがめなどはなかった。
(山村由美子『図解古文読解 講義の実況中継』語学春秋社、2013年[2019年版]、46頁
~51頁)
古文の入試問題に挑戦! 『大鏡』より
入試問題に挑戦! 『大鏡』より<東京女子大[改] >
次の文章は『大鏡』の中で夏山繁樹が語った昔話の一節です。二重傍線部の主語は誰か、それぞれ答えなさい。
延喜の御時に『古今』抄せられし折、貫之はさらなり、忠岑や躬恒などは、御書所に召されて候ひけるほどに、四月二日なりしかば、まだ忍び音の頃にて、いみじく興じおはします。貫之召し出でて、歌つかうまつらしめ給へり。
ことなつはいかが鳴きけむほととぎすこの宵ばかりあやしきぞ無き
それをだにけやけきことに思ひ給へしに、……(後略)
(注)
延喜――平安前期の醍醐天皇時代の年号。
古今――古今和歌集のこと。
御書所(みふみどころ)――宮中で書籍の管理などをした役所。
【答】
①召し出で~醍醐天皇
②思ひ~夏山繁樹(語り手)
【現代語訳】
醍醐天皇の御治世に(天皇が)『古今和歌集』をお作りになった際、貫之は言うまでもなく、忠岑(ただみね)や躬恒(みつね)などは、御書所にお呼び出しを受けてお控えしていたときに、四月二日であったので、まだ時鳥の初音(はつね)の頃で、(天皇はその初音を)たいそう楽しんでいらっしゃる。貫之を(天皇が)お呼び出しになって、歌を詠ませ申しあげなさった。
他の夏はどのように鳴いていたのだろう。ほととぎすがこの宵ほど不思議な(ぐらい素敵に鳴くのを聞いた)ことはない。
そのことでさえ異例のことだと(私は)思いましたのに、……
(山村由美子『図解古文読解 講義の実況中継』語学春秋社、2013年[2019年版]、67頁
~70頁)
古文の入試問題に挑戦! 『更級日記』より
第三章 状況把握法
次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。
入試問題に挑戦! 『更級日記』より<中央大[改]>
夜中ばかりに、(1)縁に出でゐて、姉なる人、空をつくづくとながめて、「ただ今行方なく飛び失せなばいかが思ふべき」と問ふに、なまおそろしと思へるけしきを見て、ことごとに言ひなして笑ひなどして、聞けば、傍らなる所に、前駆おふ車とまりて、「荻の葉、荻の葉」と(2)呼ばすれど答へざなり。呼びわづらひて、笛をいとをかしく吹きすまして、過ぎぬなり。
A 笛の音のただ秋風と聞こゆるになど荻の葉のそよとこたへぬ
と言ひたれば、「げに」とて、
B 荻の葉のこたふるまでも吹きよらでただに過ぎぬる笛の音ぞ憂き
(更級日記)
(注)荻の葉――隣家の女性の名前
問一 傍線部(1)「縁」とあるが、本文中「縁」にいるのは誰か。次の選択肢の中からすべて選びなさい。
ア作者 イ姉 ウ車の主 エ車の主の従者 オ荻の葉
問二 傍線部(2)「呼ばすれど」とあるが、誰が誰に「呼ばすれど」か。問一の選択肢の中から、それぞれ選びなさい。
問三 和歌A・Bはそれぞれ、誰が誰に詠んだものか。問一の選択肢の中から、それぞれ選びなさい。
<中央大[改]>
【解答】
問一 ア・イ
問二 ウがエに
問三 A アがイに B イがアに
【現代語訳】
夜中ぐらいに、(姉と私は)縁側に出て座って、姉である人が、空をしみじみともの思いに沈んで眺めて、(姉が)「今すぐ(私が)どことも知れず飛んでいなくなったならば、(あなたは)どう思うだろう」と尋ねるので、(私が)なんとなく恐ろしいと思っている様子を(姉が)見て、(姉は)別のことで紛らわすように言って笑ったりして、(ふと外の様子を)聞くと、隣にある家に、先払いをする牛車(ぎっしゃ)が止まって、(車の主が従者に)「荻の葉、荻の葉」と呼ばせるけれど(荻の葉は)答えないようだ。(車の主は)呼びあぐねて、笛をとてもすばらしく澄んだ音色で吹いて、過ぎて行ってしまうようだ。
笛の音がまさしく秋風のように(ステキに)聞こえるのに、どうして荻の葉は秋風にそよぐように「そうよ」と答えないのでしょう。
と(私が姉に)言ったところ、(姉は)なるほどと言って、
荻の葉が答えるまで吹いて言い寄りもしないで、そのまま過ぎて行ってしまう笛の音(の主)が冷淡だ。
(注)
歌の「そよ」
――掛詞
①風に吹かれて葉が「そよそよ」音をたてる意
②「荻の葉さん!」と呼ばれて「其(そ)よ(=そうよ)」と返事をする意
(山村由美子『図解古文読解 講義の実況中継』語学春秋社、2013年[2019年版]、106頁
~111頁)
古文の入試問題に挑戦!~『十訓抄』より
入試問題に挑戦!~『十訓抄』より<日大[改] >
最後に、今までのワザを駆使して、入試問題に挑戦してみよう!
次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。
大納言行成卿、いまだ殿上人にておはしける時、実方中将、いかなる憤りかありけん、殿上に参り(A)会ひて、いふ事もなく、行成の冠を打ち落として、小庭に投げ捨てけり。行成少しもさわがずして、主殿司(とのもりづかさ)を召して、「冠取りて参れ」とて、冠して、守刀より
笄(かうがい 注1)ぬき取りて、鬢(びん)かいつくろひて、(B)居なほりて、「いかなる事にて候ふやらん、たちまちにかうほどの乱罰にあづかるべき事こそ覚え侍らね。その故を承りて、後の事にや侍るべからん」と、ことうるはしくいはれけり。実方は、しらけて逃げにけり。
折しも小蔀(こじとみ)より、主上、御覧じて、「行成は(C)いみじき者なり。かくおとなしき心あらんとこそ思はざりしか」とて、そのたび蔵人頭(くらうどのとう)あきたりけるに、
(D)多くの人を越えてなされにけり。実方をば、中将を召して、「(E)歌枕見て参れ」とて、陸奥国(みちのくに)の守(かみ)になしてぞつかはされける。やがてかしこにて失せにけり。実方、蔵人頭になられでやみにけるを恨みにて、執とまりて雀になりて、殿上の、小台盤(注2)に居て、台盤をくひけるよし、人いひけり。一人は不忍によりて前途を失ひ、一人は忍を信ずるによりて褒美(ほうび)にあへるたとへなり。(十訓抄)
(注)
1 笄――髪をかきあげるのに使った道具。男子の場合、刀の鞘にさしておく。
2 小台盤――食器を乗せる小さな台。
問一 本文中から挿入句を抜き出しなさい。
問二 傍線部A、Bの主語は誰か。本文中から抜き出しなさい。
問三 傍線部Cを現代語訳しなさい。
問四 傍線部Dは誰がどのようにしたことか。その説明として最も適当なものを次の中から一つ選びなさい。
① 帝が、蔵人頭をやめさせて代わりに行成を任命した。
② 行成が、空席となった蔵人頭の地位を帝に願い出た。
③ 蔵人頭が、みずからの後任として行成を推薦した。
④ 帝が、欠員のあった蔵人頭の地位に行成を抜擢した。
⑤ 行成が、蔵人頭の地位を他人に譲ろうとした。
問五 傍線部E「歌枕見て参れ」とあるが、そこには帝のどのような意図が込められているか。その説明として最も適当なものを次の中から一つ選びなさい。
① 和歌を学ばせよう
② 左遷しよう
③ 遠くでかくまろう
④ 骨休みさせよう
⑤ 昇進させよう
問六 この逸話を通して編者が最も言いたいことは何か。
<日大[改] >
【設問解答】
問一 いかなる憤りかありけん
問二 A実方中将 B大納言行成卿
問三 とてもすばらしい人物である。
問四 ④
問五 ②
問六 忍耐することは大切だ。
【解説補足】
問二
A:第一段落は、行成と実方が争っている場面だから、事実としてはこの2人が「会ふ」ことを言っている。
問題はここでの書き方。
事実は同じでも、「2人が会う」「行成が実方に会う」「実方が行成に会う」、いずれでも言える。ここでは誰が主語になって書いてあるかの把握が大事。
直前に挿入句「いかなる憤りかありけん」がある。挿入句は本筋から離れた内容なので、「いかなる……けん」までを本文からいったん退ければ、「実方中将、殿上に参り会ひて(実方中将が、殿上の間に参上し会って)」となる。これで実方が主語だと判明できる。
問三
・ワザ40と81を使用。
「いみじ」は曖昧ワードだけど、「 」内の残りの部分に注目すると、「かくおとなしき心あらんとこそ思はざりしか(¬=このように思慮分別のある心があるだろうとは思わなかった)」と褒めているから、「いみじ」も「すばらしい」「立派な」など、プラスの方向で訳せばいいことがわかる。
問五
・ワザ82「着眼箇所発見のワザ 「 」の後の行動をチェックしてウソを見抜け!」を使用。
このセリフは言葉どおり受け取っていいのか、がポイント。
歌枕(=名所のこと)を見るだけなら、陸奥国の守にわざわざ任命しなくてもいいはず。
つまり、セリフと直後の行動とが食い違っているということ。
一般的に、地方職は中央職に比べて、当時は格下。ここは、カッとなりやすい実方の欠点を目撃した天皇が、実方を左遷させようとしているところ。
問六
・ワザ85「着眼箇所発見のワザ 読解系問題の答えは、必ず本文中に書いてある!」を使用。
⇒ここは、最後に注目。
「不忍(忍耐力がない)」か「忍を信ずる(忍耐の大切さを信じる)」かによって、幸不幸がわかれたたとえ話だ、というのだから、要するに、「忍」の大切さを言いたかった。
【現代語訳】
大納言行成卿が、まだ殿上人でいらっしゃったとき、実方中将は、どのような怒りがあったのだろうか、殿上の間に参上し(行成に)会って、何も言わずに、行成の冠を打ち落として、小庭に投げ捨てた。行成は少しも騒がずに、主殿司をお呼びになって、「冠を取って参れ」と命じて、(主殿司が取って来た)冠をかぶり直して、守刀から笄を抜き取って、鬢を直して、居ずまいを正して、(行成は)「どのような事でございましょうか、突然これほどの乱暴な罰を受けなければならない事は(身に)覚えがございません。(罰するにしても)その理由をお聞きして、その後の事であるべきでしょうか」と、理路整然とおっしゃった。実方は、きまりが悪くなって逃げてしまった。
ちょうどそのとき小蔀から、天皇が、御覧になって、「行成はすばらしい人物である。(行成に)このように思慮深い心があろうとは(私は)思わなかった」とおっしゃって、その頃蔵人所の長官(の役職)が空席になっていたので、(天皇は行成を)多くの人を飛び越えて任命なさった。実方を、中将の官職をお取り上げになって、「歌枕を見て参れ」とお命じになって、陸奥国守にして左遷なさった。(実方は)そのままそこ(=陸奥国)で亡くなってしまった。実方は、蔵人所の長官になれずに終わってしまったことを恨みに思って、執着がとどまって(生まれ変って)雀になって、殿上の間の小台盤にとまって、台盤(の食物)を食べていたということを、人は言っていた。一人(=実方)は忍耐がなかった事によって前途を失い、一人(=行成)は忍耐(の大切さ)を信じる事によって褒美にめぐりあったというたとえ話である。(十訓抄)
※何となく雰囲気で解くやり方から、確実な解き方へとステップアップでき、解き方をイメージできれば大成長。
あとは、本文や問題に応じて、最も有効なワザをパッと思い出せるように、「読解のワザ・チェックリスト」を使って、ワザをしっかり身につけ、そして、身につけたワザを、他のいろんな文章でもどんどん使って、さらに読解力アップをめざしてください。
(山村由美子『図解古文読解 講義の実況中継』語学春秋社、2013年[2019年版]、285頁~
~292頁)










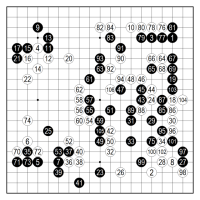
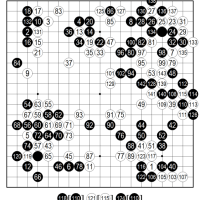
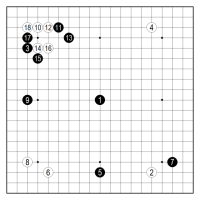
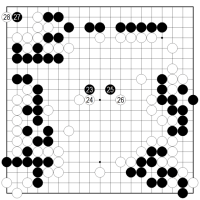
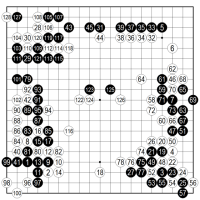
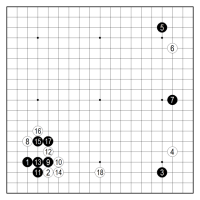
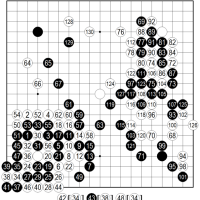
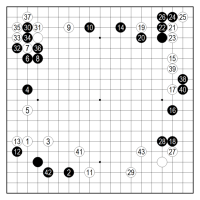
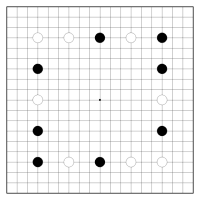
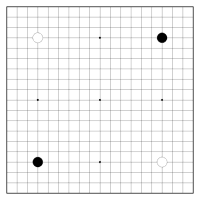
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます