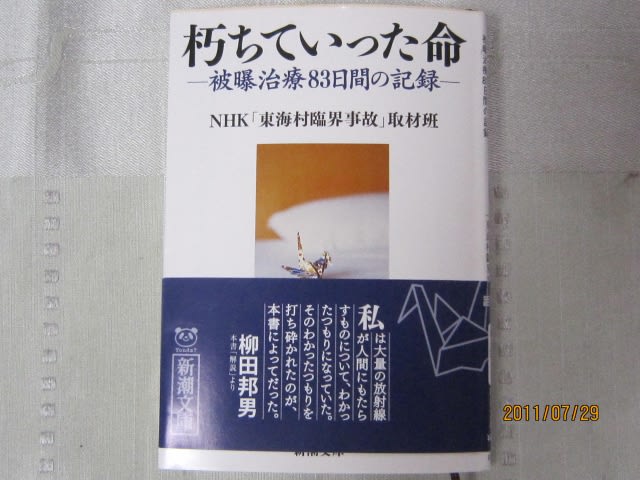
1999年9月30日 茨城県東海村 核燃料加工施設 JCOにて 午前10時35分 ウラン溶液を濾過していたところ 突然 パシッという音とともに青い光が放たれた。臨海に達した時に放たれる「チェレンコフの光」だった。その瞬間、放射線のなかでももっともエネルギーの大きい中性子線が作業をしていた二人の作業員の身体を突き抜けた。その作業員の一人 Oさんは、更衣室に逃げ込んだ後、すぐに嘔吐し、意識を失った。
この二人を助ける為に、日本中の権威と実力のある医者が集まり、かつて無いほどの厳重な無菌室で、治療に取り組んだ。しかし 致死量を遥かに越えた被爆をした患者への治療方法はいまだ無く、手探りの中での治療であった。
放射線の生体への影響は、実は細胞内の染色体への異常を引き起こす事であった。すなわち O さんの身体はもう細胞分裂により元と同じ細胞を作れなくなってしまったのである。
それでも医師団は考えられる様々な治療を試みてゆくが、それらも全て効果なく、 O さんは徐々に弱っていってしまう。身体はボロボロになってゆくが、思考ははっきりとしておりそれが却って O さんの苦しみを更に切なく感じさせる。 同時に O さんの家族、また手当てする看護師の思いも含めて一層、状況の緊迫感を感じさせてくる。医師は口には出さないが、看護師は一体この治療は誰の為、なんの役に立つのか、ただ O さんの苦痛を長引かせるだけではないかと疑問をもち始める。ある看護師はこう思った。『むかし広島にある原爆の資料館で見た被爆者の写真を思い出した。50年以上前、原子爆弾で被爆した人たちも、こういう状態立ったのだろうかと。』 一方家族は最後まで団結して期待し、はげましあっている。
83日目に O さんは息を引き取った。あらゆる治療は多少延命には役立ったのかもしれないが、却って苦しみを長引かせただけかもしれない。いや、延命できたのは治療の効果ではなく、 O さんの生命力のお陰であったかもしれない。そう思いたくなるほど、医学は放射線障害に対してまだまだ無力なのである。
我々がこの様な直接放射線を浴びる事は考えられない。しかし、放射線微粒子を体内に取り込んだときの内部被爆は可能性は十分にある。ところが、原発がいかに安全だと云われても、万一の際の医療体制はまだまだなのである。
目の前の経済と傲慢な生活をとるか一方貧しくとも持続可能な豊かな生活を選ぶかは、われわれに突きつけられた選択肢である。









